チャーリー・ガードちゃんが世界に問いかけたこと (2)
(2)医学系研究生が論文に
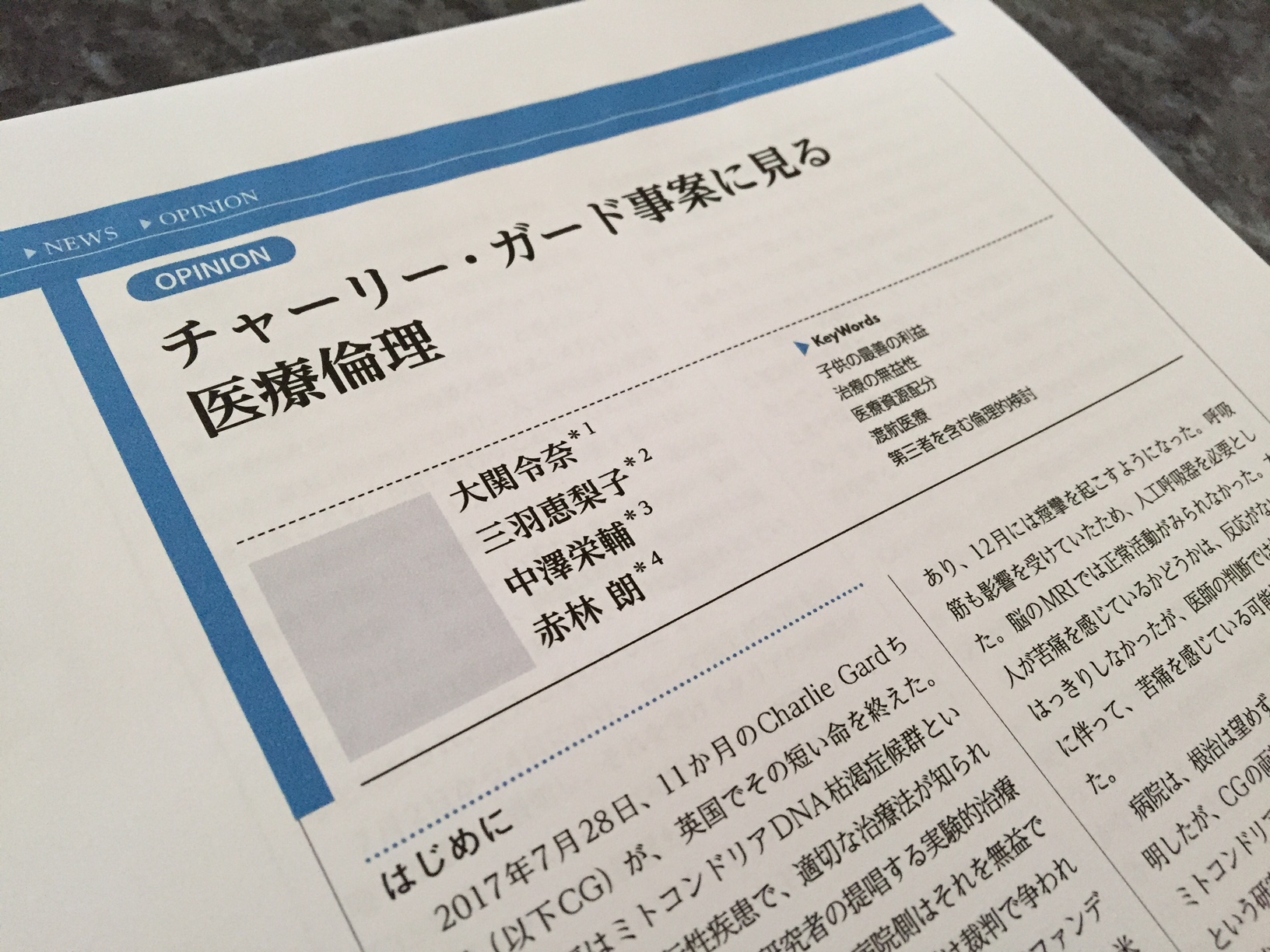
難病を患い治癒の見込みがないと診断された赤ちゃんの延命治療を巡って親と病院が争い、世界的に注目された英国の法廷闘争は、日本の医療関係者の関心も集めました。裁判所の決定により生命維持装置を外された赤ちゃんが亡くなって約1カ月後、「週刊日本医事新報」(2017年8月26日号)に論文「チャーリー・ガード事案に見る医療倫理」を発表した東京大学大学院医学系研究科(医療倫理学)の大関令奈さんと三羽恵梨子さんに話を聞きました。
大関さんは医学博士課程に、三羽さんは専門職学位課程に席を置いています。論文は同科の中澤栄輔講師と赤林朗教授との共著です。論文では、チャーリーちゃんを米国に渡航させて実験的な治療を受けさせることを希望した親と、チャーリーちゃんの治癒は見込めないとし延命治療の停止と「尊厳ある死」を提案した病院側の法廷での議論について、以下の4点の論考がなされています。
4つの論点
1)子供の最善の利益
2)治療の無益性
3)医療資源配分
4)渡航医療
1番目の論点である、治療の意思決定能力のない「子供の最善の利益」を誰がどのように決めるべきか、という問題については、まず英国では1989年に施行された法令「The Children Act」以来、「理論的・制度的・実践的議論の蓄積があり、parental responsibility(親の責任)が定義されている」と言及。親に対して「子の最善の利益において医学的な決定やその中止などを行う権利を認めている」とした上で、チャーリーちゃんの事案のように医療者と親の考える「子の最善」が異なる場合は、倫理委員会や調停、場合によっては裁判所の判断が適用されると説明しています。
司法の関与については、「各国で考えが異なる」とした上で、法廷での手続きのデメリットについて「現実的には達成不可能な理論的結論を導くことがある」「費用と時間が膨大にかかる」と指摘しています。
2番目の論点である、「治療の無益性」の判断については、治療効果が立証されていない薬の投与に対する米国と英国の考え方の違いに言及しています。
今回、チャーリーちゃんに対して両親が希望した治療は「研究段階の薬」であり、チャーリーちゃんのような患者への「投与経験はおろか、動物実験さえ行われていない状況であった」と説明。裁判ではこれらを根拠に、チャーリーちゃんにこの治療を行わないことが決定されました。しかし、論文では「米国では近年、重篤な疾患において、治療の代替案がない場合に、患者がリスクを許容すれば研究段階の治療でも試されるべきであるという」社会情勢の中で、「新薬治療の申請を行うケースがある」としています。
さらに、「米国には障がいを理由に子供の治療を制限することを禁じた法律がある」とし、「病気を持った子どもに対する治療の無益性の考え方に、このような歴史的背景が影響を与え、英国と米国の違いが生じていると推測される」としています。
「治療の無益性」 判断の根拠は?
消化器内科と緩和医療科の医師としての臨床経験を持つ大関さんは、チャーリーちゃんの事案で一番興味を持ったのがこの「治療の無益性」についてだったと言います。チャーリーちゃんの両親が治療を希望していた米国の医師が、研究段階の治療による病状の改善について「可能性はある」とした点を挙げ、大関さんは「治療は無益であるという科学的データがないと、無益性の判断は出来ないのではないか」と考えたそうです。
さらに、「無益性の判断について裁判所が関与することに疑問を持ちました」と言います。日本の臨床の現場では、「治療に利益があるかどうかという話は、患者さんやご家族とすることは難しいのが現状。治療が有効ではないと感じながらも治療の止めどきについて悩む医師も少なくないです」と説明。
チャーリーちゃんのような患者が日本の病院で治療を受けている場合は、「医師はまず、有効な治療はないとご家族に伝えた上で、ご家族の意思を尊重すると思います。人工呼吸器は外さず、そのまま延命治療を続けるでしょう。ご家族が希望すれば、米国での幼児の心臓移植の例のように寄付を募って実験的な治療を受けに渡航する可能性もあると思います。意見が対立する場合は話し合いを重ね、それでも結論が出ない場合は病院の倫理委員会に判断を任せることになるでしょう」と言います。
3番目の論点は、「医療資源配分」です。チャーリーちゃんの両親は、米国で治療するための資金を寄付によって集めていました。が、論文では「両親と病院の意向が対立してから、最終的に人工呼吸器が中止されるまでの期間に行われた治療は、公的保険でカバーされていることは、医療資源配分の観点から問題があるのではないかという指摘がある」とします。
大関さんは公費負担の英国の医療制度について、「疾病ごとに使える治療法が厳密に決められていますので、医師が無益だと判断する治療はできないと思います」と説明。「判決文で判事が『コストの問題ではない』と何度も述べており、『命の値段』という話になるのを避けたのではないでしょうか」と推測します。
論文の4番目の論点は、「自国で認められていない治療を、その治療が認められている別の国へ渡航して受けることが許容されるのかという問題」です。チャーリーちゃんに対しては、米国とイタリアの医師らが治療の提供を申し出ました。しかし、チャーリーちゃんは渡航を禁止されました。この点について、論文では「渡航医療を禁止することは、2つの重要な自由を侵害すると考えられる。1つは、旅行する自由、もう1つは治療についての意思決定をする自由」と指摘。その上で、「通常、患者が自らの意向で渡航して治療を受けることは禁止されていない」が、チャーリーちゃんの事案のように「親が子を渡航させて治療を受けさせることには問題がある場合がある」とし、「子を国外に連れていくことで、子が害を被ることから守るための法律を親が無視することになるとしたら、それは許されないと考えられよう」と結論付けています。
裁判所の判断は妥当か?
論文のもう1人の執筆者である三羽さんは、他の大学院で博士前期課程(哲学専攻)を修了した後に東大大学院医学系研究科の専門職学位課程に入学し医療倫理学と公衆衛生学を専攻しています。
三羽さんはまず、英米メディアによる連日の報道、裁判所の判決や病院などのプレスリリース、両親がインターネット上での寄付金を募った「クラウド・ファンディング」、ネット上における専門家による議論など、様々な発信がなされていた点に着目したといいます。しかし、それでもなお「この事案を十分に理解するのは難しいかもしれません。たとえば、病院と両親の間の合意点や対立点、判決の意味などです。これらを一つ一つ解きほぐしながら理解していく必要があると考えます」と話します。
日本で報道されたニュースを読む中で感じたのは、「尊厳死」という言葉がセンセーショナルに書かれ過ぎているということだったと言います。「裁判では、『尊厳死』については争われていませんでした。病院側と両親はともに、チャーリーちゃんの当時の状態が、生命維持に値するようなQOL(quality of life)を保持できていないと考えていました。その点では合意があったのです。そのうえで、即時に延命治療を中止するか、実験的な治療に賭けてみるか、どちらがチャーリーちゃんの『最善の利益』であるかが争われたのです」。
裁判では、最終的にチャーリーちゃんの延命治療の停止が決定されました。三羽さんは「裁判所は、患者に対してこのような場合は生きる価値があり、このような場合は死なせてもよいといった判断はしませんでした。実験的治療が無益かどうか、実験的治療に伴う延命が苦痛を生じさせるかどうかの判断に注力しました」と指摘。「尊厳死の基準や、資源配分の問題といったことは、たくみに論点からはずされていました。判例としての影響力を考えれば、妥当です」と話します。
チャーリーちゃんと社会のつながり
裁判所の決定を最終的に両親が受け入れたことにより、チャーリーちゃんの人工呼吸器が外され、間もなくチャーリーちゃんは息を引き取りました。1歳の誕生日を迎える1週間前でした。三羽さんはその死をこう受け止めました。
「チャーリーちゃんを助けようと、ローマ教王や米国大統領を含むたくさんの人々が動きました。両親も医療者も献身的にケアをしました。チャーリーちゃんは社会とつながっており、そこには人間的な営みがあったと思います。裁判所の決定は、その営みを否定するものではありません」
医療ジャーナリスト。札幌市生まれ、ウエスタンミシガン大卒。1992年、北海道新聞社入社。室蘭報道部、本社生活部などを経て、2001年東京支社社会部。厚生労働省を担当し、医療・社会保障問題を取材する。2004年、がん治療と出産・育児の両立のため退社。再々発したがんや2つの血液の難病を克服し、現在はフリーランスで医療問題を中心に取材・執筆している。著書に「がんと生き、母になる 死産を受け止めて」(まりん書房)
