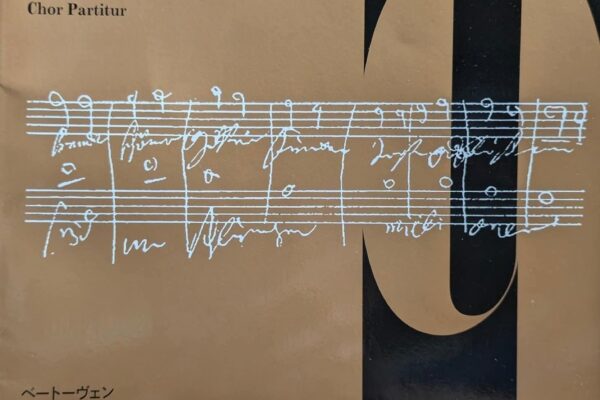シェイクスピアの2つの「問題劇」『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』 鑑賞記 2023.10.28/11.9
◆『尺には尺を』(Measure for Measure 1604)
新国立劇場中劇場 2023年10月28日


**********
今回、新国立劇場で、鵜山仁の演出により、ダブルキャストではなく。シングルキャストの2作品出演というかたちで上演されたシェイクスピアの中期の前後して書かれた「問題劇」Problem playsと呼ばれる2作品を見てきた。
まずは最初に見た『尺には尺を』について。
シェイクスピアの喜劇は、舞台では『夏の夜の夢』(ロイヤル・シェイクスピア劇団)『十二夜』(歌舞伎版)、悲劇は平幹二朗・蜷川の『リア王』ぐらいしか見ていない。しかし、オペラや映画になった諸作品、さらにはテレビの舞台中継も入れるならば、喜劇、悲劇とも相当数の作品を見ている。
しかし、今回の2作はなかなか舞台上演も翻案もされないもので、なんの予備知識もなく見たのだけど、なんとも不思議な作品であった。喜劇と言いつつ、それほど笑えない。浪漫喜劇からの転換期にあると言われるように、なるほど「ダーク・コメディ」でもあるし、喜劇とも悲劇ともカテゴライズしにくく、取ってつけたような終わり方をすることから「問題劇」と言われるわけであるが、シェイクスピアのシニカルな人間観察によって、人間の多様な内面があぶり出された作品ということになるのだろうか。
シリーズで鵜山仁とともにシェイクスピアの史劇に取り組んできた俳優陣だけあって、みな堂に入ったもので、安心して見ていられた。
ざっとあらすじを追いつつ感想を。
(なお、この投稿は「鑑賞記」であり、原作にはいまだ触れていません。とりわけ『終わりよければすべてよし』に関しては原戯曲を読むことが必要であり、その読書に基づき、本稿の加筆・改訂の可能性があることを申し添えておきます。)
*****
ウィーンの公爵ヴィンセンシオ(木下浩之)は性的風紀の乱れを取り締まるため、自分は留守を装い、代理を厳格なアンジェロ(岡本健一)に任せ、自分は実はウィーンにいて修道僧に変装して状況を見守る。
この辺の経緯は『コシ・ファン・トゥッテ』を思わせるところがあって、王政があった頃の喜劇の定番の仕掛けとして変装によって起こる状況を観察するような設定があったのかなとも思える。
若い貴族クローディオ(浦井健治)は婚約者のジュリエットとの婚前交渉でジュリエットは妊娠、それにより代理のアンジェロから死刑を宣告される。この過激な突然の宣告はラストのヴェンセンシオの求婚と並び、前後半の焦点になっている。
クローディオの友人で変わり者のルーシオは修道院にいるクローディオの妹イザベラ(ソニン)を訪ね、アンジェロに会って死刑の取り消しを懇願するように頼む。
イザベラがアンジェロに面会し慈悲を求めると、アンジェロはイザベラに惚れてしまい、自分と寝るならばクローディオを助けてもよいと持ちかける(この辺は権力を笠に着たセクハラという『トスカ』などの19世紀イタリアオペラのパターンを思わせる)。
イザベラは断固拒否し、刑務所に行き、兄クローディオに潔く死ぬよう言う。クローディオは死ぬのはいやだと言って、イザベラにアンジェロと寝るように頼むが、イザベラは拒否する。
修道士に変装した公爵はアンジェロに「ベッド・トリック」を仕掛ける。アンジェロのかつての婚約者でアンジェロをまだ愛しているマリアナ(中島朋子)を呼び、イザベラがアンジェロの誘いに乗ったように見せかけ、イザベラをマリアナとベッドで入れ替わらせた。
計画はうまく行ったが、アンジェロはイザベラの約束を破り、クローディオを処刑しようとする。公爵は病死した囚人の首をクローディオの首のように見せかけ、アンジェロに届け、クローディオは死んだと思わせる。
そして、公爵は修道士の変装をやめて、外国からウィーンに「帰国」し、イザベラとマリアナに真実を訴えさせるが、アンジェロは容疑を否認する。
そこで公爵は再び修道士に化け、改めて公爵であることを明かしたので、とうとうアンジェロも追い詰められる。アンジェロをマリアナと結婚させた後、公爵はアンジェロに「尺には尺を」でクローディオと同じこと(婚前交渉)をしたアンジェロに死刑を宣告する。
しかし、クローディオが生きて現れ、アンジェロは罪を許される。
最後5分前のここまでを見て、喜劇というより、法廷劇風ミステリとして見るなら、二転三転する展開は緊張感もあり鮮やかで引き込まれるし、現代劇に翻案も可能な内容で、さすがシェイクスピアだと思って見ていた。
*****
ところがである(ネタバレ)
最後に驚きの展開になり、公爵はイザベラに結婚を申し込むのである。もしかして、最初から公爵はイザベラを狙っていて、ここまでの経緯はすべて公爵が描いた筋書きだったのか?それとも途中からだんだんイザベラに惚れてしまって方針換えしたのか?このシニカルでブラックなところが狙いなのか?
しかし、イザベラは何も答えないところで幕切れ。このイザベラの反応は、それを無言の承諾ととることもできるし、今回の鵜山仁の演出では公爵に強引に手を取られて奥に引っ込むイザベラがこちらを振り向いて「ナニコレ?」みたいな怪訝な表情をすることで終わっていた。
こちらもあっけに取られていて、これじゃ、せっかくの経緯が台無しではないのか、高潔で寛大な人格者としての公爵像を最後に見せてめでたしの方がいいのに、と思ったものの、帰ってからパンフレットの英文学者の安達まみさんの解説を読んでいるうちに、徐々に見方が変わってきた。
*****
安達さんによると、これらの登場人物たちの評価は時代を経て変わってきたそうなのである。
公爵はかつては「神のごとく賢く、慈悲深く道徳的な導き手」とされていたのに、今は「父権性社会の傲慢さをぷんぷんさせて、体制側の監視により、ひとを操作する卑劣漢へと評価は傾いている」そうだ。
そして、イザベラは「かつては純潔な女性の理想像と賞賛されたが、一旦は欲求不満で不寛容な堅物とされたのち、いまはフェミニスト的な抵抗を体現する人物として評価を高めている。20世紀までは下層社会の場面や性的な表現は品位に欠けるとして削除されがちだったが、現在は、社会的ヒエラルキーや性的抑圧への抗議の表象として活用されるようになった」と。
なるほど。
つまり、鵜山仁の演出にしてもひとつの解釈であって、これらの人物に全く違う光を当てることもできるわけで、違和感のある最後の5分にしても、色々な解釈が可能で、それは相互の関係性が変わることでもあり、イザベラへの見方が変われば公爵への見かたも変わるということになりそうである。
マリアナやもっとも自己中心的で頑なな「ひどい」人物に思えるアンジェロについても、テクスト読解や演出により、別の視点がまだまだありそうである。
変装した修道士を公爵とわからず、公爵の悪口を言いまくるクローディオの友人のルーシオを巧みに配しているのも気になるところである。
安達さんによれば、『から騒ぎ』に出てくるクローディオ、あるいはジュリエットといった他の作品と同名の人物が出るのも明らかにシェイクスピアの意図があるだろうとのことである。
いまは、多様性の時代で、なんでも多様性と言ってしまえばまとまってしまう傾向があるけど、総じて優れた作品ほど一筋縄ではいかない多義的な解釈を誘うもので、この作品も謎の多い含蓄に富む作品だと思った。
鵜山さんは、善悪を単純に決めることはできず、今回の作品でも善悪がときに助け合ったりするのに驚いたし、人間世界でそれらがせめぎ合うところ、余計なものと感じることもバランスがとれているのかもしれないという宇宙的な視点もシェイクスピアにはある気がするとインタビューで言っていた。
なお、ワーグナーの初期の喜劇オペラ『恋愛禁制』Das Liebesverbotだけど、スッペのようなロッシーニのような、そしてワーグナーらしいところもすでに出ているあのわちゃわちゃした感じで始まる序曲(カスタネットにトライアングルも使っている)は聞いていて、内容は知らなかったのだけど、この『尺には尺を』が原作であることを今回初めて知った。これは見なくては。ワーグナーがこの劇の何に関心を寄せたのか、どう改変されているのかも興味あるところである。Blu-rayが一種出てるので、さっそく注文した。
さらにトリビアを言うと、『恋愛禁制』の自筆譜はヒトラーが所有していて最後に地下壕に持ち込んで、結局行方不明になったままだそうである。

◆『終わりよければすべてよしAll’s well that ends well (1602-3)』
新国立劇場中劇場 2023年11月9日
**********
これがまた『尺には尺を』に続いてやっかいな代物であった。上演回数が少ないのも、わかりにくいところの多い「問題劇」だからだろうか。あまり喜劇でもなく、恋愛→結婚が基本にあるけれど、ロマンスとは程遠く、およそ嚙み合わない恋愛に、若者たちの自己中心的なな打算・・・だから、最後に「終わりよければすべてよし」と言われても、表向きの体裁であって、「これでいいわけがなかろう」ともなるのである。
パンフレットの二人の英文学者、前沢浩子さんと井形洋さんがまたずいぶん違うことを言っている。井形さんのは文意がわかりにくいので、前沢さんの文に拠って話を進めると、ヒロインのヘレナによって二回言われるAll’s well that ends wellに対し、最後フランス王によってAll yet seems well(すべてよいように見える)と言われるのだから、作者とて両義的な意味でこのタイトルを掲げていることは明白であるだろう。
ざっとあらすじを。夫を亡くしたルシヨン公爵夫人(那須佐代子)は縁のあるフランス王(岡本健一)の申し出でフランス王のところに後継ぎの息子バートラム(浦井健治)を送る。
王は病に侵され、余命はわずかと見られていた。公爵夫人は他界した名医の娘ヘレナ(中島朋子)を侍女として雇い、目をかけていた。ヘレナは身分違いのバートラムに恋していて、また父の遺したどんな病にも効く処方箋を持っていたので、自分ならフランス王も治せると言って、公爵夫人から許可をもらい、後を追ってパリへ向かった。
ヘレナはフランス王に謁見し、父の完璧な処方箋で見事王の病を治して見せる。
褒美に何でも望むがよいと言われたヘレナは、バートラムとの結婚を所望する。
王の命令は拒否できないので、バートラムは渋々承諾するものの、ヘレナに対し全くその気がないので、初夜も蹴って、志願して早々と戦地のフィレンツェへ行ってしまう。残された手紙には「(ヘレナが)ぼくを父とする子を産めば、そしてこのいつもしっかりはめている指輪を手に入れれば(つまり、そんなことは不可能だと確信している)、ぼくを夫と呼んでいい。でも、そんなときは絶対来ないぞ」とあった。
こんな風に書くと、面白そうに聞こえるだろうか?
しかし、公爵夫人のところにいる昔ながらの老貴族ラフュー、道化のラヴァッチ、バートラムに付いていく臆病で嘘つきな兵士のぺーローレス(おしゃべりでセリフも多い)と言った色々な脇役たちが何かとあれこれ言うものだから、こちらの頭も錯綜してきて混乱してくるのである。シェイクスピアはそういう脇役の言葉に名セリフがあるのだろうが、やはりテクストを読んでいないと、芝居の時間の流れの範囲では追えないことを痛感した。
さて、フィレンツェでバートラムはダイアナという堅い女の子(ソニン)に恋してしまう。巡礼に身を変えフィレンツェに来たヘレナはこのことを耳にし、ダイアナ母娘に計略を持ち出す。そして、ここでまた『尺には尺を』でも出てきた「ベッド・トリック」である。この2作、そんなに共通した意図で書かれたというわけではなさそうだけど、仕掛けの「ベッド・トリック」がいっしょなのである。
つまり、男を欺き違う女がベットに入ってしまうという計略なのだが、そんなものは絶対わかるはずだ!!と思うけれど、当時好まれた作劇上の技法で、どうも効果としての変装の一形態ではないかと考えられる。
結局それが功を奏し、ダイアナの代わりにベッドに入ったヘレナはバートラムの子を妊娠し、バートラムは、ダイアナの「愛しているならその指輪をちょうだい」という言葉にまんまと引っかかり、それが後でバラされ、ヘレナもバートラムの難題をめでたく解決し、表向きは大団円となる。
『尺には尺を』は『コシ・ファン・トゥッテ』に似たところがあると書いたけれど、ここでも変装が重要な仕掛けであり、さらには「指輪」もトリックとして使われるのだから、こちらは『フィガロの結婚』を思わせるところもある。もしかして、ダ・ポンテはシェイクスピアをかなり読んでいたのではないかと思い、とりあえずネットで調べてみたけれど、該当する箇所は見つからなかった。
貧しい医者の娘が貴族と結婚するというわけで、この話はおとぎ話(メルヘン)の結構を取っているとも言える。「終わりよければすべてよし」の意味も結婚してめでたしというおとぎ話的なそれとして見ることもできそうである。
しかし、モーツァルトの世界の大団円は啓蒙主義的な君主の「赦し」が大きい要素だし、おとぎ話の女性たちは、奇跡や偶然の一致といった魔法の到来の合目的性によって支えられているのに対し、こちらのヒロインは夢のなくなった世界で自分だけを頼りに、考え行動する女性になっている。
バートラムも身勝手で刹那的で、一旦は惚れて指輪まで渡してしまったダイアナを最後に罵ったりしているし、為政者を継ぐには豊かな感情や精神を持った人物とはとても言い切れなさそうだ。
そうなると、そんなバートラムはヘレナの恋愛の対象として相応しいのかどうかという疑問も湧くし、ヘレナ自身の行動も思いつめた自己完結せねば気の済まない衝動に一貫して支えられているようにも見え、決して感動や同情を誘うものでrはないとも言えるだろう。
この物語は公爵夫人の夫(=バートラムの父)、ヘレナの父の医者が死に、フランス王も病に瀕しているという旧時代の終焉から始まっているように、古き良き時代が終わり、身も蓋もない乾いた心を抱えざるをえなくなった若者たちが描かれているのではないか。
冒頭から、ヘレナとぺーローレスは臆面もなく「処女性」についてえんえんと対話を繰り広げるし、前沢さんが「この劇で問題なのは愛よりもセックスなのだ、3度も繰り返されるヘレナの独白は彼女がまるでハムレットを思わせる自意識の持ち主だからだ」と言っているように、ここでは、新時代の環境の中で旧時代の価値が試されているとも言えそうである。
ラフュー、ラヴァッチ、ぺーローレスの脇役の3人のセリフが劇を重層的に、最初の2人は批評的にこの物語を支えていて、彼ら3人のセリフにこの作品読解の鍵が隠されているかもしれない。
となると、この話は、「昔はよかった。今の若者ときたら・・・」といういつの時代にもありそうな、現代的な物語にも見えてくる。
前沢さんによれば、清教徒革命で捕らえられたチャールズ1世は幽閉中にシェイクスピアを読んでいて、お気に入りの登場人物の名前を余白に書き込んだものが残っているそうで、本作では敬称を付けて「ムッシュー・ぺーローレス」との記載があるのだそうだ。国王たるものが、この情けなく噓つきの人物を好んでいたというのは、なんだか面白い。
*****
今回2作品を見て、がぜんシェイクスピアが興味深くなってきて、さしあたり、河合祥一郎さんの『シェイクスピアの正体』を読み始めた。田舎町ストラッドフォード-アポン-エイヴォンで結婚し子もなしていたシャクスペアShaksperが姿をくらまし、突然、流行劇作家Shakespereとしてロンドンに出現するという不可解な経緯の謎。深い教養や歴史や政治社会についての膨大な知識はそんなに簡単に身に付くはずもない・・・というわけで、別人執筆説、複数作家説など様々な憶測を生んできて、そのことだけを探究する学会もあるそうだ。どうやら、17作品は劇作家クリストフォー・マーロウとの共作であるようだ。
*****
役者たちは、『尺には尺を』と交替で、例えば、中島朋子とソニンは片方がセリフの多い重めの役、岡本健一は今回は重要な老け役でフランス王ですが、最後にカツラを取っていわゆる締めの口上役となる。
なお、タイトルの『終わりよければすべてよし』はことわざになっているが、この作品が起源であるという説と、すでにあった言い回しをシェイクスピアが使ったという説があるようですが、前者であってほしいものである(笑)
日本では、蜷川幸雄が生きていたときほどシェイクスピアも上演されなくなり、話題になることも減ったように思うけれど、やはり史上最大の劇作家の一人、劇ならず、音楽にも映画にも無数に取り上げられてきた作家、今後の上演にもなるべく足を運ぼうと思った。
東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。