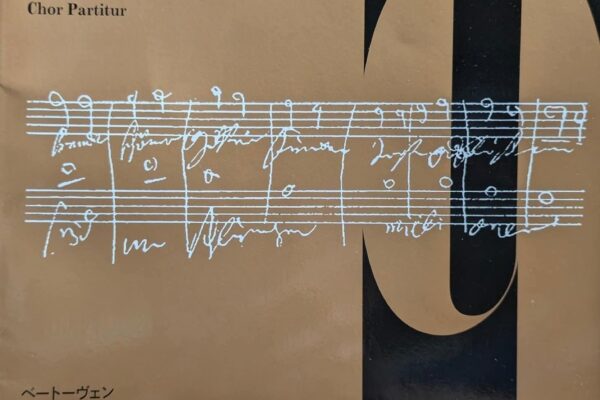『タンホイザー』『トゥーランドット』2つのオペラ公演(2023.2)でのヒロイン像の解釈について。さらに、読み替え演出のことも考えてみた。。
本論は同月に行われた2つのオペラ公演の鑑賞記であるが、とりわけそこでヒロインをどのように解釈しているかという点で、過去の歴史的限定の中で作られたオペラを現在において演出する場合の問題点やとりわけ「女性」の扱い方について触れたものである。その際、他の公演やディスクなどについても触れ、比較検討し、さらには、昨今の読み替え演出についても考察し、すぐれた読み替え演出を積極的に擁護する立場を明確にしたい。
◆ワーグナー『タンホイザー』(2023年2月8日、新国立劇場、ハンス・ペーター・レーマン演出)

ワーグナーは、いわゆるロマンティック・オペラRomantische Oper3つの第一作『さまよえるオランダ人』での、呪われたアウトサイダーが女性の自己犠牲によって救われるかというテーマに、「エロスと宗教」の要素を持ち込んで、さらに『タンホイザー』で展開させる。
実はこのテーマはモーツァルトが(もちろん表立った意図としてではないが結果として)『ドン・ジョヴァンニ』から『魔笛』への移行の中で扱っていた。しかし、ロラン・バルトが「オペラの複数の声(声の家族)がリートにおいて<ユニセックス化>」したと言うように、初期ロマン派で「エロス」の問題は一旦遠ざけられたと考えられる。バルトはさらに、「カストラートが消滅したこととリートの隆盛とは関係があり」、そしてリートにおいて「声が中性的に内面化した」のだと言っている(リートは声の性別を問わない)。
さらに「宗教」の問題も、ロマン派の「自然」の発見により、やはり一旦棚上げにされたのだというのが私の見解である。
それゆえに、ここへきてワーグナーが「エロスと宗教」のテーマを取り上げたのには十分な歴史的必然があるということになる。
キリスト教が近代市民社会になって家父長的な抑圧として働き「結婚」も制度に組み込まれることに対し、原点回帰的な宗教的純潔を置き、一方、初期ロマン派で袋小路に追い込まれた恋愛(結婚)の不可能性から抜け出るために自由で異教的なエロスの世界を置き、「恋愛」による近代の超克の可能性を試行錯誤した時期の作品が『タンホイザー』であるという構図が見てとれるだろう。
しかし、女性の自己犠牲による救済という理念は、今から見れば、やはりこれもまた男性中心目線のご都合主義になってしまうのは否めないし、初期ロマン派を抜け出るつもりが、また新たなかたちでの恋愛(結婚)の不可能性に直面したと言えるのではないだろうか。
なんだかんだで、異界からの訪問者という、お伽話、伝説的要素を入れた次の『ローエングリン』にしても、一旦結婚するものの破綻するし、ワーグナーのオペラで、結婚という結末でめでたしとなるのは、芸術と社会が融合した理想の可能態を中世に重ねようとした『ニュルンベルクのマイスタージンガー』ぐらいのものだろう。
ドイツ文学の研究者ですぐれた『マーラー』(平凡社)の著書もある村井翔氏は、HMVのリセウ歌劇場(2008)のディスク(ロバート・カーセン演出)のレビューでこう言っている。

…『タンホイザー』はオペラハウスの通常レパートリーとなっているワーグナーのオペラのなかでは一番「死にかけている」作品だと思う。だって、「清純な愛」対「肉欲」という二項対立は、ワーグナーおなじみのテーマだが男の身勝手な妄想でしかないし、ヒロインの犠牲死による主人公の救済、どちらも現代の聴衆としては真剣に付き合いかねるようなお題目ばかりだ。(・・・)この演出のストーリーは裸体画を描く革新的な画家と保守的な画壇アカデミズムの対立に置き換えられている。マネ『草上の昼食』『オランピア』、ピカソ『アヴィニョンの娘たち』など美術史の世界ではおなじみの話だ。つまり、オペラの中心テーマだけを取り出して、残りの要素はすべて捨ててしまった演出だが、ここまでやらなきゃ、もう『タンホイザー』は救えないという演出家の覚悟のほどはリセウ版を再見して一層良くわかった…
もう、身も蓋もない話だけれど、『タンホイザー』が現代でも聞くに堪えうる作品であるのは、その素晴らしい音楽ゆえであって、今日から見ればどうしても際立ってしまう内容の古臭さはその音楽によってかろうじて救われているのかもしれない。
私が所有している、ゲルギエフがバイロイトに初登場したもう一枚のバイロイトのディスク(2019 トビアス・クラッツァー演出)では、歌合戦がまさに同時進行的にバイロイトで行われているという設定になっていて、カタリーナ・ワーグナー自身が本人役で出てきたりして、このマジメくさった劇にまさかの笑いを持ち込むという芸当をやっているが、さすがに最後にヴォルフラムとエリーザベトが性行為に及んでしまうと、いくらフロイト的な読みの可能性が潜んでいるとしても、いささかやり過ぎの感があり、もうこのオペラの主題もどこかに吹っ飛んでしまいそうだ。
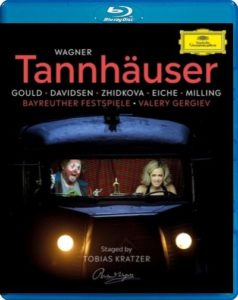
2014年バイロイトのクリスチャン・バウムガルテン演出版では、ヴェーヌスが妊娠していたりするし、いまだ見られずにいるペーター・コンヴィチュニー版では、振られたヴェーヌスがウィスキー瓶片手にベロベロに酔って出てくるらしい(笑)いやはや、今の読み替え演出はいろんなことをやってくる。しかし、それらが単に奇を衒った恣意的なものであると決めつけけることは、先にあげたオペラの音楽的素晴らしさに依存して総合芸術であるオペラの劇としての内容を歴史の旧態に閉じ込めておくことになる。読み替え演出の意義は、文学作品が、新しい解釈によって、隠れていた深層に光を当てるのと同じであると私は思う。
例えば、2006年モーツァルトの生誕250年にザルツブルクで上演された『フィガロの結婚』のクラウス・グートの演出は読み替え演出の最も輝かしい成果を見せた例である。アンシャンレジームから近代へのこの歴史の転換期は啓蒙思想の影響により、人間の「理性」と「エロス」が同時的に開放された時代である。Cherubinoの分身であるCherubim(智天使)はこのオペラでは、同じく翼を持つ天使のCupidでもあり、知を持ちながら恋愛を司る存在である。この羽のある天使を登場させ(となれば、この天使は同じく羽のある存在Papagenoをすでに示唆していることになる)、登場人物には不可視であり、魔法をかけ全体の進行を操作させる存在にする。ケルビーノの第1アリアでケルビーノとスザンナが並んで黒い目隠しを外す行為がそのまま「啓蒙」Aufklärungというこの時代の思想潮流のキーワードの意味になっているのも鮮やかである。aufklärenという動詞の原義には、(疑い、謎などを)解明するという基本的な意味の他にも、明るくする、性に関して啓蒙する…などの意味もあることを指摘しておきたい。
従ってケルビーノ/天使はこのSpiel(遊戯/ゲーム)を操作しているにもかかわらず、その一日のSpielが終結し大団円となり、いくつものカップルが成立するという政治力学(つまりそれは近代への方向づけが決定することを暗示している)においてはマージナルな存在へと追いやられる。そしてそれは同時に芸術の辿る運命をもなぞっている。
バロックにおいては権力の中心にいる王の隣にカストラートという天の声をもつ存在が付いていて神から授かった王権を補完していた。ケルビーノは、まさにその王を失った過渡期の空間で「自分で自分がわからない」Non so più cosa son, cosa faccio未決定の状態のまま彷徨うことになり、ズボン役であるという意味でもカストラートを引き継ぐ存在であるが、新しい時代ではもはや居場所を持てず、物語の筋の上でも、伯爵によって排除されようとしている存在である。
グートの演出では、最後にSpielを操作する天使の魔法は早くもすでに効力を失い、カップルたちは引き離そうとしても強く結びついて離れない。ケルビーノは疎外され行き場を失ってしまい、用済みとなった分身である天使が窓から飛び降りると同時にケルビーノも床に倒れる。それはボーマルシェの続編『罪ある母』でのケルビーノの戦死を、そして続くロマン派リートにおける恋愛の不可能性や雪の荒野を彷徨うしかない『冬の旅』のさすらい人の姿をも暗示している。グートがそこまで意図したかはわからないが、イメージがそこまで繋がってくるところが、すぐれた演出の及ぼす効果なのである。
こうした、モーツァルトの時代のみならず、先行する時代から後に続く時代までを大局の歴史と芸術における有りようまで含めて、潜在的テーマとして見通したこの演出の非凡さと慧眼は決してこれまでの演出では得られなかったものであり、読み替え演出の成功した第一にあげられるべきケースであると思う。
もちろん、演出に合わせて、音楽の指示するものを無視したり歪めたり、作曲家の意図をまったくぶち壊しかねない恣意的な演出も多々ある。しかし、文学作品同様、作家の意図とは一義的なものではないし、読み手がその一義的な意図を理解するわけではない。作品を世に出したときから、作者の手を離れ、作品は一種の余白を含むことになり、読み手(鑑賞者、批評者etc.)がその余白を埋めていくことになるのは、芸術作品の批評や解釈においてはいまや広く認められた前提である。その埋め方の力量が鑑賞者、批評者の腕にかかっているのは、音楽であれば、コンサートやリサイタルの場合と変わらない。それゆえ、ここでは「すぐれた演出であれば」作品をさらに多義的に開いていくという限定を付けているのである。

さて、話を『タンホイザー』に戻す。この作品にはエリーザベトとヴェーヌスを同じ歌手が演じる演出もあるが、確かにより現代的視点に立ち、タンホイザーを一種の分裂的妄想に囚われている人間と考えるなら、その一人二役はタンホイザーの心の反映として非常に有効なものとなるに違いない。

これらの演出に比べると、今回の新国立の今回の公演の演出(ハンス・ペーター・レーマン)はきわめてオーソドックスだったが、演奏にもひとこと触れておく。序曲からオケが鳴っておらず(指揮:アレホ・ペレス)、どうもなかなか熱を帯びてこないのがもどかしかったが、後半ようやく持ち直した感じであった。
歌手ではタイトルロールのステファン・グールドが意外と単調で、むしろエリーザベトのサビーナ・ツヴィラクとヴェーヌスのエグレ・シドラウスカイテの女性陣が見事であった。
日本勢では領主ヘルマン役の妻屋秀和はいつもながらの安定感、ヴァルターの鈴木准は声の量感がやや不足であったが、ビーテロルフの青山貴が健闘していた。それから、牧童の前川依子が、きらりと光っていた。
そして、やはりこの曲はやはり合唱の素晴らしさが聴きどころで、終幕はなんだかんだ言って、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』同様、心がもっていかれてしまうのであった。ワーグナーの音楽の罪深く魔的な魅力をもつが、ときに危険なところでもある。
2024年は東京リングが抜群の面白さだったキース・ウォーナーの演出で二期会が公演するが、どのような演出になるのだろうか。
◆プッチーニ『トゥーランドット』(2023年2月23日、東京文化会館、ダニエル・クレーマー演出)

アルファーノ補筆版のこのオペラを従来の演出、例えばMETのもので見たとき、リュウとティムールの死の後で、高らかに歌われる姫とカラフの愛は、音楽的カタルシスは得られたとしても、内容的にはもはや違和感なくまともに受け入れられる人は少ないのではないだろうか。たとえ、ワーグナーにもイタリア・オペラにも共通する無垢なる女性による自己犠牲という19世紀オペラのテーマの流れがあるのだとしても。ましてや、ますます多様性や同権が叫ばれるようになってきた現代では、なおさらのことである。
エヴァ・マルトン、ドミンゴという豪華歌手を揃えたMETの公演(レヴァイン指揮、ゼフィレッリ演出)は一時期はこの曲のスタンダードであったし、メータの紫禁城公演も記念碑的なものだったけれど、グランド・オペラの豪華さをそのまま再現したような公演は今後は出しにくくなっていくのではないだろうか。
2019年の新国立劇場の公演(と言っても私は生では見ておらずTVで見たのであるが)は、「愛の勝利」を逆手にとって、現代にふさわしく、見事にその違和感をなくす方向で解答を出した衝撃の演出(アレックス・オリエ)だったと思える。

上に円形のスポットで姫を、下にカラフを配置する構図は今回クレーマーも参照したのではないか。テオリンの白い衣装は純正なもの、そして同時に、死も連想させる。
最初に、姫(イレーネ・テオリン)がトラウマを抱えた存在だという前提を作ってある。つまり先祖の王女が異国の男に暴力的に殺されたことにより、姫が男性忌避=氷のような冷淡さをもつことになったという経緯である。カラフにも姫の美貌より権力に執着するネガティブな性格づけをしてあり、それによりカラフの姫への執拗な接近も、愛ゆえと言うより権力に執着しているように見えるし、姫からするとそのトラウマとなっている過去が反復されていることになる。これにより、最後の自死での姫の方の「愛」の完結は、カラフに向かうのではなく、むしろ自死を選ぶことでリュウの行為を引き継ぎ、もっと普遍的な人間愛の方向に向かうことになる。つまり、カラフを拒絶し、リュウの死を深く悼むことで、姫の愛に整合性を持たせたのである。
こうした演出は恣意的な改変となりかねないところもあるが、幸い『トゥーランドット』が未完で、プッチーニの描いた作品像に空白があったことが、この演出を可能にしたと言えるのではないか。
さて、今回の公演のダニエル・クレーマーの演出はそこまで大きく物語の筋を変更をしているわけではない。しかし、そのビジュアルから中国的な要素が極力除かれ、オリエ版同様、血なまぐさい恐怖政治が支配するきわめて現代的でダークな国家のような姿にすることにより(この点で、少しこの前の新国立劇場の『ボリス・ゴドゥノフ』と似ていた)、SF的な『トゥーランドット』になっていたと思う。
この超越的な存在、権力と民衆のヒエラルキーを縦の構図で明確に視覚化する点は、オリエの演出も行っており、クレーマーも多分にそれを引き継いでいると想像する。カラフも王子というより、民衆とこの地を共有するような泥臭いキャラクターになっていて、姫も最初舞台の上方に現れるが、その高みから地へと降りてきて苦悩する存在となり、再びカラフと高みへと上っていくことで、カラフの愛を受け入れただけでなく変貌して「共に愛を」実践するステージに再び上がったということなるだろうか。
ただそこをあまり派手にさせないために、べリオ版が採用されたのだろう。初めてみたけれど、全員で愛の勝利を讃えあげたりしないところはこの演出にべリオ版は相応しかったと思える。
リュウとティムールも監禁されたような電話ボックスのような吊り下げられた箱で自死を遂げるところの赤(血の色)の効果も強烈だが、再び上へと消えていく。姫とともにこの上↔下のシンボリックな動きは今回の演出の見どころのひとつだった。
否定的なものを極端に強烈に提示することで(従ってピン・ポン・パンのトラジコメディ的要素も弱められていた)、理想のイメージを暗示的に見せるというやり方であり、チーム・ラボのデジタル映像はそのために使用されたのだろうし、全体に未来のディストピア的社会の雰囲気があるので、このピラミッドのような枠内で湧きあがり、流動し、消え去り、色合いを千変万化させるデジタル映像は悪くなかったのではと感じた。


べリオ補筆部分だけでなく、こういう演出で見ていると、プッチーニも「茉莉花」のライトモチーフ的な引用の一方で、音楽的にはずいぶん不協和音を多用し、新しい試みをしていて、ヴェルディよりモダニストのプッチーニの側面を見た気がした。
このカルロ・ゴッツィの原作(1762)をシラーがドイツ語に訳したものにウェーバーが曲をつけ劇にしており、その中に出てくる「中国の歌」というのが、ヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」のテーマであるというのは、これまで知らなかった。面白いメロディだとは思っていたけれど…
グスターヴォ・ドゥダメルを生んだ「イル・システマ」出身のディエゴ・マテウスの指揮もドラマティックに響かせていたし、歌手陣は女性二人の声が圧巻だった。特に田崎尚子は大きめのビブラートに乗せた太い声が前の方の席だったこともあるのか、直接的に音圧を感じるほどの迫力だった。
東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。