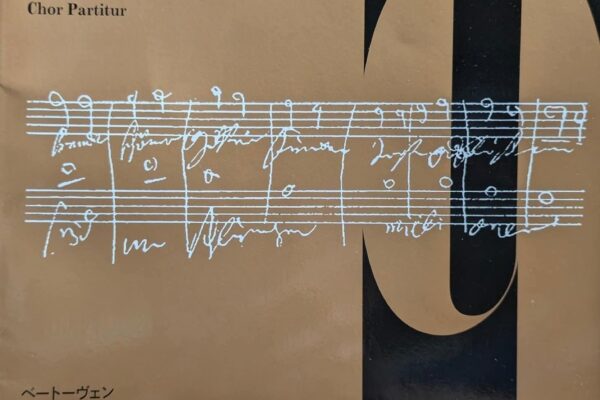二代目市川猿翁追悼と澤瀉屋の新星市川團子の『吉野山』のこと
【追悼・市川猿翁】2023.9.13



四代目猿之助の起こした突然の驚きの事件の先行きもまだ見えないうちに、二代目市川猿翁が亡くなった。
(僕にとってはいまだ猿翁より猿之助がしっくりくるので、以下、三代目猿之助と呼ぶことにします。)
成熟した後年期を迎え人間国宝になるような人生は天才的革命児のこの人には最初から与えられていなかっただろう。
早々と矢尽き刀折れてしまったようにも見えるけど、それでも普通の役者の何倍もの仕事をしたと思う。
演出家、脚本家の視点をもって、もう一度歌舞伎の歴史とその全体を解体再構成し現代に上演されるべき歌舞伎とは何かを問い、様々なかたちで実践してみせた力量には驚くばかりである。
そのために必要な若手役者たちを世襲の色の濃い歌舞伎界にとらわれず起用し、自らの一座として育てたのも大きい。
このことをほぼ一人でやったのだから、濃く短いキャリアになってしまったのもやむを得なかったのかもしれない。
若いときは「キノシ(本名の喜熨斗)サーカス」などと言われ、宙乗りやスーパー歌舞伎のイメージも強いせいか、新奇なことを手掛けた人という印象を持たれていたかもしれない。宙乗りや早変わりなどの外連(ケレン)は江戸の頃から行われていた様式だし、江戸歌舞伎のもっていた庶民のエネルギーや熱気、混沌や猥雑さ、芝居に託す夢やカタルシスといった当時の劇場で起きていたことを、台本の読み込みと演出の力によって、想像力をもって蘇らせようとしたという意味では三代目は決して異端ではなく、大衆芸能としての集団のエートスの向かう先にあるヴィジョンを見せると言う意味ではむしろ本道を究める先祖返りの仕事をしたと言えるのではないだろうか。とりわけ鶴屋南北物の通し狂言にはそれが言えると思う。
文楽の綱太夫との共演があったのも三代目が正統の意味をしっかり把握していたからだろうし、葵太夫との信頼関係は長く厚かった。四代目に引き継がれた踊りの巧さもピカ一であったし、若い頃坂田藤十郎(扇雀)と武智鉄二の元で歌舞伎を見直した経験も大きかったであろう。
海外公演も積極的に行い、世界の聴衆、ベジャール始め著名な演劇人、芸術家からも尊敬を集めた。「影のない女」や「金鶏」のオペラ演出を依頼されたのも、そういう蓄積があったからのことだろう。
スーパー歌舞伎は物語の忠義・封建道徳の足枷からも、「歌・舞」が後退した新歌舞伎のリアリズムからも逃れ、現代に訴えかける力をもつ歌舞伎の創造を考え、梅原猛とタッグを組むところから始めたが、僕は、古典歌舞伎が猿之助の演出によって錆を落とされて新しい相貌に見える方により惹かれていたので、正直、スーパー歌舞伎にはそれほど共感をしていなかった。
しかし、梅原と組まなかった、中国雑技団と共演した三作目の「リューオー」はほとんど文化の違うもののコラボの予想外の化学反応が生んだ爆発的狂気を感じさせる一作であり、そして四代目の第一作の「空ヲ刻ムモノ」は三代目の精神を引き継ぎ、まさに現代に訴えかける密度の濃い物語として、何かと取り上げられる「ヤマトタケル」や「ワンピース」(見てないのだけど )を上回る傑作としてあげたいと思う。どちらもこの先見ることは叶わないだろうが。
「三代目猿之助四十八撰」のうち、どの演目が今後誰によって演じられていくのかは今はあまり考えたくないけれど、いずれは中車・團子の線につないでいくしかないのであろう。
来月、立川で、澤瀉屋が中心となった「義経千本桜・忠信編」が演られる。狐忠信の三役を中村富十郎の遺児中村鷹之資、市川團子、そして三代目の部屋子から名題になった市川青虎の若手が勤め、澤瀉屋の総勢が脇を固める公演だが、こういう試みを大いにやって未来に向け形を作っていってほしいところである。
そして、まずは京都芸大に猿翁が寄贈した資料等の「猿翁アーカイブ」から、残された映像の少しでも多くのDVD化を望むところである。
病状がどうだったのかわからないけれど、その後の澤瀉屋に起こった痛ましい出来事を把握していたのだろうか?もしも認知症にもなっていて、告げてもわからない状況だったら、かえってそれでよかったのかもしれない。
忘れ難い演目はたくさんある。内容と(新しい)形式の独創的融合が素晴らしい「義経千本桜」「伊達の十役」「加賀見山再岩藤」「金弊猿島郡」「當世流小栗判官」「御贔屓繋馬」・・・初代猿翁から四代目にまで受け継がれ代表的家の芸となった「黒塚」・・・エンタメとしての楽しさが炸裂する「獨道中五十三駅」や「菊宴月白浪」。南北を復活させ、新しい構成で見せた「四天王江戸化粧」もそこまでの三代目の集大成と言える意欲的な試みで、国立劇場での昼夜通しの公演であった。猿之助、段四郎各5役に、田之助、門之助、歌六、彌十郎、亀治郎とその配役の分厚さにも改めて驚く。
他の役者でもよく掛けられる「敵討天下茶屋聚」でも、三代目のは演出の力が効いていて、エピローグに「矢の根」を持ってきたりする遊び心も冴えていて抜群の面白さであった。
国立劇場での三島由紀夫の「椿説弓張月」。この公演では、理想の現世を超える次元を夢見るがゆえに、現実の天皇制からも反れていく為朝の姿を壮大なスペクタクルの形で描いていた。原作のテキストを共感をもって深く読み込んでいることが感じられ圧倒的な感銘を受けたが、こんな凄い公演がただの一度しか見られなかったことも残念でならない。三代目がスローガンとした「天翔ける心」「夢見る力」を体現したのはまさにこの演目であり、「ヤマトタケル」以上に、こちらに三代目の思いはさらに強く表現されていたと僕は思う。
團十郎や幸四郎ら後続の若手たちにも慕われ、彼らにも憧れの対象となり、通し狂言「伊達の十役」は、実際にこの2人によっても演じられたが、やはり形をなぞってしまうことだけになるのは致し方ないし、その精神まで継いでいたのはやはり四代目現猿之助ということになるだろうが、これもまた、悲しいかな、言うても詮無き残念なこととなってしまった。
まだチケットも安く、客の入りもそこそこだったけど、歌舞伎座がいつも興奮状態で掛け声が一段と多く飛び交うものすごい熱気で、当日でも空いていた3階席一列目で眼の前に近づいてくる宙乗りを身震いするように見ていた頃が懐かしい。宙乗りは僕には「見得の持続」と感じられ、間合いの難しい声掛けを僕でも何度もしたものである。
それは、確実になにか新しいことが眼前で起きているのに立ち会えた感覚であり、もしかすると、若者たちが変革の夢を見、挫折した時代を演劇が引き継いだという面もあったのかもしれない。
蜷川幸雄の芝居は間違いなくその影響下にあるし、村松友視はその愛とも言える思いを著書にした。
昼夜通しで「義経千本桜」を一日でしかも碇知盛、いがみの権太、狐忠信の主要三役を全部三代目が一人で演るという、思えば信じ難い公演だったけれど、こちらも若かったのもあるが、あっという間に一日が経ってしまう感があった。
40年前から追い続けてきた人である。心から哀悼の意を捧げたい。
ずっと兄を支えた名優市川段四郎にも改めて。「御贔屓勧進帳」は二代目松緑よりもはるかに柄が大きく、「勧進帳」の弁慶は團十郎でも吉右衛門でもなく、十五代目羽左衛門とともに、いまだに段四郎のものが僕にとっては一番この目に焼きついている。
【衝撃のスター誕生に立ち会う瞬間/市川團子の「吉野山」】2023.10.25




立川の新しい大劇場ステージガーデンでの現在の澤瀉屋が総力をあげた「義経千本桜忠信編」の公演を見てきた。メインゲストに中村壱太郎。開幕前に壱太郎と團子による解説があり、壱太郎が、猿翁が最後に「千本桜」の全役を演じたときの静御前が祖父の坂田藤十郎で、「今日は團子くんと孫同士の共演になります」と言っていた。
中車がやたらと張り切っていて、最初に舞台挨拶をして、最後にもまた閉じた幕を開けて全員でお礼の挨拶をしていた。
立川ということもあり、歌舞伎初心者も多かったようで、上記の壱太郎と團子による「義経千本桜」の解説もあったのだが、この芝居を見たことあるかという質問への挙手は1/3ぐらいだったし、帰り道でも、初めて歌舞伎を見たのであろう人の「寝ちゃったよ」という声や「すごく面白かった」という声が聞こえてきた。
******
遺伝においては、何代かは明らかに見て取れる似たような部分が認められるように思える。ところが、あるとき滑らかに繋がらず段差ができるようなまったく違う新しさが現れることがある。突然変異とまでは言わないまでも、今回の團子には心底驚かされた。
まず、体型が違うことがこれほどまでに違った印象をもたらすものかということを感じざるを得なかった。歌舞伎は上背がなく、ずんぐりした体型の方が合うと言われるし、摺り足が板に付いて這っていくところが踊りの基本でもあろうけれど、團子の場合、なにしろ19歳にして180㎝で八頭身(いや、十頭身とも言われている)。ガゼルか何かの動物がふわっと風を切って進むような趣きがあるのだ。それでいて、不安定に軽いわけでもない。
たとえば、踊りの家に生まれいまは名手と言われる現松緑が出てきた頃は中心の軸から背中がぶれるような不安定な感じがありどうも落ち着かなかったし、女形で上背がある場合、とりわけ、体をたたんで小さく見せる苦労がいることは玉三郎の話でも知られるところである。
しかし團子の場合は、特に何かの工夫をしているわけでもなし、新しいことをしているわけでもない。そのままであってかつ新しいのである。
元々女形だった現猿之助が亀治郎の時代、少しずつ立役にも挑戦し始めた頃は、明らかに伯父の模倣から入っているのがよくわかった。中村屋の場合は先々代から三代に渡っての影響を見ることができる。役者の伝統芸は、そうして学ばれ。伝承されていくのだと思う。
しかし、今回の團子はそういった影響関係がないように見えるのである。もちろん、本人が公言しているように、祖父に憧れ、その映像もたっぷり見て体に覚え込ませてきたことだろう。
澤瀉屋の清新の気風やストレートな口跡は共通のものがある。にも関わらず、ここには過去に向いているもの以上に、未知のものの可能性の方を強く感じるのである。
狐の性を現わしてからの花道の引っ込みは、その跳躍の高さや歩幅に驚き圧倒され、何かにつけ受難に見舞われ悲劇のにおいが付きまとう澤瀉屋の暗雲を切り裂く新世代のスター誕生にじーんと来てしまった。
狐忠信を3人で演じわける今回の「忠信編」、團子は真ん中の「吉野山」、最初の「鳥居前」が中村富十郎の遺子鷹之資、最後の「四の切」が澤瀉屋の部屋子から名題になった青虎(前名弘太郎)が勤めた。
鷹之資は声が多少ざらつくが、この荒事風の忠信にはぴったりで合っていたと思う。名優を父に持つ割に、係累が少ないのかいまだにいい役がもらえずにいるようなところがあるが、立役として期待したい一人である。
青虎は丸顔でこれまでの忠信とは雰囲気が違い、凛と締まった感じより五月人形のようなおおどかさだけれど、体の方も小太りぎみで、ケレンの多い澤瀉屋の型に合わせるには、もう少し絞って体のキレをよくすべきところ。狐言葉になってからの嘆き、義経から鼓をもらった喜びの爆発・・・このあたりの感情の表出、描き分けのメリハリがもう少しほしいし、子狐であることの幼気さももう少し必要である。今回は歌舞伎座より大きな会場。天井も高く、宙乗りは劇場の機構もあるのだろうけど、斜めのラインの長距離。ワイヤーがある方がいいのか、この宙乗りは見事な体の動きで見ごたえがあった。
とはいえ、早く歌舞伎座で團子の「四の切」を見てみたいものである。
ステージガーデン。2500席もあり奥に長く、巨大なスタジオのような作りで、芝居より音楽ライブ向きの会場である。シートも堅く小さく、ひじ掛けもなく、そっけなくて座り心地が悪い。トイレも便器の数が少なめだし、手洗いのシンクも金属製の安っぽいものだし、新しいホールだけど、都心の落ち着いたホールの作りに比べ、立川風に効率優先で作った安っぽさが感じられた。
でも充実した公演内容だったので、そんなことはどうでもよくなり、広いプロムナードを心地よく風に吹かれながら駅まで歩いて帰った。
東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。