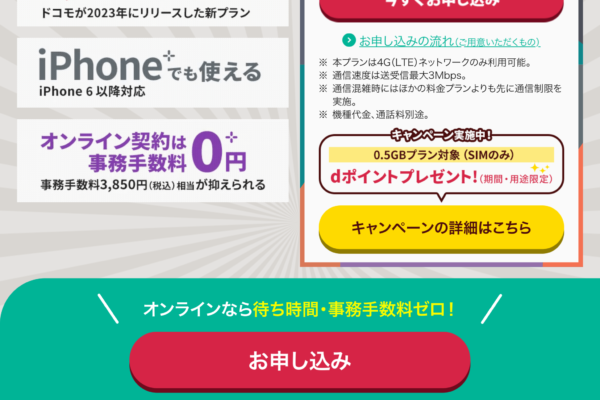テキサスの孤独の星
プロローグ
「誰でも何らかの形でアメリカとつながっている」
石川好のノンフィクション「ストロベリー・ロード」に記された一文を鮮明に思い出したのは、三度目にアメリカに上陸したときだった。今回は旅行でもなく、学会でもなく、長期留学である。
これまでずっと本能のままに動いてきた。父親のいる日本に来たのも、理系の大学を卒業したのち科学未来館に勤めたのも、そして博物館学を専門的に勉強したくなってアメリカの大学に留学したのも。後先を考えずに動く理由はたったひとつ、「楽しそうだから」。
留学先はアメリカ南部テキサス州にあるラボックという小さな町だった。ニューメキシコ州との境に近く、一番近い大都市ダラスへも車で5時間を要する。別名The Lone Star(孤独の星)と呼ばれるテキサス州の典型的な場所である。これは私が「孤独の星」で過ごした2年間の記録である。
テキサスの孤独
機上では14時間一睡もせずに、東京からダラス空港に飛んだ。長い期間をかけて、莫大なエネルギーをつぎ込んで、ようやく実現したアメリカ留学。脳内にドーパミンが大量に分泌されていることは、長時間の移動中も途切れずに快感を味わっていたことからもわかる現象だ。興奮、期待、そして希望。飛行機のローカル線に乗り継ぐために、ダラス空港で待機した。
「本当にアメリカの大学に入れるんだ」、「本当にずっと英語がしゃべれるんだ」、「本当にアメリカに住めるんだ」。英語のテストで苦しみ、タイミングにも恵まれず、幾度となくアメリカの大学にアプローチしたが、全敗した。苦い経験のあと、ようやく実現した今回の留学だ。自分の人生なのに、まるで他人の人生を生きているかのような錯覚さえ生まれた。「本当に自分の手で夢をつかんだんだ」。
ダラス空港から1時間ほどで、大学のある町、ラボック(Lubbock)に到着した。タクシーで学生向けのシェアハウスに向かった。空港から出た最初の印象は、「まぶしい」、そして土色。テキサス州の西北部は乾燥地帯であるため、年間を通して降雨日数が少ない。空気が乾燥していて日照時間が長いため、外の日差しが常に強烈である。現地では土色が最も太陽光の反射を抑制し、人の目を保護でき、かつ断熱効果のある色だと信じられている。
このため大部分の建物は外壁が土色となっている。植物はほとんどなく、だだっ広い土色の大地の上に、土色の建物が点在するという風景だ。世界の端っこに捨てられたかのようだった。北京にある私の実家はいつも人でごった返していたし、にぎやかな大都市東京で13年間過ごした私にとって、目の前の風景はまるで映画のセットの中にいる感覚で、しばらくは「現実だ」と受け止めることができなかった。
今回は遊びではない、学びに来た。そう自分に言い聞かせてなんとか落ち着きを取り戻そうとした。授業開始前に、私が入学する博物館学科では、学生主催のパーティーが開催された。
アメリカ人学生との初めての出会い
博物館学科の大学院は規模が小さく、修士1年と2年合わせても学生数は30人超えない。時差ボケが取れない中、何とか周りの人と話そうと必死に英語を話し続けた。イメージ通りの陽気なアメリカ人たちと、スムーズに話をすることができた。少しずつ彼らのことがわかってきた。9割以上の学生は現地テキサス州の出身で、私ともう一人の黒人の女子以外、全員白人の学生だった。
博物館学は歴史学や考古学や人類文化学などの文系科目の流れにあり、私のような理系出身者はおらず、学生はもっぱら文系の出身だった。社会人経験を持つ人も多く、年齢は20代後半で、30歳を超えた私のような学生はいなかった。ほかに女性がいなければ、私はすべての点でマイノリティとなるところだった。マイノリティであることが嫌いなわけではなく、むしろユニークな自分が好きだったが、あまりに周りとかけ離れているかと思うと、わずかな不安とかすかな孤独感が湧いてきた。テキサスに到着して三日目のことだった。
私が入学したのはTexas Tech Universityで、決してランキング上位の大学ではない。しかし博物館学科オリエンテーションの日に初めて訪れた大学博物館の規模に驚いた。新入生はすべての収蔵庫に案内された。生き物の標本や剝製、恐竜の化石、ロマン派から現代までの絵画、そして大量の家具と衣装。コレクションの総数は50万点を超えるが、アメリカの大学博物館の中ではそれでも中小規模に属するとのことだ。「これが本来の博物館なんだ」と理解した瞬間だった。
私は東京工業大学を卒業したあと、お台場にある日本科学未来館に約三年間勤務した。職業は科学コミュニケーターだ。研究者の世界と社会をつなぐかけ橋としての役割を持ち、科学を「文化」にすることがミッションである。主な業務は展示の解説、イベントの企画と運営、執筆やネット配信を通じた発信、それに他の科学館や企業との連携だ。未来館は独自のコレクションを持たず、正確には「サイエンスミュージアム」というより、「サイエンスセンター」あるいは「サイエンスフェア」というジャンルに属する。コレクションを持っていないため、当然収蔵庫を見たことがなかったし、コレクションをベースとする活動を展開した経験もなかった。未来館の職務経験を自慢にしていた自分はいつの間にか消え去り、真新しい世界にどっぷりと浸からなければならないと感じた。
授業が始まった。アメリカ留学用の英語テストをクリアしたからといって、本格的に英語で大学の授業を受けるのは初めてだった。しかも新しい専門分野なので、断片的にフレーズを聞き取るだけではなく、全体的な文脈を理解する必要があった。仕方なく授業を録音して家で書き起こすという方法を取った。1時間の授業を書き起こすには、3時間以上かかる。
授業内容は、コレクションの管理、文化財に関する国際条例および国際法、展示テーマと合わせたコレクションに対する解釈方法、ミュージアムを場とする教育プログラムの設計など多岐にわたった。加えて実習が多く含まれており、大学博物館のコレクションを利用した文化財の保護、修復および分類などについても学んだ。博物館内ではコレクションのジャンルによって部門が分かれており、学生は自分の希望で部門を選び、アシスタントとして仕事をすることが義務付けられている。
アメリカに行く前の自分であれば、ゼロからのスタートを覚悟して、新しい分野に飛び込んだだろうが、自分が慣れ親しんだテーマが無難だとの気持ちもあり、未来館での経験が生かせる教育部分を選んだ。
新しい情報が短期間で詰め込まれたせいか、脳が働きすぎで一時停止し、簡単な英語すら聞き取れないという現象が頻発し始めた。まだ授業は始まったばかりだ。「ここで落第するわけにはいかない」というプライドと気力だけで、何とか最初の学期を乗り越えた。すべての授業で合格ラインギリギリだった。
大学での生活
気が付くとすでに冬休みに入っていた。次の学期に備えて、大量の本と論文を読んで予習する以外に、やることはなかった。何せ車がないととても不便な町だった。学生専用のバスはあるが、遠くまでいかない上に本数も少ない。乾燥した大地で強風にあおられながら、バスを延々と待って、やっとのことでスーパーに着き、食糧を調達した。そしてようやく気が付いた。「テキサスの食べ物、ぜんぜん口に合わない」。
私たちアジア人が好む汁物はほとんどない。麵類もパスタのみ。パンの種類が多いものの、米は硬くて噛めない。野菜なども水分が少ないので、調理時間が倍以上かかる。殺人的な甘さのお菓子しかないので、毎日自炊を余儀なくされた。料理好きの私だったが、慣れない食材で全食作らなければならないかと思うと、さすがに気が滅入ってきた。テスト期間で忙しいときに、ネットで大量の日本製カップラーメンを買って、とてつもなくおいしさを感じた。しかし割高なので、出費を抑えるために、毎日は食べられない。食生活が合わないだけで、この土地で疎外感を感じるかと思うと虚しくなった。
テキサス北部の冬は極寒である。風が強く、雪が降らない時でも日中10度以下にとどまっている。そんな中でシェアハウスの暖房が壊れた。何度修理を呼んでも来なかった。やっと来たかと思うと、むしろ前より悪くなった。小さい熱風ファンが支給されたが、パワーが弱かったため、シャワーを浴びる以外、常にダウンジャケットを着ていた。アメリカ全土がクリスマスモード一色だったが、私は厚着をしてふとんの中で身を震わせていた。「ここはどこ?」「私は、生きている?」。肉体こそ存在しているものの、存在が証明される根拠が何一つ見つからなかった。自分の存在価値を見失っていた。渡米して三ヶ月目だった。
年が明けて授業が始まった。博物館の職員から大きいヒーターを貸してもらい、一回風邪を引いただけでなんとか厳冬を乗り越えた。授業は自分で選べるようになったが、アメリカ人学生にすら最難関といわれる博物館法律学の授業が始まった。法律、条令、規則、しかもアメリカバージョンと国際共通バージョン。一つ一つが抽象的な概念ばかりで、ロースクール並みの英語力が要求された。分厚い本を背負って自転車に乗って、図書館漬けの生活が始まった。午前零時に無料で支給されるコーヒーや、電話で呼べる学内のシャトルバスはありがたかった。アメリカの大学には、こんないいシステムがあるのかと、気持ちが少し楽になった。アメリカはやっぱり資源が豊富な国なんだ、もっとここの資源を利用しようと思った。

再びギリギリセーフで春の学期を乗り越えたのち、うれしい誘いが舞い込んできた。ずっと仲良くしていたサラという女の子から、春休み中に、実家の牧場に遊びに来ないかと誘われた。もちろん行きたいと伝えて、日程を決めた。車で4時間、クラスメイト4人とともにサンアントニオ郊外にあるサラの実家に到着した。
見渡す限り全部彼女の家の敷地だった。山から平原まで牛やヤギが点在していて、境界が見えない。そんな大自然の中にサラの実家があった。外壁が白くて広い平屋だった。家の前に家族で作ったプールがあった。文学作品を読むと、アメリカ南部の風景は田園詩のようだとよく言われる。しかし私は分かっている。美しさを感じると同時に、単調さと虚しさが混在していることを。リラックスした一週間だった。動物と遊んだり、山に登ったり、星空を撮影したり、みんなでターキーを食べたり。ホームステイのような時間だった。依然テキサスは私の世界とかけ離れているが、現地の人の温かさに少し安心した。
授業と格闘しながら、徐々に友人が増えていった。他の人と共有する時間が長くなり、やっと慣れると、すでに一年半が過ぎていた。プログラム最後の半年は、博物館でのインターンシップが義務付けられている。大学とつながりのあるヒューストン郊外の「牧場博物館」で働くことになった。
博物館での単調な仕事
牧場博物館はアメリカでよくある形である。もともと牧場だったところが何らかの理由で運営ができなくなると、その中の施設を利用して現地の歴史を紹介する博物館に変身するのだ。私がインターンとして働くことになった博物館は、1970年代に牧場の後継者がいなくなったため、地元政府に土地の一部を寄付する代わりに、予算を支給されて博物館が建設された。
ヒューストンといったら、都会のイメージがあるだろう。しかし実際に都会といえる部分の面積が非常に狭く、車で少し走ると、もうテキサスの「孤独の星」にふさわしい大草原である。住まいは牧場の中で、もともと使用人が使っていた小さな家だった。ここで私は大学時代よりさらに不便な生活を強いられることになった。
大学のような学内バスすらなくなった。自分でUberを呼ぶか、知り合いに頼む以外にどこにも行けない。知り合いはまた最初から作らなければいけない。クラスメイトのような同年代の人が少なく、共通点がほとんどないアメリカ人のおじさま、おばさまたちだった。しかも住まいにネットがつながっていない。これは到着したあとに知ったことだった。時間をつぶす方法が大幅に減ってしまった。何より仕事の内容は思った以上に苦痛だった。
広報活動をまったくしていない無名の牧場博物館なので、来客は一日でせいぜい三、四組だった。それでもインタープリターとして、牧場にある複数の小屋の中の一つに一日中いなければならない。ほとんどの時間はスタッフ同士のおしゃべりや、スマホゲームでつぶれる。
半分は屋外にいるので、木から落ちてくる毛虫や10㎝以上の蚊と格闘しなければならない。さらに上司はまったく管理能力がなく、すべて思いつきで動き、人の意見を聞かない。閉鎖的なところだけで生きてきた典型的な人間だった。私から提案や企画には目もくれず、常に「そんなのできない」との一言で跳ね返される。
テキサスでの最初の冬休みと同じような気分になった。拘束されてしまい、まったく身動きのできない、自由を失った状態だと感じた。大学の先生と相談し、インターンを変えたいと告げたところ、「卒業を延長することになるし、もっと時間とお金がかかる」と言われてしまった。「数か月だから、ここは踏ん張ってくれ」と言葉を交わしたものの、気分が優れないと告げて分かれた。先生は心配してくれ、大学のカウンセラーとつないでくれた。ただ普通のアメリカ人心理カウンセラーでは、私のようなケースが理解できるわけもなく、何の改善にもつながらなかった。
これが正しいと信じて選んだ道なのか、自分の存在には何の価値があるのか。一層のこと独断でアメリカから離れようとも考えた。だが自分を応援してくれている友人、先生、家族を裏切ることになることもわかっている。こんな複雑な思いを抱え、悶々とする日々を過ごしていった。
NICEな瞬間と経験
そうこうしているうちに、3月の春休みに入った。はじめて朝から来客が現れる状況になった。いくつ違うロケーションでツアーを続けた。聞いてくれる人が増えただけだが、はじめてこの仕事にポジティブな感情を抱きはじめた。
ある日に、いきなり20人のツアーを案内することになった。うしろの人が来るのを待つ間に、一番近くにいた小学校低学年の男の子に声をかけた。
私:「キャップは恐竜だね!恐竜が好きなの?」
彼:微笑んで頷いた。
彼のお母さん:「もうすっごい恐竜好きだよ。」
私:「テキサスには恐竜の化石がたーくさんあるから、ちょうどいい場所にいるよ。おめでとう!」
そして、みんな揃ったので、ツアーを始めた。話す内容はそれほど熟練していなかったけど、それなりにインタラクションを図りながら、和やかな雰囲気でツアーを終えた。
みんないろんな場所に散っていく中、あの恐竜少年がその場を佇んで、お母さんに小声でなんか話しはじめた。そして、お母さんから「直接お姉さんに言ってみたら?」と聞こえた。私が二人に近づけて彼に「質問があるの?」 と聞いた。すると、少年がまた微笑んで、恥ずかしそうに小声で私にこう言った:
「You are nice.」
涙が瞬時に溢れ出した。充実感たっぷりと同時に、いろんなことを思い出した。アメリカに来るまでの道のり、アメリカ生活の苦労、インターン先での不慣れ、そして予測不可能な災難に見舞わされたときの苦い気持ち。この十年以上続いていたアメリカにかかわる苦しさが全部、このひと言を聞くための前ふりなのではないかとさえ思えた。ツアーのテーマは私が全く馴染みのないテキサスの地域史だし、第二外国語の英語を使って表現力が限られるし、特別なアレンジや笑いを誘うための仕掛けなどしてもいない。でも、伝えたい気持ちが伝わった。
この瞬間に、テキサスとつながったと感じた。やっと、報われたと思った。
もう一度自分の存在を考えた。存在価値より、存在意義を求めるべきだと思った。なにか生み出そうとすることばかり追求するのではなく、自分がここにいる本当の意義、ここにいることが許される理由は真剣に考えるべきだと気づいた。
ドラマのように一気に前向きになり、最終的にアメリカンドリームをつかむなんていう素敵なオチが私にはなかった。やはり生活環境や仕事のスタイルなどから感じるギャップが埋められそうもないと感じたので、結局のところ最後までネガティブな感情を抱えてインターンを終了した。テキサスという孤独の星から孤独の心を持って、慣れ親しんだ日本に戻ることにした。
中国・北京出身。高校卒業後、日本に留学。東京工業大学大学院卒業、専門は化学。日本科学未来館などで勤務。アメリカ・テキサス州の大学で博物館学の修士課程修了。趣味はイタリアオペラ鑑賞と日本のプロ野球観戦。