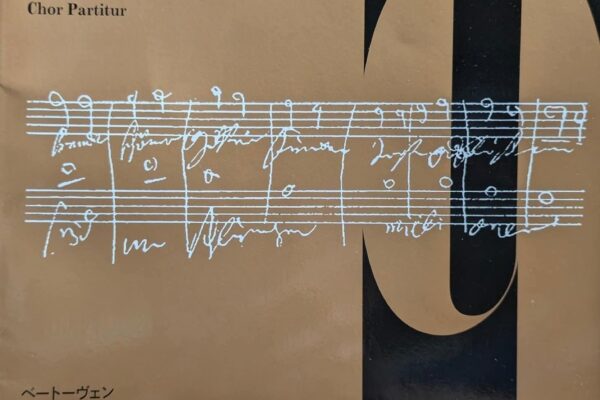阿佐ヶ谷住宅のこと(下)-過去においてありえた未来を現在に重ねる
(承前)

画像(1)阿佐ヶ谷住宅で最後の花見(2011年4月撮影)
阿佐ヶ谷住宅のテラスハウスの設計に携わった一人、大高正人は「コモン」と呼ばれる共通の緑地に「割合に個人的に感じられる所があるので、意外によい管理の状態になったりする。そのまわりの土地もそれに引きずられて、ある程度の水準になるという読みでしたけれどね」と言っているが、この「個々に丁寧に管理された専用庭と、みんなの共有地としてのコモンが、ゆるやかに共存している」(大月敏雄/志岐祐一)ような集合住宅がありえたということが、まさにこの本のタイトルの「奇跡の」団地ということの意味なのであろう。建物の規模が大きくなり、それ自体の独立性が高く周辺との関係性が弱まるとともに、「棟間園地」も切り離して考えられるようになる。管理するのもコミュニティによるのではなく、別費用を払って委託する事項となってしまう。大高は「僕らは緑に対しての考えが豊かになくちゃ。シューベルトの<リンデンバウム>というのがあるんですがね。あれは町の入り口のところに一本の菩提樹があって、そこに腰掛けて夢見たというのだけれど、そういうのが無いんだよね」と言っているのに対し、大月/志岐は阿佐ヶ谷住宅のループ路から見えるところに生えるヒマラヤ杉がまさにそれだとしている。

画像(2)「リンデンバウム」としてのヒマラヤ杉
「この腰掛けに座ると、本当にうとうとと、いい夢が見られそうである。こんな詩的な情景のある団地は、そうざらにあるものではない。」
これは、のどかな夢物語として、現在では一笑に附されるものであるのだろうか?しかし、2012年というついこの前までこれは現実に存在していた世界なのであり、もしかしたら、依然その夢物語を保持することもあり得たかもしれないのである。
こうした文を読むと、私はアドルノがモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』のツェルリーナについて語った一節を思い出す。
「ツェルリーナの姿のうちにはロココと革命のリズムが停滞している。彼女はもはや羊飼いの娘ではないが、まだ女性市民(シトワイエンヌ)でもない。両者の中間の歴史的瞬間に彼女は属しており、封建社会の圧政にそこなわれることもなく、市民社会の野蛮からも守られている人間性がほんのつかのま、彼女において輝き出るのである・・・彼女は静止状態にある歴史の比喩として永遠の生命を保っている。」(T.W.アドルノ『ツェルリーナへのオマージュ』より。川村二郎訳)
絶対王政が今にも崩壊しそうであり、自由と新しい時代への予感を抱きつつも、近代が動き始める前のひとときの静止状態。阿佐ヶ谷住宅の場合も、終戦と東京オリンピック以前の高度成長開始直前の時期の間に「奇跡的に」存在しえた一瞬の夢の跡なのだと言えるかもしれない。戦時中の「圧政」から開放され、建築においても時代の方向性もまだ一律ではなく、経済効率優先の「野蛮からも守られている」自由や遊びの入る余地があった短い間に「ほんのつかのま、輝き出た人間性」の感じられる建築群。それは具現化された夢の設計図として「静止状態にある歴史に刻まれた生命」を保っていたのではなかったろうか?
それがあり得たのは、津端修一(1925-2015)が全体の統括者前川國男(1905-1986)とアントニン・レイモンド(1888-1976)の弟子であり、前川はル・コルビュジエ(1887-1965)とレイモンドの弟子であり、そして、レイモンドはフランク・ロイド・ライト(1867-1959)の弟子で、一時期帝国ホテルの建築も手伝っていたという背景があるだろう。ル・コルビュジエやF.L.ライトのようなモダニズム建築の錚々たる面々からの流れがあり、そしてライトに学びつつ、日本の木造建築にも影響を受けたレイモンドのような建築家がいる。明治以降にまで話を広げると鹿鳴館、御茶ノ水のニコライ堂、三菱一号館などの建築に関わり日本の近代草創期の建築家辰野金吾を育てたジョサイヤ・コンドル(1852-1920)、そして関西で活躍し神戸女学院や関西学院大学などの設計者にして近江兄弟社の設立者のウィリアム・メレル・ヴォリーズ(1880-1964)といった日本の建築、文化に魅せられ日本に居を定めた建築家たちもおり、レイモンドも彼ら同様、日本木造建築の中にモダニズムの精神を見ていた(大月敏雄)。そしてル・コルビュジエやレイモンドらの西洋の建築家たちから学んだ若き日本の建築家、都市計画者たちに受け継がれた叡智とイマジネーションと創造性がこの集合住宅に入り込んでいるからこそ、阿佐ヶ谷住宅の「奇跡」が現出したのだという点は無視できないと思う。画像(8)-(12)のレーモンドや前川の住宅作品を見ると、そのモダンにしてシンプルな美しい木造建築のフォルムや屋根の勾配、インテリアの吹き抜け構造が阿佐ヶ谷住宅のそれへと受け継がれたことは想像に難くない。そう考えると阿佐ヶ谷住宅のもつ歴史的な価値も一層はっきりとしてくる。文化遺産的な思想もようやく日本でも普及してきた感もあるが、しかし阿佐ヶ谷住宅という「団地」をその対象として見るところまではいかなかったということなのだろうか。

画像(3)アントニン・レイモンド設計 東京女子大学本館

画像(4)同 東京女子大学礼拝堂

画像(5)礼拝堂内部

画像(6)前川國男設計 東京文化会館

画像(7)東京文化会館大ホール内部

画像(8)レイモンド設計 軽井沢夏の家

画像(9)レイモンド邸を模した旧井上房一郎邸(高崎哲学堂)。玄関は左側中央

画像(10)同旧井上邸裏側(平屋建だが天井を2階の高さまで上げているのは阿佐ヶ谷住宅のテラスハウスを思わせる)

(11)前川國男自邸(「江戸東京たてもの園」に移築)

(12)同前川邸側面
私はここまで、戦後の建築史、都市計画にける阿佐ヶ谷住宅という「団地」の目指した「理想」のもつ意義について語ってきた。しかし、並行する「現実」についても触れておく。実際の阿佐ヶ谷住宅は、当時としてはサラリーマンには高嶺の花の高額物件で、昭和40年代になりようやく分譲住宅を購買する習慣が根付き始めるため、個人が買うには時期尚早だったのか、購買者のほとんどは法人で(つまり社宅利用)あとは賃貸者という構成だった。後には一般購入者も住むようにはなったが、そのことが、「資力や所有目的が異なるために、管理を難しくする側面もあ」り(松本真澄)、権利形態も複雑で改築や取り壊しに至る経緯には難航することもあったようだ。老朽化して、最初は改修または立て直しの方向の案があったのが、いつのまにかその方向が変わり、6階案に反対運動も起きたけれど最終的には事業者・地権者が推進させ大手不動産が入って、4、6階中心の高層マンションを建築することとなった。法人が多かったことが難航させることとなった背景だとしても、一方で個人所有者の少ないことが改修・建て直し案の推進運動の団結力となりにくかったであろうことも想像される。購買層や建物の改築のことについてまでは設計者たちも予想できなかったことであろうか。住人たちのコミュニティの詳細については、松本真澄によるこの本の第三章に詳しいが、それについてはここでは触れない。
そしてまた、セキュリティと利益効率を考えれば、このテラスハウスの住宅棟と「コモン」とのバランスは、今日の日本の都市の現状には合わないではないかという反論は当然あるだろう。しかし、いまだに欧米でこのようなスタイルのテラスハウス群の並ぶ集団住宅が成立しえていることも考えると、我々が問うべきは、むしろそうした構想を即座に却下してしまう社会になってしまったという現状自体ではないのだろうか?
自分に籠もって社会から身を守りながらも常に「公」に怯える「私」。でいながら、「私」が脅かされるフラストレーションは時に匿名のクレームとして「公」に頼り責任を転嫁し、一方「公」は「公」でこうした「私」からの攻撃に神経を尖らしているような社会。こうしたマイナスの共依存関係は、「公」が快適さを最大公約数的に過不足ないパッケージとして提示する方向となり、経済もそれに合わせた効率性と確実性を軸に動いているのが現在である。
大月敏雄はこの本のあとがきでこう言っている。
「津端さんたちの昭和30年代前半の団地設計で、彼らの筆を引っ張っていたのは、「経済原理」ではなく「素直な都市計画」という原理だったに違いない。その事態とは打って変わって、今では設計者が持つ筆に、経済至上主義からの一本の強力な糸が結びついていて、知らず知らずの計画上の線がそっちの世界に引きずられてしまっているような気がする。
この「経済至上主義の世界からの一本の強力な糸」の出現を鋭く察知した津端さんは、やがて公団の団地設計から身を引くわけだが、この糸は今に至るまで、年々その強さを増しているようだ。
さて、ここで言いたかったのは、阿佐ヶ谷住宅を老朽化したままほっておけということではない。「経済至上主義の世界からの一本の強力な糸」が今や、公共の政策になっている現実を嘆いているのであり、そこにしか、居住空間の再編を頼るすべがない日本国民の危うさを嘆いているのである。
短期的にみて帳簿上多少赤字が出ても、長期的に見て正しく素直な都市計画をやろうとするのなら、行政がその赤字を補てんしましょうというような世の中にならないものか。実際いくつかの産業については、国レベルでも地方行政レベルでも、行政が堂々と税金でもって赤字を補てんしている現実を、われわれは多数目撃しているわけで、正しい街づくりをやって赤が出るのなら、その赤を補てんするような、そんな国づくりを目指すしかないのだろう。」
この本の著者たちが、前川、津端、大高らの阿佐ヶ谷住宅に関わった建築家、都市設計者たちの精神を現在まで引き継いでいることは喜ぶべきことであろうが、それ以上にこの大月の文章に書かれた「嘆き」の方が心に刺さってくる。なぜか?この引用文で大月が「阿佐ヶ谷住宅を老朽化したままほうっておけということではない」と書いているように、この本が出版された2010年の少し前ぐらいの時点では、阿佐ヶ谷住宅をどうするかに関してまだ最終的決定が下されておらず、著者たちもまだ阿佐ヶ谷住宅が保存され改修される可能性もないわけではないという期待と推測を持っていたのではないかと思われるからだ。だから、確実になくなるものの価値を知らしめんがために、「記録として残す」ためにこの本が編まれたわけではないのだろうと私は考える。結果的にはそうなってしまったのだけれど、当初の意図は、阿佐ヶ谷住宅の価値をもう一度振り返り、戦後の団地の建設においてそれが果たした意義を再建のために役立てようという意図もあったのではないだろうか?
残念ながら、阿佐ヶ谷住宅はもう跡形もなくなってしまった。私は日本の「現代温泉旅館事情」(上)(下)に続き、今回も前後編に分けて阿佐ヶ谷住宅について書いてきた。テーマは違うけれど、そこに通底する問題意識には一貫したものがあった。「現代温泉旅館事情」(下)の最後に書いたように、それは失われたもの、時流の荒波に抗えず消えていったものへの単なるノスタルジーではない。かつてあったが今は無い過去を、その時点ではありえた未来に変換し、さらにそれを現代に重ねること。追悼という行為のもつ意味はそれをおいてはあり得ない。
(了)
<阿佐ヶ谷住宅三景>



【注】
1)『奇跡の団地 阿佐ヶ谷住宅』の著者については、前編(上)の【注】を参照。
2)転載した画像についてはURLを表示する。
(3)東京女子大学本館は大学ホームページより。
(4)(5)http://arch-hiroshima.main.jp/main/a-map/tokyo/tojo_chapel.htm
http://www.suminoya.co.jp/blog/?p=242
(6)http://arc-no.com/arc/tokyo/tobunka1.htm
(7)http://ueno-bunka.jp/facilities/t-bunka/
(8)http://folli-2.at.webry.info/201110/article_4.html
(9)http://www.suminoya.co.jp/blog/?p=242
(10)http://amarantine2.blog46.fc2.com/blog-entry-157.html
(11)(12)https://www.ohkaksan.com/2015/11/14/%E5%89%8D%E5%B7%9D%E5%9B%BD%E7%94%B7%E8%87%AA%E9%82%B8%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8F/
<阿佐ヶ谷住宅三景>(順に)
https://blogs.yahoo.co.jp/tamazo_building/26649699.html
http://danchi100k.com/file0092/
http://danchi100k.com/file0092/pages/FH000036.html
東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。