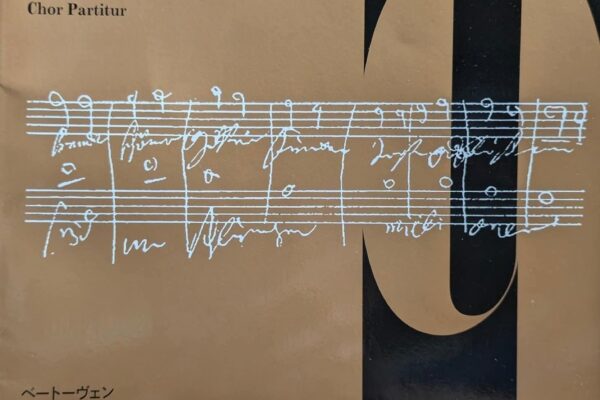トーマス・マンとチューリッヒ(下)
トーマス・マンとユング
マンがチューリヒ近郊で最初に居を構えたキュスナハトには、それ以前からユングが住んでいた。ボーデン湖畔の小さな町に生まれたユングはチューリヒ大学の病院で精神科医として働いていたが、1907年からフロイトとの交友を始める。ユダヤ人以外の稀有な精神分析学会会員としてフロイトから大いに将来を嘱望され、国際精神分析協会の指導的地位につく。しかし、性理論などについての考え方の違いから次第にフロイトとの溝を深め、1914年には決裂して協会を辞し、キュスナハトで個人医療を始めていた。

ミュンヘンに住んでいたころ、マンはユングの訪問を受けたことがある。その対面の様子はつまびらかでないが、ユングはマンが親しかったヘッセの精神分析を担当したこともあるので、マンはヘッセを通してユングのことは聞いていただろうし、ユングの著作には亡命以前から触れ、かなり熱心に読んでもいた。それどころか、マンがキュスナハト時代に書いていた長編『ヨゼフとその兄弟』には集合的無意識や元型といったユング心理学の基本概念の影響がはっきりと認められる。ところが、キュスナハトでいわば同じ町内に住むことになったマンとユングとの往来は皆無だった。(3)
それについての正確な理由は寡聞にして知ることを得ないが、当時のユングがナチに協力的な姿勢を見せていたことが影響していることはまちがいないだろう。ナチスはユダヤ人フロイトの創始した精神分析を憎んだが、1933年以降、ユングはナチスによる精神分析運動弾圧の指導的な地位についていた。後にユングはナチスを批判することになるが、当初は合理主義が行き過ぎた現代文明に対するアンチテーゼとしてそこに積極的な要素を見ていたのである。(4)

もともと、民族の集合無意識を語るユングの考え方は、ナチスにとっては都合のよいものだった。マンはフロイトとは個人的な交友もあり、親しくしたが、ユングとはついにその交友を深めることはなかった。しかし、ユングの考え方には大いに共感し、影響を受けており、1936年の講演「フロイトと未来」のなかでも、フロイトを前にしてそのいわば忘恩の弟子であるユングの『チベットの死者の書』を共感をこめて取り上げている。
マンのユングへの関心はユングと親交の深い神話学者カール・ケレーニイからのさまざまな刺激、特にユングに大きな影響を受けた著書『神的な子ども』(1941)や『神的な少女』(同)を贈られたことによって最高潮に達する。マンは、これらの書物から得た神話的キャラクターについての新たな理解を執筆中だった『ヨゼフとその兄弟』に生かしている。しかし、1936年のフロイト講演を除けば、公的にマンがユングについて語ることはほとんどなかった。1954年に日本の独文学者高橋義孝にあてた手紙では、フロイトからの多大な影響についてはこれを積極的に認めながら、ユングについて聞かれたことへの回答としては「ユングは一度も読んだことがありません」(5月17日付)という、唖然とするような言葉が記されているのみである。マンのユングへの姿勢はその神話理解への熱い関心と、そのナチスへの協力に対する嫌悪のあいだで分裂していたようである。戦後のスイスではナチスとの因縁もあってユングへの関心は総じて低く、遺族がキュスナハトに住みつづけることすら必ずしも容易ではなかったという。(5)
ユングに大きな影響を受け、その思想を作中に取り入れながら、マンがそれを認めたがらず、まったく否定することすらあったのは、自身の文学が最初からフロイトの思想との親近性をもっていることを公言し、積極的にそれについて語ったのと対照的である。少しでもナチスに関わるような事柄については、マンは非常に慎重であり、賢明だった。
そもそもマンにとってナチス、そしてその頭目であるヒトラーは生理的次元で耐えがたいものだった。ヒトラーの声、その話し方はマンに身体的な不調を引き起こすものだった。(6)それでいて、60歳近いマンはナチスの脅威のなかにあっても容易に住み慣れたドイツを離れようとしなかった。小説作者としては明敏そのものの観察者であるように見えるのに、実際の世事には鈍感そのもので危険を的確に認識できず、大嫌いなヒトラーが支配するようになったドイツをなかなか離れたがらない不精なマンを無理やりに出国させたのは、鋭敏な実際家である家族のメンバー、特に妻カーチャと長女エーリカだった。
ユングがその理論と作品をとおしてマンに与えた影響については少なからぬ研究があるが、両者ともチューリヒに住み、互いに目と鼻の先に住んでいながら、現実的にはわずかな関わりすらもとうとしなかった。これは、マンがその気難しさにもかかわらず、フロイトやヘッセなど同時代の代表的な知識人と比較的親密に接触していたことに照らし合わせてみても、ほとんど奇怪な印象すら与える。
ドイツではなくスイス
ナチスがオーストリアを併合し、その脅威がスイスをも呑み込みかねないと思われていた1938年、マンは欧州を去って安全なアメリカに移住することになるが、出発の前夜、チューリヒの聴衆に向かって『ワイマールのロッテ』の朗読を行なう。その前置きとして、マンはスイスで過ごした五年間を総括して次のように語った。
「私はあなた方の間で生活し、あなた方の山の大気を呼吸し、あなた方の文化生活を共にし、あなた方の高い均整の取れた文明に安全に包まれているのを感じ、成り行きのまま、別離、ないし別離らしきものがこの時局を支配している今日、この五年、感動的に優しく祝われた私の六十歳の誕生日もこの五年の間のことでしたが、この五年がいかに私をスイスの生活、スイスの風景、スイスの人情に結び付けてくれたか、に本当に気が付きました。いや、私はこの人情、その実直さと繊細さ、その温かみと取りつきにくさ、その陽気さと心的な難しさ、その誇りと不信を理解することを学んだと信じています。」(日記1937―1939、822頁)
マンの言説は社交辞令にすぎないものも少なくないが、ここに記されたスイスへの共感は本心からのものだろう。マンは本当にスイスに深い共感を抱き、不本意なままにそこを離れ、アメリカ在住中もスイスに戻ることをつよく願っていた。スイスのなかでも熱望されるのはドイツ語圏だった。骨の髄までドイツ語で思考し、表現するマンにとって、ドイツ語に取り囲まれて暮らすことができないことは身に染みて辛いことだった。
スイスへのマンの共感は、一面で自分と似ているものへの共感であるということができるだろう。スイス人の陰影にとんだ二面的な性格をマンは語っているが、マンこそは誰にもまして二つの魂を一身に抱える、高度に複雑な人間だった。スイス人気質の閉鎖性はよく言われることだが、マンの人となりもさばけたものとはいえず、一般にあまり親しみをもたれるものではなかった。
マンはきわめて神経過敏である一方、異常なまでの野心と虚栄心に駆り立てられる人間だった。人前での一挙一動はすみずみまで計算され、ていねいで紳士的ではあったが、いかにも矜持が高く、他者への警戒心がつよかった。生涯をとおして親友と呼べるような存在がいたかどうかは疑わしい。作家としても対象を突き放し、冷徹な視線で描くのが本領だった。しかしまた、自分のなかにある冷たさを反省する誠実さや温良さも持ち合わせていた。肝胆相照らすような友人に恵まれない反面、家庭を大切にし、特に妻カーチャやお気に入りの子どもや孫にはこまやかだった。自身の心にもっとも近い作品であるとマンが認めた(全集11巻75頁参照)『トニオ・クレーガー』は、アイロニカルな含みをもつものではあるが、ともかくも「人間的なもの、生命あるもの、平凡なものへの」(全集8巻275頁)愛情を語る小説である。
アメリカがマンにとって必ずしも馴染みやすい国でなかったことは容易に想像がつく。儀礼的で堅苦しく、複雑な陰影に満ちたマンの人間性は、ふつうにアメリカ的と言われる、率直で行動的な人間像とはおよそかけ離れている。世界的名士としていたるところで歓迎の嵐に巻きこまれながら、アメリカ人の押しつけがましい親切、無遠慮な意見表明には辟易していた。(7))ナチの脅威から守ってくれる庇護の地としてアメリカに感謝し、公的にはアメリカを賛美しながら、日記や手紙にはアメリカへの違和感とスイスを終焉の地とする希望を記しつづけた。(例えば日記、1941年7月4日付参照)
ナチスという激烈な病原菌に汚染され、到るところで暴虐の限りをつくしたドイツはマンにはもはや耐えがたいものだった。戦争中も欠かさずつけていた日記からは、ヨーロッパ戦線の成り行きを遠いアメリカからマンが一喜一憂しつつ見守っていた様子がうかがえる。戦争末期、ドイツの各都市が連合国の侵攻や爆撃によって破壊しつくされ、ドイツの敗北が決定的となっていくことをマンは心の底から喜んでいた。「アメリカではユダヤ人、ロシア人、わけてもイギリス人に対する憎悪があるが、唯一ドイツ人に対してだけはそうでない」(日記、1944年12月30日)と記し、アメリカがドイツを深く憎み、さっさと殲滅することを願っている。

マンにとって、ナチスによって汚され、罪悪にまみれたドイツは「まるで縁遠い国」(1951年6月3日付パウル・アマン宛書簡)になってしまっていた。祖国の破滅を物理的にともにすることなく、終始安全な場所から見ていたマンを歓迎しない人びとがドイツには少なからず存在していたが、マンもまたドイツを無心に愛することはできなかった。
それでももともと骨の髄からドイツ人であることを自認していたマンが、ともかくも祖国であるドイツに戻り、そこで最期を迎えることを心のどこかで願っていたということは十分にありうる。亡命先で高見の見物を決め込んでいたという世評はあったが、戦後、故国ドイツのあちこちで行なった講演や朗読会はどこも盛況で、特にリューベックで名誉市民として歓迎されたこと、必ずしも良好な関係とは言えなかったこの故郷との和解はマンの最晩年にやすらぎをもたらすものだった。しかし、マンは結局ドイツには戻らず、スイスを終焉の地として選んだ。罪悪にまみれ、荒廃したドイツではなく、賢明にも戦争に巻き込まれることなく、無傷のまま、国土と財産を保全したスイスを選んだことは、どこまでも潔癖症のマンに似つかわしいことだった。
幸運児トーマス

キルヒベルクで過ごした最晩年の一年間、マンはいつも心やすらかだったわけではなく、しばしば厭世的な気分に襲われた。死の年の2月、熱烈な支援者だったアメリカの女性アグネス・マイヤーに宛てた手紙のなかでマンは、「人生とはまったく奇妙なものです。私としては、人生をこれよりましな言葉で形容したくありませんし、もう一度やって見ようとも思いません」(1955年2月9日付)と記している。しかし、元来が憂鬱症のマンは、ごく内輪の人びとには生涯をとおしてこの種の愚痴を吐きつづけてきた。こうした愚痴を妻や信頼のおける女性にもらすことはマンの習い性と言ってもよかった。
二つの魂を一身に合わせ持つマンは、人生を呪いつつ、同時に、幸運が生涯をとおして自分を守ってくれていることを信じつづけてきた。1875年6月6日、日曜日昼の12時に生まれたと語るマンはいわゆる「日曜の子」だった。ドイツ語の「Sonntagskind(日曜の子)」は文字通り日曜日に生まれた子を意味するが、この呼称には幸運児という意味合いが込められている。1936年、60歳のときに書かれたマンの自伝的エッセーには、自分が誕生した際の星座の配置がおごそかな調子で書かれている。
「星位は吉兆を示していたが、これは占星術の大家たちが、のちにしばしば保証し、私の誕生日の星相にもとづいて、長寿と幸福な生涯、ならびに穏やかな死を約束してくれたとおりである。」(「1936年の履歴書」、全集別巻450頁)
これは中年以降のマンの目標となっていた世界文学史上の幸運児ゲーテの自伝『詩と真実』の冒頭の数行をもじった戯言のようなものだが、冗談にかこつけているもののここからはマンのナルシシスティックな自信が少なからずうかがえる。一般に、自分だけはどんなことがあっても最悪の不幸や悲惨な死を免れるという、根拠のない自信に守られて人間は苦難に耐え、楽天的に暮らし、ひとかどの仕事をすることが可能になるものである。不安感のかたまりのようなマンもその実、この種のうぬぼれをたっぷりと、ひょっとすると誰よりも多く持っていた。実際、60歳のマンは多大な文学的成功と世俗的幸福と言えるものを獲得しており、自身の人生は幸運に包まれていると語る理由をもっていた。長寿と穏やかな死は未だ実現されていなかったが、その後の20年は占星術的予言のほぼ完全な実現を示すものになる。
もともと精神的に不安定で麻薬中毒だった作家の長男クラウスは戦後、自死を遂げたが、残りの5人の子どもたちはおおむねそれぞれの道を歩んでいて、入れ替わり立ち代わりマンの家に滞在していた。76歳で『選ばれた人』、78歳で『欺かれた女』、79歳で『詐欺師フェーリクス・クルル』と次々に傑作を刊行したマンの驚異的な創造性はほとんど衰えることなく、80歳で長編評論『シラー詩論』を書いている。1955年6月6日、マンの80歳になる誕生日をチューリヒ市は盛大に祝い、全世界から祝辞と贈り物が届く。
これ以上は望めないその晩年の幸福のただなかに死は忍び寄ってきた。誕生日から、ほぼ一か月後、マンは左足に痛みを覚える。一時的にかなり悪化するが、その後の経過は順調だった。ところが、思いがけず、幕切れがやってきた。本人ももうすぐ退院と考えていた8月11日、突然、病状が悪化、翌12日、マンは家族に見守られてチューリヒ州立病院でその生涯を終えた。ほとんど苦しむことのない、安らかな臨終だった。
注
3.Dierks; Thomas Mann und die Tiefenpszchologie, In; Thomas Mann Handbuch, Frankfurt am Main, 2005, S.298
4.林道義 『ユング』 清水書院 1980 175頁以下
5.磯前純一 「チューリヒのC・G・ユング」 『みすず』2012年8月号 みすず書房 15頁
6.Heinrich Breloer; Unterwegs zur Familie Mann, Frankfurt am Main, 2001, S.64
7.クラウス・ハープレヒト 『トーマス・マン物語Ⅱ』(岡田浩平訳) 三元社 2006年 594頁
1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。