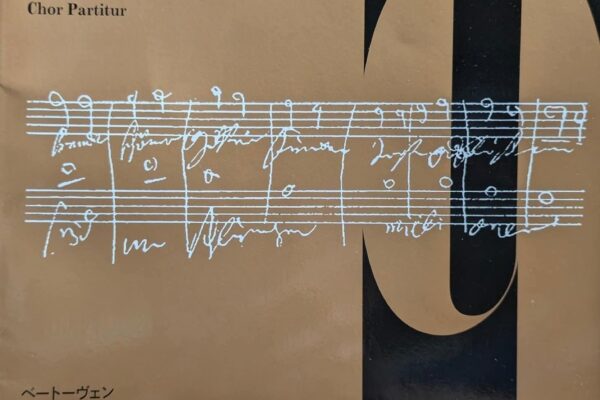バイロイトの旧市街と宮殿
バイロイトという地名
バイロイト市街地は、赤マイン川(Roter Main) — マイン川は上流で白マインと赤マインに別れる — とゼンデルバッハ川(Sendelbach)に挟まれた、馬蹄形の砂岩台地の上に乗っている。地図1で「旧市街の範囲」として示した場所である。
この小都会「バイロイト」Bayreuthの地名の由来は何なのだろうか。
まずBayreuthの綴りの後半、「ロイト」(-reuth)というのは、この地方に多く見られる地名の接尾語で、森を開墾して作った耕作地ということだ。現代ドイツ語で開墾するという動詞にrodenというのがあるが、-reuthはこれの古い形が変化したものだそうだ。

では前半のBay-とは何を意味するのか。これにはいくつかの説がある。ひとつはバイエルン人(Bayer)という意味にとる説で、開墾が盛んに行われた10世紀頃に神聖ローマ帝国内に勢威を振るった、バイエルンのアンデクス=メラーニア家が主導して開墾した土地ということから来た地名であるとするものだ。
もうひとつはバウアー(Bauer)の開墾地ととる説である。Bauerとは農民の意味だ。このほか、英語のbyと同じく「傍らの」を意味する副詞beiから来ているという説もある。これらの説はみな根拠となる資料に乏しく、なかなか決着を見ないようである。
そこでこれらを念頭に自分なりにこの地の昔の光景を思い浮かべてみると、日本の奈良時代から平安初期に当たる8世紀から9世紀ごろに、ようやくフランク王国の支配体制がこの地方にも及んできた。そのころはゲルマン人達が定住し、スラブ人と混在していた。バイロイトの周囲は緩やかな丘が点在し、その全体が深い森に覆われていたことだろう。その後日本の平安時代中期に当たる10世紀から12世紀頃、その森のあちらこちらに円形の禿のような開墾地が出現し、それらはみなReuthを呼ばれていたが、それぞれ次第にほかと区別して、何らかの由縁をもとに、「なになにロイト」と呼ばれるようになって行ったのだろう。
それらの内、今のバイロイト市街地に存在した開墾地が、先ほどの説に従えばバイエルンの貴族が主導して開発したのでBayer-Reuth、あるいは農民主導だったので、または農民が集団で住んでいたのでBauer-Reuthと呼ばれるようになり、そこからBayreuthと地名が出来る。そのころには台地の上のこの集落には市場が開設され、その両側に家が建ち並ぶようになり、村というよりは市というにふさわしい景観になっていった。
もっとも当時の古文書での表記は今日の標準的な綴りであるBayer、Bauerそのままではない。さまざまな表記例が今日のBayerやBauerに対応するかどうかが判断基準となるのだが、このあたりは専門家ではないので省かせていただく。このころこの地方はゲルマン人とスラブ人の混住地帯で、その後次第にゲルマン化が進んで行き、最終的にはスラブ人はボヘミア盆地中央部から東に押し出されたのだろう。これが今日のチェコ人というわけである。
バイロイト市街地の歴史的展開
バイロイトが「市」として記録される最初の例は日本の源平時代に当たる12世紀末だ。1192年の古文書にBaierreutと記されているのが文献の初出である。今でも市街地の中心であるマクシミリアン通り(地元の人は簡潔に「市場」Marktということが多い)の周りには一応都市らしい景観ができつつあり、上にも記したようにそこに領主から市場開設の権利が与えられ、小さいながらも「村」Dorfではなく「市」Stadtと呼ばれることになったのである。
この「市場」はこの馬蹄形の台地の北側の尖端近くにある。東側にはマイン川岸に落ちる崖に沿って一列の家並みがあり、西側にも同じように一列に建物が並び、その両サイドの家並みの間の通りの中央部がふくらんで形作られた広場が「市場」である。中世にはこの「市場」の真ん中に、広場を南北に二分するように市役所(Rathaus)の建物が建っていた.
その後この市役所は火災で消失し、西側の家並みの一家屋に移った。今日この第二次市役所の建物は「オスカー」Oskarという名のレストランになって、バイロイト大学の教授連や学生達に親しまれている。なお今の市役所は東側の崖から下りた、かつては赤マイン川の川原だった場所に建てられた高層ビルである。
12世紀にはまた、市教会(Stadtkirche)と呼ばれる教会堂が建てられた。これはその後何百年もバイロイト市民の宗教生活の中心をなしてきたものだ。この教会の位置は、従来の「市場」の南側に当たる空き地にあたり、ここに聖堂の建設が始まると、それに伴って市街地が南に拡大することになった。マクシミリアン通りを中心とする旧市街北部に対して、この地域は道路がみな教会に向かうようになっているのだが、これは聖堂建設の資材を運ぶために普請した道がそのまま街路になったためだと推測される。
ホーエンツォレルン家と旧宮殿
さて、こうして教会を中心として南側に展開した市街地の外れに、中世末期に城砦が築かれた。ここに城が築かれたのは、両側を川に挟まれた崖の上の台地という、防御しやすい地形だったからだろう。この城はニュルンベルク城伯として南ドイツで勢力を拡大しつつあったホーエンツォレルン家が支城として利用した。
ちなみにこのニュルンベルクからドイツ北東部のブランデンブルクに移った家系がブランデンブルク辺境伯として、後にプロイセン王、ドイツ皇帝となる。もうひとつの家系は、最初バイロイト北方20キロほどに位置するクルムバッハKulmbachを本拠地としたが、その後バイロイトを本城としてバイロイト辺境伯となる。移ってきたのは日本の徳川幕府開府と同じ1603年のことだ。
ヨーロッパの多くの街では、城壁の内側の旧市街はわれわれ日本人が抱くヨーロッパの町の観光的イメージそのものだ。日本のテレビ番組で紹介されるのはこうした旧市街ばかりであり、しかもいかにもヨーロッパ人といった外見の人ばかりが映っているが、実際に現地にいれば、目に入る風景の中に必ず黒人や頭に頭巾を被ったアラブ人女性がいることに気づく。カメラマンはこうした人たちがいなくなる瞬間を辛抱強く待っているのだろうか。あるいは後から映像処理で消しているのだろうか。
ところが城壁の外側はマンションや分譲宅地、スーパーマーケットが並ぶ、現代人の生活世界である。特にドイツは社会状況が日本と似ているので、こうした新市街地に住んでいる人々の生活はわれわれとそれほど違わないく。21世紀の先進国での人生は散文的に共通なのである。私がホームステイでお世話になった家庭のご主人は、上フランケン郡役所の公務員で、毎朝早く出勤し、夕方遅くに帰ってくる。ドイツのサラリーマンは早起きして一生懸命働くのだ、とは彼自身の弁である。私が滞在していた一ヶ月ほどの間に、ガス管取り替え工事に立会い、車の買い換えのためにフォルクスワーゲンの工場まで一泊して新車を引き取りに行ったりしていた。何でも自分で直に工場で引き取ると、販売店を通すよりずっと安くなるのだそうだ。
バイロイトにも「市場」を中心とした北半分と市教会を中心とした旧市街を取り囲む城壁が存在した。17世紀初頭のバイロイトの絵図を見ると、町を囲む城壁が描かれ、その端に旧宮殿が建っているのが見える。

地図2はGoogle Mapを加工した現代のバイロイトの姿である。バイロイト辺境伯の本来の宮殿である「旧宮殿」Altes Schloss(写真1)は、一見町の中心にあるように見えるが、歴史的な市街地の範囲では、市民の町の南東の隅であるのがおわかりだろう。それより南側に、広大な緑地(宮殿庭園Hofgarten)を囲むように広がる市街地は18世紀以後のもので、本来のバイロイトの市域の南限は、この旧宮殿の前から西に向かって走る、官房(Kanzlei)の建物の前を通る道のラインであった。

旧宮殿は今はバイエルン州財務局などのオフィスが入っていて、観光客が中に入ることはできないので、この素敵なルネッサンス様式の建物は外から眺めるしかないのだが、バイロイトの歴史的建造物の中で異彩を放っている。ベンガラ色に似た赤と白漆喰のコントラストの美しさはドイツの他の都市でもあまり見かけない。
この宮殿は17世紀初頭に辺境伯がバイロイトを宮殿所在地に定めて以来次第に拡張されて、中庭を囲む四つの建物と、さらにその北側に二つの翼を有するかなりの規模のものとなったのだが、1753年に大火災が起こりほとんど灰燼に帰した。今の建物はその後に再建されたものである。このとき従前の建物にどれだけ忠実に再建されたかは、手持ちの資料ではわからない。ただ、壁にずらりと並んでいる漆喰の人物像は、この再建時のものである。なお、火災の原因は辺境伯自身が就寝前に、図書室の蝋燭を消し忘れたためだそうである。
18世紀中頃、プロイセンのホーエンツォレルン家本家からヴィルヘルミーネ妃が嫁いできた当時は、宮廷財政の立て直しの時期に当たり、宮殿の修繕も行われておらず、彼女の手記によれば、ソファーの布が破れていて、中の布がのぞいていたり、壁紙も色あせていたとのことである。
新宮殿
官房の南側の、17世紀までは市外であった土地に18世紀になって建てられたのが新宮殿(Neues Schloss)(写真2)である。この当時バイロイトではこの宮殿の新造営のほかに既存の離宮の整備なども行われており、それらはバイロイト・ロココ(Bayreuther Rococo)と称賛される高いレベルの仕事だったのだが、その面影はこの新宮殿では外観ではなく内部の装飾にこそ伺うことができる。

18世紀のバイロイトでそんな建築事業が可能だったのは、プロイセン王家から嫁いできたヴィルヘルミーネ辺境伯妃の力に拠ったのである。これ以後辺境伯の宮廷機能はこの新宮殿に移り、再建された旧宮殿は一部が教会に改築され、その他は武器庫等に利用されていたらしい。
新宮殿ではファイヤンス焼き(Fayence)の作品が展示されている。ファイヤンス焼きは低温で焼成するので、分類上は陶器であるが、釉薬をかけて磁器のような外観を与えたもので、オランダのデルフト焼きが有名である。ドイツ国内でも各地で制作され、バイロイトには1716 年から1788年まで工房があった。
新宮殿でもっとも美しいのは、西側の翼のさらに先に建てられたイタリア棟(Italienischer Bau)と呼ばれる部分である。これはヴィルヘルミーネ死去後、後妻として嫁いできたゾフィー=カロリーネ=マリーエ辺境伯妃の居所だったところだ。新宮殿本体は全体に無表情な外見で、正面中央だけ宮殿にふさわしく荘厳さを施されてはいるが、それ以外は簡素で大学の校舎のような印象だが、イタリア棟だけは外壁の色が明るい黄色であり、室内空間にはいかにも女性的な繊細さが感じられる。イタリア棟の中央には浴室が残されている。18世紀中頃までの貴族女性はほとんど入浴しなかったらしいが、辺境伯妃だけは頻繁に入浴していたという。貴族が入浴しなかったのは、温水に浸かるのは身体にとって危険であるとの観念があったためといわれている。
人生においては香りはときとして記憶をよみがえらせるきっかけとなるが、歴史には香りは当然残ってはいない。現代人がいきなり18世紀にタイムスリップしたら、豪華な衣裳をまとった貴族たちの体臭にびっくりすることだろう。逆にわれわれの生活がいかに多くの清潔を保つものに支えられているかに気づかされることでもあろう。タイムスリップした現代人は、シャンプーがない、歯磨もないので、ノイローゼになるのではないか。もっともしばらくすると、こんなことにも馴れてきて、かえって体臭を嗅がないと物足りなくなったりし、さらには体臭にえもいわれぬ感応性さえ感じるようになるのではないか。そうして「人間臭さ」とはこんな感覚のことを言うのだと、納得するのではないだろうか。
1953年5月31日 長野県生まれ。
1960年より長野県小諸市にて少年時代を過ごす。
長野県立上田高等学校卒業
東京大学文学部、同大学院でドイツ文学を学ぶ。
1987年より筑波大学でドイツ語、ドイツ文学、ヨーロッパ文化等の講義を担当。
研究領域:ゲーテを中心とする18世紀末および19世紀初頭のドイツ文化
最近の研究テーマ:バレエの歴史と宮廷人ゲーテ、18世紀の身体美意識とゲーテ、ゲーテ時代のサロンの瞬間芸(タブロー・ヴィヴァン、アチチュード)