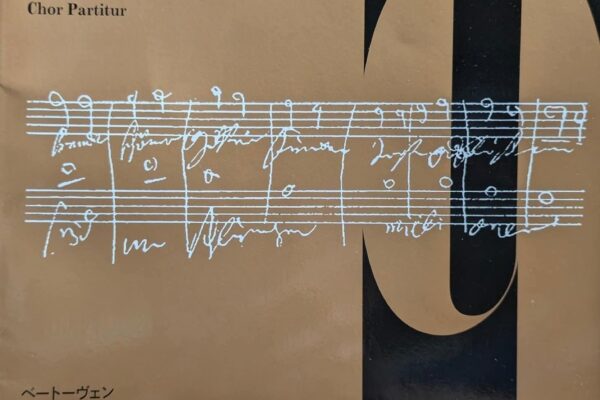トーマス・マンとチューリッヒ(中)
チューリヒと故郷リューベック
チューリヒゆかりの偉人といえば誰よりもまずツヴィングリの名を挙げなければならないだろう。ツヴィングリはスイス東部の小さな村に生まれ、ウィーンとバーゼルの大学で宗教学を学んだ。1518年、チューリヒの市参事会に招かれ、市の司教座聖堂の説教師となる。ルターと同様に信仰の基準を聖書だけと考えたツヴィングリはスイスで最初の宗教改革を始める。ツヴィングリはカトリック勢力との争いのなかで戦死するが、その遺志を継ぐチューリヒの改革派は1549年、ジュネーブのカルヴァンの呼びかけに応えて合同信条を作成し、ここにスイス改革派教会の基礎が築かれた。
合理主義や勤勉を特質とするプロテスタントの精神は、清潔で整然としたチューリヒの町の雰囲気を形成する大きな要素となっている。マンがことのほかこの町を愛し、ここを終焉の地とすることを願ったことには、その雰囲気が故郷のリューベックの北方的・プロテスタント的精神風土と類似していたことが関わっていただろう。ナチスを逃れてスイスやアメリカに亡命し、安全な国外で比較的恵まれた境遇にあったマンに対しては、ドイツ国内には反感をもつ人びとが多かったこともあって、マンは戦後もドイツに居を構える気がなかった。それでいてドイツ語を自身の生存の不可欠な根拠として生きる作家マンにとって、ドイツではないが生きたドイツ語に囲まれて生きることができるスイスのドイツ語圏は世界中のどこよりも好ましい場所だった。

『ブッデンブローク家の人びと』という北ドイツの町に生きる一族の盛衰を描いた小説を文学的出発点とするマンは、きわめてドイツ的な作家だった。兄で作家のハインリヒがその文学的出発のときから国際派であるのと対照的に、ドイツ文化に深く根をおろしていることを身上とする作家だった。第一次大戦のさなかに書いた長大な政治評論『非政治的人間の考察』は、西欧文明と民主主義を標榜して反戦的立場に立つ兄ハインリヒに対して、非政治的で内面的な伝統的ドイツ文化を擁護し、ドイツ帝国への支持を表明するものだった。
祖母がスイスの出自であるだけでなく、母親がブラジル出身という点からすれば、もともとトーマス・マンにも国際派の素地はあった。マンの母はドイツとポルトガルに起源をもつブラジル人で、幼少期をジャングルに囲まれた町で送ったのち、リューベックに移り住んでマンの父と結婚した。異国の血を引く少年としてリューベックの学校生活になじめなかった経験は、『ブッデンブローク家の人びと』のハノー少年やトニオ・クレーガーの苦しみとして作中に色濃く反映している。しかし、『トニオ・クレーガー』の結末が示すように、若いうちはむしろドイツの市民階級の出自であることをつよく自身の根拠として打ち出していた。
リューベックは現在は人口約21万の中都市だが、かつてはヨーロッパ北部の経済を支配したハンザ同盟の中心都市として隆盛を誇った。ハンザ都市は皇帝から自治権を買い取った独立性のたかい国際的商業都市である。市民みずから合議制を形成し、みずから町を守り、治める政体をもち、自由な気風を特色としている。チューリヒも早くから(1218年)帝国自由都市となり、その後も、スイスで大きな勢力だったハプスブルク家に屈することもなく、自治権を守ってきた歴史があり、1648年には帝国自由都市の地位を捨てて都市共和国になるなど、市民みずからによる統治を維持しつづけてきた。
バルト海河口に位置するリューベックは港湾都市であって、世界に向かって開かれた性格をもっている。間近に海があり、川や運河に囲まれ、その中心部にマンの生家はある。建物は、現在はハインリヒとトーマスというマン兄弟の文学記念館ブッデンブロークハウスとなっている。マンの家は一大豪商で、当主は代々、参事会員として市政の指導的な立場にある名士だった。チューリヒも湖に面した水の町であり、気候もいくぶん湿気を含んで程よい冷気を含んでいる点がリューベックと共通している。
若干26歳のマンを一気に世界的な作家に押し上げた『ブッデンブローク家の人びと』は、リューベックを舞台として、マンの生家をモデルとする架空の一族ブッデンブローク家の歴史を描いた長編小説である。この小説を読むと、そこに描かれた人びとの姿をとおして、自由と独立の精神をもったハンザ都市の市民の生活や気風が実感として把握できる。4代にわたる家族の当主のうち、もっとも大きな役回りを与えられているのは3代目のトーマス・ブッデンブロークだが、勤勉で生真面目で、明るい理性に導かれた生き方を志向する半面、厭世的で憂鬱にとりつかれやすいその人となりは、プロテスタンティズムを支柱とする倫理的な空気のなかで勤勉に生きる北ドイツの市民の典型といえるだろう。トーマス・ブッデンブロークは直接的にはマンの父をモデルとしているが、マンはこの人物を大きな共感をもって描き、そこにマン自身の志向する生き方を反映させている。
『トニオ・クレーガー』の主人公もまたマン自身を大きく反映しているが、この人物においても父は生き方の規範として選ばれることになる。芸術と市民性のあいだで迷うトニオは早くに死んだ父を顧みて、その「考え深く、徹底的で、清教主義を奉じているところから自然几帳面で、どちらかといえば憂鬱な性」を北方的で市民的な気質と総括し、それを母の「官能的で率直で、けれども同時になげやりで情熱的」な、南方的で芸術的な気質と対比させながら、市民的なものへの、すなわち父への帰順を表明するのである。マンの生涯は、芸術という反市民的な要素がつよい仕事を天職として選びながら、秩序、勤勉、節度という北方的・プロテスタント的な生き方を貫くものとなった。
『ブッデンブローク家の人びと』には親族をはじめ、郷里の人びとを辛辣な筆致で描く部分が多分にあったため、発表以来、マンと郷里の関係は必ずしもよいものではなかったが、1926年に行なわれたリューベック700年記念祭に招かれたマンは、そこで「精神的生活形式としてのリューベック」と題された講演を行なっている。このなかでマンは自身の小説が郷里の人びとを憤激させたことに触れつつ、しかし、芸術家となった自身の根幹には「精神的生活形式」としてのリューベックがあったと語っている。第二次大戦後、リューベック市は世界有数の作家となったマンを名誉市民として称えることになる。
国際都市の光と影
マンの故郷リューベックは海に向かって開かれた近代的な商業の町である一方、中世の面影を残す歴史の町でもある。そこに古色蒼然としたドイツが混在していることは、マンの晩年の作品『ファウストゥス博士』の舞台となる架空の中世都市カイザースアッシェルンのモデルの一つがリューベックであることが物語っている。カイザースアッシェルンはルターの宗教改革の本拠となったドイツ東部にあるプロテスタンティズムの栄える町として設定されている。しかし、それは中世の暗黒時代を思わせるような不合理な神秘主義がはびこる場所でもあり、魔女伝説、少年十字軍、舞踏病のような「中世のヒステリー」(全集6巻39頁)が20世紀になっても残滓として存在していたと『ファウストゥス博士』は語っている。近代性のなかに中世が混在する町としてマンはこの架空の町を描くが、その背景にはマンが幼少期を過ごしたリューベックという町の面影がある。

チューリヒはこの点でもマンの故郷に似ている。開かれた国際的な都市という側面をもつ一方で、古色蒼然とした旧市街が残っており、閉鎖的で保守的で息苦しい面もあるようである。ここには1948年にユング研究所が設立され、ユング心理学の本拠として世界中から分析医志望者を集めた。日本におけるユング心理学のパイオニアである河合隼雄や秋山さと子もここで学んでいる。秋山はスイスという国は清潔で美しい反面、宗教的で道徳的な堅苦しさがあり、通りすぎる観光客にはまったく理想的に見えるスイスの実際の姿はあまり健康的とはいえない複雑なものであると語っている。
「スイス人は一般に閉鎖的で、石造りの小さな家にとじこもり、隣の家の木の枝がこちらの庭にまでのびてきたというようなことで大騒ぎする。そのあまりにも閉ざされた家庭の中では、たとえば山間地では貧しさの故に近親相姦が起きたり、都市の有閑階級の間では、暇を持てあまして親子二代の二組の夫婦が相手をとりかえて性的遊びにふけったりもする。アルコール中毒患者も多く、うつ病の人たちがよく見られるのは、この自閉的な暗い雰囲気も影響しているのかもしれない。」(1)
スイスの精神医学はこうした事情もあってめざましい発達を遂げ、ヨーロッパにおける一つの中心となってきた。チューリヒはユング以外にも、ルートヴィヒ・ビンスワンガーやメダルト・ボスなどの現存在分析でも知られている。スイスをヨーロッパ有数の精神医学の牙城に押し上げた、スイスのあまりほめられない側面については、マンももちろん盲目だったわけではない。ドイツを脱出して間もない、豊かだったミュンヘンの生活への未練がいまだたっぷりとあったころの手紙では、スイス亡命を考える知人に対してそれを勧める気はないと述べ、「スイスはおそらく世界中で『いちばん自給的な』国、つまり自国および自国民にいちばん気を使っていて、外国人にたいしてはいちばん不親切な国」(1934年2月16日ルードルフ・カイザー宛)と評している。
実際、革命家や亡命者の避難場所となってきたスイスも、ナチスドイツの成立にともなって亡命を希望して押し寄せる無数のドイツ人に対しては、マンのような著名人は例外として、必ずしも好意的ではなかった。マンの次男ゴーロは、政治的理由でのドイツ人の移住に対して国境の検問が厳しくなっていたことをみずからの経験として語っている。(2)
マンの長女エーリカはドイツにいたときからみずからが台本を書き、司会や歌も行なう風刺的な寄席を運営し、チューリヒ移住後も公演をつづけていたが、最初のうちはドイツ以上の評判だった。しかし、その反ナチス的な風刺に憤激したスイス内の親ナチ勢力がはなはだしい妨害を行なうようになり、やがて市の上演許可を得られなくなった。スイスはオーストリアのようにナチスに併合される憂き目には至らなかったが、ナチス全盛期においてはその危険は少なからずあったし、破竹の勢いだったナチス・ドイツへの合流を期待して家に歓迎のためのナチスの旗を用意しておくスイス人も少なからずいたのである。
注
(1)秋山さと子 『チューリヒ夢日記』 筑摩書房 1985年 23頁
(2)ゴーロ・マン 『ドイツの青春2』(林部圭一他訳) みすず書房 1993年 235頁以下
1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。