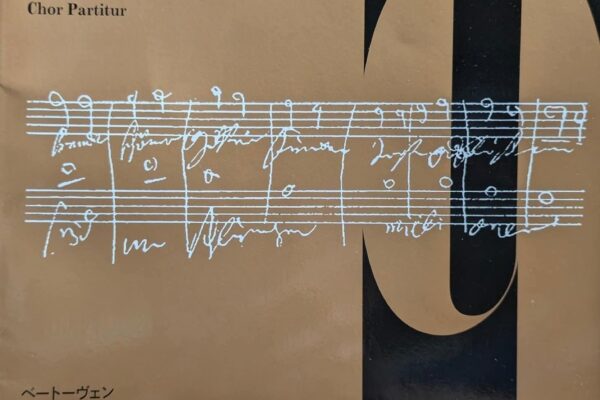ドイツの城下町バイロイト~ワーグナーの町というよりは~
これから何回かにわたって、ドイツの小都市バイロイトについて書こうと思う。
縁あって私はこの地を何回か訪ねた。とは言っても、私はワグネリアンではなく(彼の音楽は好きだが)、ワーグナー詣をしたのではない。以前勤めていた大学がバイロイト大学と協定を結んでいて、あちらの関係者には学生の留学や私個人の研究で、たいへんお世話になったのである。
バイロイトという町は、第一印象では正直言って「冴えない」ところである。建物は古くさく、バロック的な華麗さに乏しいし、かといってゴシック的な古色もない(実は独特のロココ宮廷文化の栄えた場所ではあるのだが)。要するに地味なドイツの典型的な小城下町なのである。その典型性に私は次第にのめり込んでいった。
ただ、バイロイトのビールは美味であることは言っておかねばなるまい。バイロイト市内で醸造しているマイゼル(Maisel)は、すっきりした喉ごしでありながら、こくがあって、なるほどビール純粋令を守って真面目につくるとこうなるのか、と思わせるビールである。上面発酵のヴァイツェンもうまいが、いちばん基本的なドイツビールであるヘレス(Helles)がいい。ヘレスはミュンヒェンのものが有名だが、私はバイロイトの方がずっとうまいと思う。
バイロイトはバイエルン州の上フランケン郡(Oberfranken)の郡庁所在地である。お隣の下フランケン郡(Unterfranken)は、フランケンワインで有名である。マイン川の川面の反射光が当たる斜面で葡萄栽培が可能なのである。上フランケンでは残念ながらワインはできない。マイン川の川幅が狭く、また気温が低すぎるのである。
下フランケンと上フランケンは見事に対照的である。下はカトリックで、中心都市ヴュルツブルクはバロック的な装飾に満ちた美しい町である。それに対し、上はプロテスタント(カルヴィン派)で、宮廷は繊細なロココ様式であるが、それを除くと生真面目な直線的な建物が多い。ワインとカトリックに対し、ビールとプロテスタントはそれぞれに相性がいいのかも知れない。
バイロイトにワーグナーがやって来たのは、1872年だった。彼が自分のオペラの上演に適した劇場を求めてドイツのあちこちを探ったあげく、バイロイトの古いオペラハウスに目を付け(このオペラハウスはバイロイトから宮廷がなくなったために、あまり使われずにいたので、再利用できないかと考えたらしい)、この年に実際に検分にやって来たのだが、旧式の劇場では使い勝手が悪いので、新しい劇場を建てることにした、という経緯は広く知られているが、なぜこの新しい劇場、いわゆる祝典劇場Festspielhausを最終的に同じバイロイトに建てようと決めたのかはよくわからない。ただ、次の事実からは彼の心中を垣間見られるかも知れない。彼はこの古くさいドイツの田舎の城下町に落ち着こうと思ったのである。居をかまえ、その館をHaus Wahnfriedと命名した。訳せば「狂躁沈静館」。わが半生の狂おしさここに静まれり、というわけである。
実際それまでの彼の生涯は、生まれ故郷のライプチヒから始まり、ヨーロッパの主要都市のほとんどに足跡を残し、行く先々で恋愛沙汰、議論、確執の連続で、しかもそのたび毎に借金を積み重ねた。日本にはワーグナーの専門家の方も多くいらっしゃるので、私がここでこれ以上彼の生涯について述べるのは控える。ともかく、こんな修羅道を歩んでいる男がついに心の平安を見いだしえたのが、このバイロイトという土地だったということに、私は妙に納得してしまうのである。
とは言え、それは人生の戦いに疲れたワーグナーがどこか静かな隠棲の地を探し求めてたどり着いた、というような、よくある偉人伝の結末のようなことではないだろう。彼はバイロイトでさっそく祝典劇場Festspielhausの建設という、およそ芸術家の精神生活とは対極にあるような世俗の事業に勢力を注ぎ込むことになるからである。事業欲を抱いてこの地に降り立った彼をして、同時にここを安住の地にしようと思わせたものは何か。それはこの地に降り立ったとき肌で感じる、安らぎの感覚ではなかったろうか。何かの魅力と言うよりは、その特徴のなさといってもいい。私がバイロイトという土地で感じるのも、この何もないことの安らぎである。町の簡素なたたずまい、背後の緩やかな丘の連なり、人々の表情の穏やかさ。およそミュンヒェンのせっかちなとげとげしさとは対照的である。
他国にいるとき、私達はしばしば今自分がしかじかの土地に確かにいるのだ、という実感がつかめなくなる。ミュンヒェンとか、ベルリンとか、その訪れた場所の地名は知っていても、かくかくしかじかの土地に今自分が立っていて、その土地の空気を吸っている、という感覚がどうも湧いてこない。名所旧跡を訪ねても、これが私にどんな関係があるのか、と、妙に冷めた気持ちになってしまうし、せっかくお金を掛けてきているのに、こんな程度の感興しか湧いてこないのでは損だ、などとけちくさい根性に、我ながらあきれてしまうのだ。
これは単に位置のオリエンテーションの困難と言うのではない。その場所にまとわりついているさまざまなコンテクストに疎遠だからだと思う。たとえば東京にいるとき、今いる場所が東京の中でどのようなキャラクターを割り振られているかを、私は知っている。渋谷なら若者に人気の繁華街、北千住は下町の庶民的な町といったふうに。そしてこの二つの正反対の性格の町が、丁度対角線上に位置していることも知っている。
今神保町にいるとしよう。今日はどちらの町で飲みたい気分かによって、乗る電車の路線を選ぶのである。渋谷なら半蔵門線の東急直通中央林間行き、北千住なら逆方向の東武南栗橋行き、といった具合に。それが私にとっての東京の生活であり、まさに東京に自分が居る、ということを保証してくれる根拠である。
これは私の頭の中に私独自の密度の濃い情報の蓄積があるからできることで、この情報が空間イメージにプロットされたものを社会学ではメンタルマップと呼ぶらしい。この蓄積された情報には、自分自身の行動によって獲得したものだけでなく、他人から得たものもある。つまり書物やメディアから得たものであり、それらの中にはさらに今すでに生きてはいない人たちの残した情報も多く含まれている。
こうした外来の情報は、言うまでもなく私だけが持っているのではなく、東京に住む多くの人々に共有されている。いわば時間と空間が立体的に組み合わされた4次元メンタルマップが人々の頭に入っているのである。この意味で、都市とは現実の土地であるというより、その共有された主観的世界のことであると言ってもいい。私達はその主観の中の時空間を生きているのである。
外国のなじみのない都市では、土地の人々に共有されているメンタルマップが私にはないのである。だからその土地に馴染む、ということは、このメンタルマップを獲得するということに他ならない。
バイロイトが私に示してくれたのは、ひとつの地味なドイツの都市の姿であった。軍国主義的な町だとか、貴族的な町だとかのレッテルを都市に貼ることは、却ってその土地を理解することを妨げるものなのである。なぜなら、たいていの人はそうしたレッテルを頼りに、土地の人にとっては何の意味のないことまで、過剰な解釈をしてしまうからである。
バイロイトという町は、ワーグナーの町、またワーグナーの提示した「ドイツ精神」の町、といったレッテルが貼られてきたが、私にはそんなレッテルは無意味であると思われる。バイロイトの市民生活そのものにワーグナー由来のそんな「色」が付いているはずがないのである。
ワーグナー的なうわべの性格ではなく、私にとってはここはむしろ歴史、それも語られてきた歴史Historie/historyが景色として空間化されている場所である。ここでは現在の空間的な姿から過去の時間的な経緯が推測しやすいのである。自分が持っているドイツの、もっと長く深い歴史の知識が、観光やイデオロギーに染められないで形で確認できる。言い換えれば、バイロイトという都市の空間について、歴史軸も有効な4次元メンタルマップが作りやすいのである。
こうして空間的・地理的にだけではなく、時間的・歴史的にも自分のいる「場所」が確認できるということは、心に大きな安らぎを与えてくれる。
また、バイロイトの位置するフランケン地方は、森の中に騎士の城が点在するといったドイツのイメージそのものの地であり、風景の中に、というより空気の中に、暗い衝動を隠して静まりかえっているドイツの地霊の気配とでも言うようなものを感じてしまう土地なのである。
今日のバイエルン州の北半分、ほぼドナウ川より北側はフランケンと呼ばれ、本来のバイエルンとは別の歴史を歩んできた地域である。ミュンヒェンのヴィッテルスバッハ家が一円支配してきた本来のバイエルンは、ドナウ川より南側の、アルプス山麓から緩やかに降りてくる、どこかとりとめもない広大な斜面を占めている。それに対してフランケンは小さな丘が連なり、その間に小河川の作る緑の谷が開ける複雑な地形で、それぞれの谷間が、丘陵に抱かれたまとまった小世界を作っている。そこにヴュルツブルク司教領やバンベルク大司教領、帝国自由都市ニュルンベルクなど、神聖ローマ帝国の格式高い諸侯が混在していて、バイロイトはバイロイト辺境伯という小さな君主の領邦としてそれらの間の一角を占めていた。
フランケンがバイエルン王国に併合されるのは、ナポレオン戦争においてバイエルンがナポレオンに協力したための報酬であったが、ヴィーン会議でも最終的にバイエルン帰属が承認され、以後200年近くバイエルンの一部として扱われてきた。
しかしフランケン人はバイエルンに必ずしも帰属意識を持っているわけではない。フランケン人が好むジョークに次のようなものがある。そのかみのローマ帝国駐屯軍は、ドナウ河畔に「ゲルマン人川を越ゆるべからず」という立札を立てた。その立札の文字が読めた教養のあるゲルマン人は川を渡らなかったが、文字が読めなかった野蛮な連中は川を渡ってしまった。前者の子孫がフランケン人であり、後者の子孫がバイエルン人である、というわけである。
バイロイトの君主の家系は、ホーエンツォレルン家という。といえば、あのプロイセン国王からドイツ皇帝になった、ヨーロッパ有数の強大王家を思い浮かべるだろう。カイゼル髭で有名なヴィルヘルム二世皇帝もホーエンツォレルンだし、宮殿をかまえるベルリンはこの200年間ドイツ第一の大都会として発展した。
一方バイロイトの方は田舎の小領邦で、日本で言えば徳川家の親戚筋である松平家が10万石程度の譜代大名になっているようなものだ。とは言え、ベルリンの本家とは養子や婚姻関係もあり、小なりといえどもそれなりに格式のある殿様ではある。特に18世紀中頃のヴィルヘルミーネ妃はベルリンの本家から嫁いできており、あのフリードリヒ大王の姉である。彼女のおかげでバイロイトロココと呼ばれる独特の宮廷文化が栄えたのである。彼女の造った優雅な宮殿については稿を改めて紹介したい。
バイロイトの殿様の称号を「辺境伯」Markgrafという。これは何もバイロイトという土地が辺境にあるからというわけではない。地図を見ればわかるが、バイロイトはドイツの国土のほぼ中心に位置している。辺境伯というのは、ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン人がようやく西欧の国家秩序を立て直してフランク王国ができたころ、中央政府から離れた新たな征服地を支配させるために遣わされた、全権委任の役職のことで、日本のたとえで言えば「大宰帥」のようなものである。こうした称号はその後有力貴族の間で使い回されて来て、実際の職務とは無関係になった。これも日本に引きつけて言えば、「出羽守」といってもその大名が山形や秋田を支配していたわけではないのと同じである。
今回はバイロイト紹介のいわば導入、大学の授業で言えば概論のようなことを書いたが、次回からはこの町のあちらこちらにある、想像力をかき立てる事物や歴史上の出来事について具体的に書きたいと思う。

1953年5月31日 長野県生まれ。
1960年より長野県小諸市にて少年時代を過ごす。
長野県立上田高等学校卒業
東京大学文学部、同大学院でドイツ文学を学ぶ。
1987年より筑波大学でドイツ語、ドイツ文学、ヨーロッパ文化等の講義を担当。
研究領域:ゲーテを中心とする18世紀末および19世紀初頭のドイツ文化
最近の研究テーマ:バレエの歴史と宮廷人ゲーテ、18世紀の身体美意識とゲーテ、ゲーテ時代のサロンの瞬間芸(タブロー・ヴィヴァン、アチチュード)