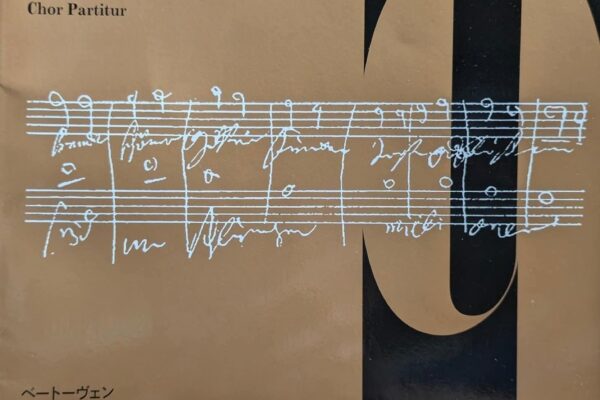太宰治と佐渡 (下)
生活者になる決意
三十路に入ったこの頃の太宰にとって、生活者になるということは大きな主題だった。上京して以来、度重なる自殺未遂や薬物中毒、生家からの除籍、精神病院への入院、同棲生活の破綻などで社会的不適応ぶりを見事なまでにさらけ出していた太宰は、師井伏鱒二夫妻の媒酌で昭和14年に結婚したが、そこには堅実な生活者として再出発するというつよい決意があった。生家から義絶同然の状態だった太宰は婚約にあたって井伏に保証人の役割を依頼したが、その際に書いた誓約書には次のように書かれている。
「結婚は、家庭は、努力であると思います。厳粛な、努力であると思います。浮いた気持はございません。貧しくとも、一生大事に努めます。ふたたび私が、破婚を繰りかえしたときには、私を完全な狂人として、棄ててください。」(井伏鱒二『太宰治』)
太宰の決意がこの時点で真剣なものであったことは疑い得ない。戦時中の三鷹での生活や、戦後しばらく郷里に疎開していた時期の生活ぶりは、二十代のころの無軌道からはほど遠い堅実なものだった。戦後、一躍人気作家になってからの太宰は精神の平衡を失い、荒廃した世相や身体的な衰弱もあって家庭から逃れて刹那的な快楽や放蕩に溺れていくことになるが、無頼派の名を決定的にしたその生活は38歳で自死するまでの2年間のことに過ぎず、三十代の太宰の生活の大半は元来が精神的にもろい太宰にしてはよくよく自制した上で営まれた手堅いものだった。『佐渡』の少し前に書かれた『東京八景』は、二十代の破滅的な生活とそこからの脱出を事実に即して振り返った小説だが、作中の「私」は結婚まもなく三鷹の新居に移り、武蔵野の夕陽が見える部屋でつましい夕食をしながら妻に「僕はこんな男だから出世も出来ないし、お金持にもならない。けれども、この家一つは何とかして守っていくつもりだ」とキザなことを言うのである。
しかし、堅実な生活者になるという覚悟が並々でなかった一方で、それを実践する太宰の胸中にその安定への倦厭の気持が重苦しく堆積していったことは容易に理解できる。一般論としても、そもそも堅実な小市民的な生活が性分に合い、それに充足できる人間が作家に向いているかどうかは、はなはだ疑問である。もちろん、自分を律し、家庭を大切にし、世間的な道徳と折り合いながらすぐれた作品を生み出す作家もいるだろう。しかし、その堅実さはたいていは絶えざる克己の上に危うい平衡をもって成り立ついわば擬態であるだろう。一体に、自分の世界を創造しようとする衝動の根源に現世の束縛から逃れ、自由をもとめる気持があるのだとすれば、創作という営為は多分に人を型にはめようとする秩序や制度に対立するものである。無軌道な青春ゆえに自身傷つき、真剣な反省の上に立って地道に生きる覚悟を持つに至ったその心事を疑うことはできないが、太宰ほどに本質的な表現者がいつまでもその思いを堅持するのは至難の業であるだろう。
結婚した年の8月に発表された『八十八夜』という小説には、早くも生活者であることに耐えがたさを覚える太宰の心境がよく表現されている。太宰自身をモデルとする貧乏作家「笠井さん」は、生来不器用で小心、一般に芸術家らしいとされる天衣無縫からほど遠い性格で、創作という危険な闇のなかを手探りで這うように進んできて、あまりの苦しさに精も根も尽き、5月のはじめ、有り金もって信州への旅に出る。かねて知った女性、といっても名前を知っているだけなのだが、その人が女中として働く温泉宿にアバンチュールを期待して向かうのである。
「めちゃなことをしたい。思い切って、めちゃなことを、やってみたい。私にだって、まだまだロマンチシズムは、残っている筈だ。…(中略)…笠井さんは、良い夫、良い父である。生来の臆病と、過度の責任感の強さとが、笠井さんに、いわば良人の貞操をも堅く守らせていた。口下手ではあり、行動はきわめて鈍重だし、そこは笠井さんも、あきらめていた。けれども、いま、おのれの芋虫にうんじ果て、爆発して旅に出て、なかなかめちゃな決意をしていた。何か光りを。」
言葉を失う「私」
信州に向かった笠井さんが期待していたものと、佐渡に向かった「私」のなかにあったものは、明暗において対照的であるが、いずれの場合も小心翼々たる小市民的な生活からの脱出を熱望しているという点で同じ硬貨の表と裏のようなものである。
「なぜ、佐渡へなど来たのだろう」とバスの中で自問しながら、「私」は金山のある相川まで行く。「佐渡には何も無い。あるべき筈はない」ということはわかっていた。しかし、「来てみないうちは気がかりなのだ」、「大袈裟に飛躍すれば、この人生さえも、そんなものだと言えるかもしれない。見てしまった空虚、見なかった焦燥不安、それだけの連続で、三十歳四十歳五十歳と、精いっぱいあくせく暮して、死ぬるのではなかろうか」。そんなことを考えながら、白昼の相川の町を歩くが、そこは歩く人もなく、がらんとしている。平成元年に資源枯渇のため、相川の金山は廃坑となるが、「私」が訪ねた昭和初期、まだ金山は稼働していた。しかし、江戸期には「佐渡へ佐渡へと草木もなびく」と佐渡おけさに歌われ、繁栄をきわめた相川の町も往年の面影はなかったのだろう。

すぐにでも東京に帰りたかったが、おけさ丸の便は明朝までない。相川に泊まることにして旅館に入り、金山に行こうとして女中に尋ねるが、その年の九月から見学できないことになったと言う。海岸に行くが、「何の感慨もない」。山に登り、日本海を見るが、寒くなったのですぐに下山する。「少しも気持が、はずまない」。これまでの旅路でもそうだったが、ここでも「私」は早々と相川に見切りをつけ、身もふたもない感想で終始していて、少しもその土地に寄り添う気持を示さない。たしかに別段変わったところのない海が広がっているだけで、「私」の感想も当たらずといえども遠からずというところなのかもしれない。
しかし、旅がよいものになるか、つまらないものになるかは、なによりも旅人がはじめて見るその土地にどのような姿勢で向き合うかによっている。「佐渡には何も無い。あるべき筈はない」と決めつけ、佐渡にすべての責を負わせるのは不当であるだろう。たとえば相川の金山にまつわる歴史をしのばせるものはいくらでもあっただろうし、佐渡を囲む日本海の風景もただ漫然と眺めるだけならば何の変哲もないかもしれないが、その水平線の彼方を思うことでしばらく時を忘れることもできるのである。
ちなみに、筆者も「私」同様、相川の旅館に泊まったが、宿の主人の話で、北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんがこの相川に近い町の人であることを知った。夫の元米軍人ジェンキンスさんは2017年12月に亡くなったが、佐渡金山跡の観光施設の土産物屋で働いていた。このあたりの海辺には主を失った北朝鮮の漁船がよく漂着すると聞き、口幅ったいようだがしばし感慨にふけった。これは現代の話だが、太宰のころは大陸で戦争が行なわれていた時代であり、相川の海のかなたにある朝鮮半島や中国大陸は日本人にとってあるいは今以上にその存在が重かったかもしれない。検閲が目を光らせていた時代で、海のかなたのことを気楽に書くようなことはできなかっただろうが、それにしても「私」の旅のやりかたには目の前の風物に対する意識的な働きかけが欠けている。そもそも作中の「私」をあえて太宰と重ねるならば、その佐渡旅行がつまらないものである理由は、何よりもその一人旅への適性のなさである。
新潟に戻った太宰は、来たときと同様に新潟高校OBの東大生と東京への帰途につき、車中で佐渡の不愉快だったことをぶちまけたと言うから、楽しい旅でなかったことは作中の「私」がこぼしているとおりなのだろう。しかし、太宰が味わった不愉快の実質は、ほぼすべて一人旅の淋しさ、寄る辺なさであって、気心の知れた友人とにぎやかに酒を酌み交わす佐渡旅行であったなら、また別の感想があったにちがいない。
もっとも、『佐渡』は小説であって、太宰の旅がこのままのものであったと見ることは軽率である。旅行下手を自任する作者が書いたこの小説は、陰鬱にして珍奇な滑稽譚の一種であって、「私」の言動はおおむね作者による確信犯的な創造であるだろう。すでに述べたように、この小説には芸術と生活、ロマンティシズムと現実の対立という主題が織りこめられていて、太宰が現実に行なった佐渡旅行という素材は、その主題に則って構成され、脚色されている。現実からの脱出をもとめて佐渡に来た「私」がそこにひたすら興ざめな現実しか見ないという物語は、かなりの部分、方法的な創作意識が生みだしたものである。しかし、この単調な小説は最後のところで、それまでのいささか滑稽な作品世界とは雰囲気を異にするなまなましい現実を静かに指し示して終わる。翌朝、早朝に起きた「私」はまだ薄暗い旅館の前で女中と並んで両津行のバスを待つ。
「ぞろぞろと黒い毛布を着た老若男女の列が通る。すべて無言で、せっせと私の眼前を歩いて行く。
『鉱山の人たちだね。』私は傍に立っている女中さんに小声で言った。
女中さんは黙って首肯いた。」
明治以降、相川の金山は官営となって近代化・機械化され、かつての無宿人は姿を消し、その働き手は各地から仕事をもとめてやって来た失業者になる。その労働環境は地獄といわれた江戸期に比べれば改善したが、相変わらず過酷で、逃亡者も多く、廃業する者も多かった。「私」がバス停で見たのは、朝鮮半島も含めた日本各地から仕事をもとめてやってきた貧しい労務者の群れである。「死ぬほど淋しいところ」というロマンティシズムをもとめて佐渡にやって来た「私」は、そこにあじけない庶民の生活ばかりを見いだし、不平を言い続けてきたのだが、最後にその庶民の生活の「最底辺」にうごめく人びとに遭遇し、粛然とする。あるいは、地底で働くこの黒い毛布をまとった人びとこそ、「私」が佐渡にもとめていた「地獄」の住人だったのだろうか。

本文中の引用は以下の書物から行ない、ただし旧漢字は新漢字、旧かなは新かなに改めた。
筑摩書房 太宰治全集 3巻(1975)、4巻(1971)、10巻(1971)
井伏鱒二 『太宰治』 1989 筑摩書房
津島美知子 『増補改訂版 回想の太宰治』 1997 人文書院
青野季吉 『佐渡』 1942年初版 1980年再版 佐渡郷土文化の会
主要参考文献
野本秀雄 「『みみずく通信』と『佐渡』のころ」(太宰治研究5号所収 1998 和泉書院)
磯部欣三 『佐渡歴史散歩 金山と流人の光と影』 1972年 創元社
田中圭一 『佐渡金山』 1980年 教育社
司馬遼太郎 『街道をゆく10 羽州街道、佐渡のみち』 1983年 朝日文庫
磯部欣三 『佐渡金山』 1992年 中公文庫
1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。