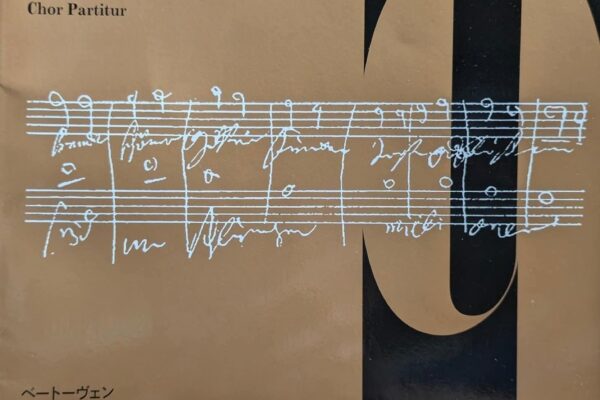太宰治と佐渡 (中)
意外性の島、佐渡
さて、太宰と小説中の「私」は厳密にいえば区別しなければならないので、後者については「私」と書くことにするが、船上の「私」は酔いを怖れて陰鬱な船室の片隅で毛布にくるまりながら、早くも後悔に暮れる。「死ぬほど淋しいところだ」と聞いていた佐渡に、「何の理由も無く」ひかれ、「こんな、つまらぬ旅行」を企てたのである。意外にもまったく酔わないので、甲板に出ると「空は低く鼠色」にたれこめ、「陰鬱な寒い海」、「真黒」な日本海の水が眼前にある。船は意外に早く佐渡と思われる陸地に近づき、その沿岸をながながと進む。航海の時間からして到着は早すぎるし、「私」はそれが本当に佐渡なのかどうかいぶかりながら島を見ている。しばらくすると船は向きを変え、その島の奥に向かい、港に近づくが、さて、そこにもう一つ別の島と見える陸地が姿を見せたとき、「私」はそれがどういうことか判断できず、さらには新しく姿をあらわしたその陸地の巨大さに戦慄を覚え、恐慌をきたす。「はるか前方に、幽かに蒼く、大陸の影が見える。…(中略)…満州ではないかと」思い、あるいは、日本の内地、はたまた朝鮮、ひょっとして能登半島かと疑う。
船が港に停泊して、ようやくそれが佐渡であることが確定するが、それでも「私」はあらためて佐渡に大陸を感じ、北海道とそんなに違わない、台湾とはどうかしらなどと考え、うんざりするのである。旅行先の土地が予想外に大きいことにうんざりするというのも奇妙な話だが、そもそも太宰治は巨大なものに対して感嘆したり、共鳴するということがなく、むしろ嫌悪する人だった。「富士には月見草がよく似合う」という『富嶽百景』中の言葉は、巨大なものに対峙して弱小ながらもけなげに咲く花に共鳴するところから出た言葉である。バルザックやフローベールよりはミュッセやドーデー、ドストエフスキーやトルストイよりはチェーホフやプーシキンが好きだった。(「わが半生を語る」)佐渡の大きさに、「私」は早くもこの島が自身にとって決してなじめないものであるという予感を抱くのである。

ところで、佐渡ヶ島への接近にあたって「私」が感じた不可解さは、都会から観光でやってきたとおぼしき家族客の会話によって氷解する。この家族の少女はその父親に航海の途上で島が二つあるように見えた理由を聞くのだが、それに対する父親の返答は「私」を納得させるのである。つまり佐渡は小佐渡と呼ばれる低い山脈をもつ島と、大佐渡と呼ばれる比較的高い山脈をもつ島が国仲平野という平野部で接着されたようなかたちをしているのだが、太宰はそれを「佐渡ヶ島は『工』の字を倒さにしたような形で、二つの平行した山脈を低い平野が紐で細く結んでいるような状態」であると表現している。まず小佐渡の南のほうに接近した船がしばらくその沿岸を北上し、小佐渡の北端から平野部に向かって回りこんだところで、高い山脈をもつ大佐渡の陸地が姿をあらわしたのである。
太宰は佐渡の大きさに辟易し、ふたつの島が平野でつながっているようなその独特のかたちに驚いたが、あまり予備知識をもたずに訪れる者には、佐渡は何かと意表を突く島であるだろう。太宰は佐渡の山脈には触れていないが、筆者は2018年の早春にこの島をはじめて訪れたとき、思いがけず高い山脈が雪をかぶったりりしい姿で迎えてくれたことに感激したものである。この印象は佐渡の意外な大きさにうんざりした太宰とは反対で、筆者の感性が平凡なものでしかないことを露呈している。日本最大の島である沖縄本島と第三位の淡路島の中間に位置する規模の佐渡ヶ島を、筆者は前二者と同じ比較的平坦な島のように勝手に考えていた。
太宰が乗ったおけさ丸は2時間45分で新潟港と夷港(現在の両津港)を結んでいたが、筆者が乗ったジェットエンジンで進む半ば飛行機のような船ジェットフォイルは時速80キロで同じ場所を運航し、一時間で目的地に到着する。安全ベルトをつけて座席に座っていないといけないので、窓の外に広がる海以外は何も見ることができない。旅情も何もあったものではなく、時間に余裕があれば今も太宰が乗船したのと同じ名前で運航しているフェリー「おけさ丸」で佐渡に行くのがいいだろう。甲板に立った太宰が佐渡ヶ島の独特な形状によって抱かされることになった錯覚のようなものもジェットフォイルでは経験しようもなかったが、それでも船を降りるときに見た大佐渡山脈の威容には驚かされた。

なにも見ようとしない旅人
晩秋の雨の夕暮れ、夷港(両津港)に着いた「私」は宿の客引きに車を呼んでもらう。車中から見る町は暗く、「房州あたりの漁師町の感じである」。旅館で女中についてもらって夕食をとるが、会話は途切れがちでぎこちない。太宰は気が許せる相手だと気持が大きくなって談論風発するが、そうでないときは手も足も出ない。ありがちなことだが、太宰の場合は万事に極端である。早い夕食が終わり手持無沙汰なので散歩に出るが、思ったほど淋しくはない。孤島の感じはなく、やはり「房州あたりの漁村を歩いている」ようである。料亭を見つけて入ったが、注文もしないのに魚介類を山のように持って来る。夕食を済ませたばかりでとても食べられない。勧められて芸者を呼んでもらうが、気のきかない芸者で話がはずまない。何の情緒もなく、「すべて、東京の場末の感じ」である。八時過ぎに宿に帰り、すぐに寝る。夜半、目覚め、ひどい孤独感に襲われる。
「ああ、佐渡だ、と思った。波の音が、どぶんどぶんと聞える。遠い孤島の宿屋に、いま寝ているのだという感じがはっきり来た。眼が冴えてしまって、なかなか眠られなかった。言わば、「死ぬほど淋しいところ」の酷烈な孤独感をやっと捕えた。おいしいものではなかった。やりきれないものであった。けれどもこれが欲しくて佐渡までやって来たのではないか。うんと味わえ。もっと味わえ。床の中で、眼をはっきり開いて、さまざまの事を考えた。自分の醜さを、捨てずに育てて行くより他は、無いと思った。」
夜中に目覚めて物狂おしい思いにとりつかれ、闇のなかで悶々とすることは誰にでもあるだろうが、太宰の場合はこれまた極端である。戦後に書かれた『母』という短編にも港町の旅館で酒を飲み、夜半に起きて波の音を聞きながら孤独なもの思いに苦しむ場面がある。過去の自分の醜態を思い出し、「いかん! つまらん!」などと呟き、床のなかで輾転とする。「泥酔して寝ると、いつもきまって夜中に覚醒し、このようなやりきれない刑罰の二、三時間を神から与えられるのが、私のこれまでの、ならわしになっているのだ」。
太宰治は自分にとりつかれた人間だった。旅をしても名所旧跡や風景にはほとんど興味がなく、自分のことだけを考えている。妻美知子によれば、新婚間もないころに上諏訪と蓼科に夫婦で二泊旅行をしたが、高原の秋を味わおうという気など微塵もなく、旅館に着くと部屋に籠って酒また酒である。「この人にとって『自然』あるいは『風景』は、何なのだろう。おのれの心象風景の中にのみ生きているのだろうか――私は盲目の人と連れ立って旅しているような寂しさを感じた」と美知子夫人は記している。(『回想の太宰治』)太宰の小説には風景の描写が少ないが、小説『佐渡』もそうである。翌朝、「私」は佐渡金山のある相川にバスで向かうが、車外の景色は次のように書かれている。
「けふは秋晴れである。窓外の風景は、新潟地方と少しも変りは無かった。植物の緑は、淡い。山が低い。樹木は小さく、ひねくれている。うすら寒い田舎道。娘さんたちは長い吊り鐘マントを来て歩いている。村々は、素知らぬ振りして、ちゃっかり生活を営んでいる。旅行者などを、てんで黙殺している。佐渡は、生活しています。一言にして語ればそれだ。なんの興もない。」
「私」がバスから見たのは、小佐渡と大佐渡といういわば二つの兄弟島をつないで広がる国仲平野の風景である。太宰は「なんの興もない」と冷淡だが、国仲平野はこれもまた意外性の島・佐渡の面目躍如たる場所である。山の多い佐渡にあって思いがけなく広々とした平野で、水田がのびやかに拡がっている。両津から相川に行くにはたいていはこの平野を抜けていくので、まったく同じルートではないにしても、筆者もこの平野を通った。水田のあいだに決して貧しげではない家々が点在し、晴天だったせいもあるかもしれないが、余裕のある明るさを感じさせる風景だった。

佐渡というと日本海の北に位置することもあって寒々としたイメージをもつ人も少なくないだろうが、実は対馬暖流に囲まれ、しかも島の北西部を覆う大佐渡山脈が大陸からの寒冷な風を防いでいるために新潟本土よりも温暖な気候に恵まれ、古くからの米どころであって、大量の米を島外に送り出してきた。晩秋なので、太宰、いや作中の「私」の眼には寒々として見えたのかもしれないが、この小説はことさらに佐渡をつまらない場所として描いている。絶海の孤島にふさわしい、人を寄せつけない、寒々しく荒涼とした風景、そのようなものをこそ期待していたのに、そこには意外にゆたかな漁村や平野があり、人びとはさして苦しげでもない生活を営んでいる。「私」にはそのことが許せなかった。
ドイツの建築家ブルーノ・タウトは戦前に佐渡を訪れ、そこで見た農家の雅趣に驚き、「それは私が日本で見た家屋のうちで、最も雅致あるものの一つであった。実に傑れた調和と高い文化を示す見事な農家である」(青野季吉『佐渡』による)と述懐している。実は佐渡の文化レベルは高く、そのことは風景にも反映しているのである。徳川幕府の天領として中央の行政に直結していただけでなく、大阪と北海道を結ぶ北前船の寄港地として関西とつながりがあったので、佐渡には江戸・大阪の文物がさかんに流入してきた。室町期に世阿弥が流されてきたことや、江戸初期の佐渡奉行がもともと能楽師だった大久保長安であった縁もあって、佐渡では能がさかんに行なわれるようになり、現在でも30以上の能舞台があるという。
『佐渡』は紀行文風の小説だが、その叙述には紀行文というものに必ずあるはずの土地への関心が稀薄である。逆に自分がその土地に相手にされない淋しさをかこっている。「死ぬほど淋しいところだ」と聞き、その法外さに惹かれて佐渡に来たはずなのに淋しさに耐えられないのである。ロマン派気質の太宰の分身である「私」がこの世のものでないような淋しさを期待してやって来た佐渡で見つけたのは、そんな旅人の気持を「黙殺」して「ちゃっかり生活を営んでいる」、「新潟地方と少しも変りはない」場所だった。そして、「私」の失望には当時の太宰が生活というものに対して感じていたやりきれなさが反映している。

1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。