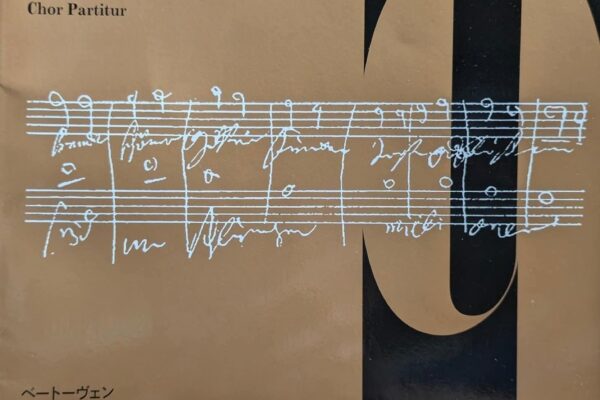ニーチェへの旅(1)— 国境の町バーゼル(上)
はじめに
今は亡き著名人の足跡をたどることになぜか言い知れぬ愉悦を覚える私は、さまざまな場所にフラフラと足を運び、故人の面影を偲んできた。この度、本サイトに掲載させていただけることになったので、これまで行なった旅に触発されて学んだことを文章化し、そこで味わった愉しさを何倍にもふくらませ、貪欲に反芻していきたい。手始めに、広範な人気があり、私もドイツ文学研究者として親しんできたニーチェについて2回にわたって書くことにする。
お断りしておくが、私が書こうとしているのはいわゆる紀行文ではない。紀行文を書くには、かすめるようにしてその土地を通り過ぎるだけの私の旅はあまりにも貧弱なものである。私の旅はいつでも漫然と歩き回ってその土地の雰囲気を味わうという態のもので、入念に観察したり、人びとと言葉を交わして土地の人情を知ったりというようなものではない。私が書こうとしているのは、大部分は、故人がそれぞれの土地に残したその足跡をさまざまな記録からたどるものである。個人的にその土地を歩いて得た印象や経験などを書くことは少ないだろうが、それでもその場所に足を踏み入れ、故人の人となりを思い浮かべながら歩いたことは何らかのかたちで反映しているのではないかと思う。
1. 国際文化都市バーゼルとニーチェ
2014年3月、私はドイツ、フランスと国境を接するスイスの都市バーゼルを訪れた。小国スイスにあって人口ではチューリヒ、ジュネーブに次ぐ町だが、それでも19万と日本の感覚からいえば中都市といった規模である。ライン河畔にあるバーゼルは古くから交通の要衝として栄えた町で、ライン川の橋の上から見る旧市街は歴史の重みを感じさせる。しかし、風光明媚な観光地がひしめくスイスにあって、アルプスの山々からはるかに離れた平地にあるこの町が観光面で脚光を浴びることは多くない。私がバーゼルを訪れたのも美しい風景や町並を期待してではなく、そこがスイス最古の大学町で、世界的な文化人が輩出し、住んだ町だったからである。特に、ドイツ文化を学ぶ者にとって、バーゼルの名は哲学者ニーチェがその大学で教鞭をとった町としてなじみが深い。私は、ニーチェの跡を追ってバーゼルに入ったのである。

ライン川沿いのバーゼル旧市街 著者撮影

バーゼル市庁舎 著者撮影
バーゼルはスイスのドイツ語圏にあり、ライプチヒ大学に学んだニーチェが1869年、24歳の若さで古典文献学の教授として赴任した町である。今日とは事情が違うが、当時でも24歳の大学教授というのは滅多にいるものではなかった。ニーチェはなみはずれた秀才だったのである。ニーチェが住んだ家は現在でも往年の面影をとどめる姿で残されている。ニーチェはこの町で『母権制』で知られるバッハオーフェンや歴史学者ブルクハルトなどの大知識人と知り合い、またさほど遠くないトリプシェンに居住していたワーグナーとも親交を深め、大きな影響を受けた。ニーチェは大学のほかにギムナジウムでも教えていたが、生粋のバーゼル人であるブルクハルトはギムナジウム教師としてのニーチェをとりわけ高く評価し、「このような教師はバーゼル人にとって二度とえられぬ教師だろう」(「ギムナジウム教師としてのニーチェ」35頁)と絶賛したこともある。
病のために10年ほどで大学を去ったニーチェはあらゆる組織から離れて孤独な著作活動に入るが、その生活を支えたのはバーゼル大学から支給される年間3000フランの年金だった。退職後のニーチェはイタリアに滞在することが多かったが、1889年の発狂に至るまでのほぼ10年間、夏はおおよそスイスの保養地ジルスマリーアに滞在し、その地を愛した。その著作にバーゼルやスイスの名前があがることはほとんどないが、ニーチェはバーゼルとスイスに決定的な恩義を蒙っている。国籍の上でも、ニーチェはバーゼルに就職が決まった際にプロイセンの市民権から離脱してスイス国籍を取得し、以後、法的には終生、スイス人でありつづけた。友人に宛てた手紙でもニーチェは「僕は僕のバーゼルが好きなんだ」(カール・フォン・ゲルスドルフ宛、1971年9月1日付)と語り、また、「自分はドイツ人のなかで暮らすより、スイス・ドイツ人のなかで暮らすほうがいい」(マルヴィーダ・フォン・マイゼンブーク宛、1877年5月13日付)などと書いている。

現在のバーゼル大学 著者撮影
バーゼルはその世界への開かれた立地や宗教的な寛容の精神ゆえに内外から傑出した精神が寄り集まり、コスモポリタン的な文化が花開いた土地である。ネーデルランドの人文主義者エラスムスは1514年、バーゼルに入り、以後1536年に当地で没するまでのあいだ、断続的にではあるがここを活動の拠点とした。19世紀にバーゼルの文化は華々しい開花の時期を迎え、すでに名を挙げたブルクハルト、バッハオーフェンに加え、『死の島』で知られる画家ベックリンなど世界的な才能が輩出した。また、スイスのボーデン湖畔で生まれ、バーゼル大学で学んだ心理学者ユングや、少年期をバーゼルで過ごしたヘルマン・ヘッセなどもバーゼルが生んだ大文化人といえる。ヘッセは少年期に学校の関係でいったんはドイツ国籍に移るが、作家となった後、第一次大戦時にその反戦的な思想ゆえにドイツ国内で物議をかもし、戦後はドイツ国籍を放棄してスイス国籍に復帰した。

ベックリン 死の島
ヘッセだけでなく、バーゼルゆかりの文化人の共通性としていえるのは、その端的な内面性と世界市民性である。それは地理的な条件によって育まれたものであるとともに、この町で古くから培われてきたヨーロッパヒューマニズムの伝統によるものであるだろう。こうした文化的性格をもつバーゼルは、世界市民的な教養人であるニーチェには水の合う町だっただろう。ニーチェは終生、バーゼルが生んだ記念碑的な人物であるブルクハルトを敬愛し、バーゼルに好意的な感情を抱きつづけた。
2. 世界市民としてのニーチェ
その荘重な口髭や、「力への意志」、「超人」といったキャッチフレーズゆえに、ニーチェには、ナチスのニーチェ像が典型であるような、ゲルマン魂を具現する勇猛果敢な哲人という虚像がしばしばつきまとってきた。特にニーチェが紹介されて間もないころの日本では、そうしたイメージが流布していたようで、たとえば漱石の弟子でドイツ文学者の小宮豊隆が寺田寅彦にあてた手紙には、「今の世の中のやつ等は、見かけが威嚇的に出来ていないと、駄目だと見くびって仕舞うから、いやになって仕舞う。こんど生れ変わってくる時は、山本権兵衛か、フリードリッヒ・ニーチェのような獰猛な顔に、生れて来たいものだと思っている」と書いている。(『ニーチェの顔』2頁)小宮のこの言葉を聞いたら、ニーチェはさぞかし喜んだだだろう。実際、弱さや同情を嫌い、強者たらんとすることを説いたニーチェが当時でもめったにないほどの大きな髭を生やしていたのは、威嚇的な外見を欲してのことだった。そのあたりの機微については、『曙光』のなかでニーチェみずからが明かしている。
<彼の「一面」を知る。――われわれは、初対面の人の眼には、自分で思っているところの自分とはまったく異なるものに見えているということを、すぐに忘れてしまうものである。印象を決定するのは、ほとんどいつも最初に眼に飛びこんでくる特徴である。だからこれ以上ないほど穏やかでやさしい人間であっても、大きな口ひげをたくわえてさえいれば、いわばその背後に身を隠し、落ち着き払っていることができる。――世間一般は、彼を大きな口ひげの付属品と見なす。つまり、軍人のような、怒りっぽい、ひょっとしたら乱暴な人物かと思う。――そこで、それ相応に彼を遇することになる。(Werke, Ⅴ₁-249f.)>
仮面の哲学者ともいわれるニーチェは、強壮な外見を作ることに苦慮する人だった。しかし、それはニーチェが考えていたほどに実効性のあるものではなかったようだ。実際のところ、父を四歳のときに失い、六人の女性のなかの唯一の男子として育ったニーチェは、乱暴さとは無縁の、女性的な物腰の、温和な印象を与える人物だった。実際にニーチェと出会ったすべての人びとの証言はそのことを伝えている。たとえば、女性との付合いが苦手なニーチェがただ一度、真剣な思いをもって求婚し、その拒絶によってあとあとまで残る深い傷をこうむったルー・アンドレアス・ザロメは、ニーチェの高貴な精神と孤独をたたえた風貌がもつ魅力を語りながら、「平常の生活においては彼は、きわめて丁重で、またほとんど女性的に柔和であり、好意的な落ち着いたむらのない気分をもっていた」と証言している。(『ニーチェ 人と作品』P.23~25)

ニーチェ
三島由紀夫は若年で保田与重郎の面識を得るが、その文学から「談論風発、獅子のごとき人物」を予想していたのに、実際に会ってみれば、同じ関西人の川端康成に似たその「言葉少なに低い声で語る言葉にかすかに残る上方訛り、何事にも大しておどろかない物静かさ」が「はなはだしく意外」(『私の遍歴時代』)だった経験を語っているが、ニーチェの場合も書くものと著者のたたずまいが驚くほど乖離している例の一つだろう。
ニーチェは、その過激な言説からあるいは想像されるような大胆不敵なゲルマンの豪傑からはほど遠い人物だった。熱愛した音楽家ショパンの祖国であるポーランドこそがみずからの父祖の地であるという根拠のない思いこみをしばしば得々と語ったニーチェは、またフランス文化を人類の精華と称揚し、ラテン的な風物全般を愛好する繊細なコスモポリタンだった。世界に開かれた普遍的な精神を志向するニーチェにとって、バーゼルはその哲学者としての経歴を始めるのには好個の町だった。たまたま出来た欠員による教授招聘という偶然によってニーチェはバーゼルと深い関わりをもつことになったが、哲学者ニーチェの世界市民性のいくばくかはバーゼルを拠点としたことから生れたといっていいだろう。
1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。