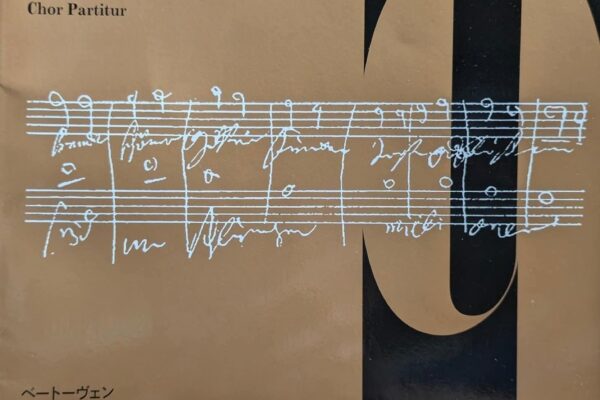現代温泉旅館事情(上)-または、木造宿への愛について
私が地の恵みを受ける場所としての温泉、そこの地図に打たれたピンのような役割をもつ昔ながらの開放的な木造旅館に惹かれるのは、子供の頃はまだ一般的であり我が家もそうであった木造平屋建ての建物への愛着と関係がありそうである。毎日縁側の拭き掃除、雨戸の開け閉めをせねばならず網戸もまだなかった頃で、夏は蚊や虫が入り冬は隙間風が入る寒い建物。しかし、縁側の履物を置く石から直接庭へ出入りできることからもわかるように、面倒なことは多いしエネルギー効率は悪くとも、開放的で外と繋がっているような建物。そんな我が家も大学の頃、都道の建設で土地を半分取られ、鉄筋の建物になると、その開放性は失われた。住宅の気密性は高まり快適にはなるものの、裏腹にそれはそのまま生活や日常での意識が内向きになることにも繋がる。以前は垣根越しに「お隣さん」とそれこそ鍋や調味料の貸し借りをしていたこともあったが、こういう住宅形態になると、いつのまにか隣がどういう生活をしているかもまったく見えなくなってしまうものである。私は東京オリンピック前に幼年期を過ごしただけに、都会化の過程で失われていくものへの郷愁が自然の中の木造の温泉宿への関心と重なるのだろう。
そういう木造旅館で、外観は変わらなくとも、その後もきちんとリフォームを重ね現代のお客さんたちのニーズに応えられるように磨き上げているところもあるが、そういう宿はいわば高級和風旅館で、宿泊料も高いしリゾート企業の傘下に入ってしまっていることが多い。個人が経営しているような、かつては宿泊施設の中核を形成していた中級の木造旅館は今でははなはだ旗色が悪い。まず、海外旅行の比重が増えたこと、飛行機代が安価になったことで、温泉地は旅行の花形ではなくなった上に、国内旅行は価格的には必ずしも安く行ける場所ではなくなってしまった。そして、生活の洋風化で若い人たちは、むしろ木造の古い宿の開放感などより密閉された快適さや小ぎれいさを好みアメニティを重視するようになっている。シャワーはあったほうがいいけれど、なければないで桶で浴槽から汲んで洗えばいいし、トイレも洋式の方がいいけれど和式ならそれでも構わないと考えているような私のような人間は少数派であり、そういう設備がきちんとしているかいないかは、この先旅館の死活問題になっていくだろう。
脱線するが、観光客より地元民が銭湯代わりに利用しているような旅館の中にはびっくりするようなところもあるので、ちょっと体験したエピソードを紹介する。佐久にあるA荘。階段をあがると、室内なのに外の非常階段のような薄い金属のような音がして微妙に揺れる。下はどうなってるんだろうと思った。もちろん共同トイレだが、当然和式だろうと思ったら洋式という紙が貼ってあるドアがあったので開けると、ウォシュレットではないオマル型の便器が置いてあったが、これがやけにドアに近い。座ってみると膝がドアの線より前に出て、ドアが閉まらないのだ。他に客もいなかったから、仕方なくドアを開けたままで用を足した。設置するとき何も思わなかったのだろうか?クレームもあっただろうが、ここまで根性が座っていれば平気なのだろう(笑)フロントに「フリーワイファイあり」と手書きで書いてあるので、いやな予感はしたが女将に「パスワードは?」と聞いたら、「待ってて、聞いてくっから」と言って一旦奥に引っ込み、戻ってきて「電話番号だって」とのこと。やってみると、やはり接続しない。ダメだと言ったら「あら、そお?わたしよくわかんないから(がはは)」との返事で、こちらも絶句した。朝風呂に行こうとしたら、階段の上に「朝は女湯です」という木札がかかっているので「あの、朝は入れないんですか?」と聞いたら「女湯の方に入ってよ」との答え。そういう意味か。いやはや、万事にアバウトな宿であった。
和歌山県紀伊長島のA久寺温泉は文字通りの木造のボロ宿で、夕食を古い広間で食べるのだが、すぐそこになぜか宿の高齢のおじいちゃんが布団に入って寝ていて、時々目があったりして妙な緊張感がある。一部屋ぐらい家族用に空いてる部屋あるんじゃないのかな?その雰囲気に相反するように、海の近くなので魚のうまかったこと。とはいえ、「うまい!鮮度いいねえ」などと声をあげるわけにもいかず、黙々とその味を噛みしめていたのだった。しかし、漂泊の漫画家つげ義春の傑作「ほんやら洞のべんさん」には、別居中の妻の実家から盗んできた錦鯉(新潟は冬期の鯉の観賞用の鯉の養殖で有名である)が夕食に出たり、酔ったその宿の主人のために布団を敷いてあげ、隣に並んで寝る話が出てくるのだから、上には上が(いや、下には下か)あるものである。
もちろん、私がこういった絶滅「非」危惧種の宿を積極的に好むと言うわけではなく、もう一度行こうとも思わないのだけれど、これもまた旅の楽しみと面白がれる我が性向は、やはり子供の頃にあったある種のおおらかな世界へのノスタルジーと無関係ではないと感じている。どうも私は隅々まで行き届き備品が揃っていることはどうでもよく、こちらが自由に開放感を味わえる余地があるかどうかを重視したくなるのである。ネットに載る口コミ情報を見ていると、部屋の隅に埃が落ちていたとか、障子の桟にクモの糸がついていたとか、到着時に呼んでもすぐに出てこなかったとか、シャワーがなかった、あるいは隣の人のシャワーがかかった等々、細かいケチをつける人が多いことに驚く。さっきあげたような宿は極端だとしても、せっかく温泉に来たんだから、いいお湯と自然環境、そこそこおいしい食事とシンプルだけど寛げる部屋があれば多少のことはいいじゃないかと思ってしまう。
二度目の東京オリンピックの開催が決まり、国を挙げて「おもてなし」を日本文化の積極的プラスの特性として前面に出そうとしているが、現代の日本では、他者のために施す細かいサービスは、自分が受ける側に回り、それが他者に足りないと感じると容易に神経症的クレームに反転しかねない。「空気を読む」ことは気遣いでもあり、同調を強いる圧力でもあるのだ。昨今言われている「自由にものが言えない社会になってきた」という状況はネットにおける匿名の野放しの毀誉褒貶と表裏一体の関係にあるのではないか。
その結果はどうなるのか?誰しもが自分で好きに楽しみ方を創ろうという姿勢よりも、すでに与えられた既製品の質を細かく採点するのを重視する社会が現れてくる。まず「何もない」ことをよしとするのではなく、「何かを用意してくれる」ことを求める気持ちは、余暇産業においては「テーマパーク化」と連動するが、それがときに「何もない」「邪魔しない」ということをも意識的に演出しつつ、一方で各種イベントも企画するという二面性を伴うのは、H野リゾートのサービスのスタイルを見れば明らかだろう。そしてこのテーマパーク化は同時に旅館においても、富裕層のための高級路線と低所得者やファミリーのためのファミレス路線の違いはあれ、その二傾向が同時に進行していく。前者の代表がH野リゾートだし、後者の代表がO江戸温泉物語やI東園グループということになるだろう。それを担うのは巨大リゾート産業で、経営が立ち行かなくなった旅館を次々吸収しチェーンにしていくのは、地方の商店街がシャッター化し皆大規模スーパーに車で買い物に行くようになることとパラレルである。後者の格安路線になると、一泊バイキング・飲み放題付き、カラオケ無料で1万円を切るという価格設定はファミレスや回転寿司を支持する層に人気であるのは言うをまたないし、こうなると個人経営の小規模旅館は苦しい立場になってくる。少子化が追い討ちをかけ、いま旅館業界では後継者問題が深刻になっているし、先ほど書いたように、時代に合わせたアメニティの需要に合わせるための設備投資をしないことには客を呼べない状況になっている。この絶えざるリノベーションに応えられるのはリゾート産業しかないのだ。前にあげたような地元民密着のC級旅館は、やがて廃業することを前提に続けられるところまでやる、だから設備もこれで我慢してほしいという潔さがあるけれど、厳しい選択におかれているのは、それなりの規模や伝統もあり全国から客が来ていたはずの、そして最も数が多かった中級規模の旅館である。江戸や明治期に創業の老舗があっけなく店仕舞いしてしまう話は旅館業界ならずともこのところ後を絶たないし、袋小路で身動きができないような例は枚挙に暇が無い。
一方で、世の中には一流を目指したがる人間はいるもので、いくつかの月間女性誌のゴージャスな路線、そして食雑誌DANCYUのレギュラー執筆者だった柏井壽やグルメ評論家の山本益博といった人たちの文章は、リゾート企業による旅館やホテルの高級チェーン化に対してもセレブの大衆化として、自らをさらにその上の「本物を知る」人間として差異化するような傾向を見てとれる。つまり一流の文化を理解でき、享受する資格のある自分を選民、貴族の位置に置くわけである。だがそれが、しょせんは「広い」現実に目をつぶることでしか成立しない「狭い」範囲での快楽のレベルの問題であり、飽食と美食の時代で鈍化した倫理の問題がそこにある。「考える舌」(山本益博)とは私にはどうしても、脳が思考を停止したから代わりに舌が考えるようになったという意味に聞こえてしまう。「味な宿に泊まりたい」(新潮社)の中で、山本は京都の俵屋旅館のベテランの仲居さんに夕食時のビールの銘柄が何がいいかと聞かれ「キリン・ラガー」と答えたとき、この仲居さんならこのことを記憶するのではないかと思ったという話を持ち出し、はたして次に訪れたときその通りだったとことに感激したことを書いている。本物の文化の送り手と本物がわかる受け手に通じ合う瞬間があったと言わんばかりであるが、それを味わえる特権はむしろ秘しておくことで貴族的にもなりうるのに、語られた途端卑しいものになることがこの著者には見えていない。「何回か泊まるうち、他の宿では絶対に満足できないような客になってしまうだろう、というのが、泊まってみての正直な感想である」と山本は言うが、これこそが「考える舌」の行く着く先である。「他の宿では絶対に満足できない」と言うことが言動の節度を欠いた、「広くあろうとする」思考を切り捨てているからこそ、舌という局部が考えるという比喩に安住してしまう。閉じた世界での経験が一般的に通じるものと思い込む勘違いに気付かないからこそこの著者は「食べ歩きのし過ぎで自らがフォアグラ状態」になったと誇らしげに言えるのであろうし(本人は文化に貢献するため食に身を捧げた求道者のつもりでいるのだろう)、この旅館についての本でも、「湯布院はまるでオーベルニュのようだ」と旅館無量塔の主人に話しながら、「三回たずねるのもよし、湯布院の御三家(無量塔、玉の湯、亀の井別荘。いずれも宿泊費一泊4~5万円)をハシゴするのも楽しい」などと書いている。なんともまあ、おめでたい話だ。
話を戻そう。伊豆長岡に南山荘という広大な庭園に離れ形式の部屋が点在する老舗があり、かつては川端康成はじめ文人や政治家も訪れた風格ある木造宿である。


旧南山荘全景(左)、斜面の建物をつなぐ階段(右)
庭の斜面に木造の味わいある階段が走っていて、エレベーターはない。かつてはそこを仲居さんが上り下りしそれも宿の風情ある光景だったのだろうが、人件費の節約で部屋食をやめて一階の食事処で食事を取ることにしても、今日の宿泊客は食事や入浴のときの階段の上り下りだけでもう不満を言いそうだし、その階段や庭園の維持費だけでも費用は馬鹿にならないだろう。結局この旅館は、大胆にも食事なしで一泊4000円ぐらいの格安方式に切り替え、夕食は外のレストランを紹介するか出前を取るという苦肉の策に出た。朝食はロビーでセルフで簡単なトーストとコーヒーを供するという思い切った作戦である。しかしである。やはり、器というものは本来それに相応しいものを盛るためにある。その階段もかつてはお客さんや宿の人たちが行き交って華やぎを感じさせる場所であったのだろうが、今は夜など真っ暗でしーんとして怖いぐらいである。その人気の無い階段を上下して夜の露天風呂に行くのも侘しいものである。やはり宿の構造が二食付きという日本旅館の伝統的形式を要求しているのであり、この旅館の場合はもはやかつてあったそういう文化、文士が泊まり小説を書き、宿の主人もその地域の文化の担い手であったような時代にしか存在できないことを痛切に感じた。案の定南山荘はほどなく倒産してしまった。
夏目漱石が滞在したことでも有名な湯河原の天野屋旅館も重厚な木造建築だったが、こちらはリゾート企業に売り渡したら、その会社はあっさり建物を壊して、周囲の風景とと調和する建物などという配慮も無く巨大なリゾート・マンションを建ててしまった。せっかくの文化財のような建物なのだから町にでも売って保存すればいいのにと言っても、巨額の金を積まれたら、廃業する側にしてみればそちらになびくのは致し方ないところだろう。(続く)
東京都杉並区生まれ。都立富士高校卒。東京大学大学院ドイツ文学科で修士号取得。弘前大学を経て、現在成城大学に勤務。東京大学、東京芸術大学、東京女子大学などで非常勤講師。専門分野はカフカを中心としたドイツ近現代文学、古典派~ロマン派の音楽。論文で扱った作家、哲学者、音楽家は、カフカ、リルケ、ニーチェ、ハイデガー、ハントケ、シューベルト、ベートーヴェンなど。共訳書にヴォルフガング・イーザー『虚構と想像力-文学の人間学』。研究分野に関しても、現在のポップカルチャーを扱うにしても、アカデミックな閉域にもオタク的趣味の閉域にも籠もらぬよう、常に時代と世界に向けて風通しをよくしておきたいと考えている。