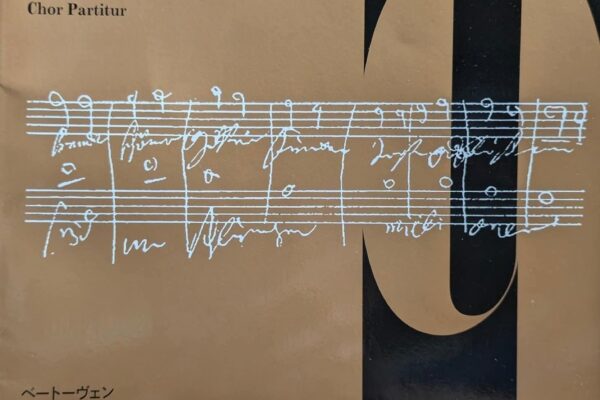バイロイトの宮廷劇場
バイロイトの優雅な街区
前回紹介したバイロイトの旧市街地の南西側、新旧の宮殿や官房(Kanzlei、日本で言えば藩庁)がある一帯から崖下に下りたあたりには、18世紀に建てられてた宮廷関係の大建築物が並んでいて、バイロイトにおけるもっとも優雅な街区である。旧宮殿から降る石段の下には華麗な大噴水があり、その噴水を囲む広場の向こう側には仮面舞踏会場だった建物が見える。
同じ舞踏会でも、通常の舞踏会がいろいろな行事にちなんで大人数で行われ、比較的開放的で、参加制限も緩やかだったのに比べると、仮面舞踏会(Redoute)は参加資格がやかましく、身分の高い人でないと入場できなかったと言われている。これは仮面、仮装によって本人であることを隠して楽しむのが趣旨の催しであるため、誰でもというわけにはいかなかったためだろう。
別の意味で権威ある建物として、ユダヤ教のシナゴーグもこの近くにあった。今あったと過去形で書いたが、実はシナゴーグとユダヤ人会館が今でもほとんど同じ場所にあるのだが、建物はごく目立たないものである。
中からは子供達の遊び声が聞こえてくる。ユダヤ人家庭の子供はいつもここで学校後のひとときを過ごしているようである。私が門扉の格子越しに覗いていると、白いユダヤ帽子キッパをかぶった色の白い少年が、「だめだめ!」(Nein, nein!)と甲高い声で叫んで私をにらんだので立ち去った。

辺境伯歌劇場
これらの建物の中でも一番華麗なのが、辺境伯歌劇場(das markgräfliche Opernhaus)であり、ユネスコ世界遺産になっている。
バイロイトと言えば、リヒャルト・ヴァーグナーが建てた祝祭劇場(Festspielhaus)が有名だが、あちらは建物としては取り立てて見るべきところもない単純な造りのもので、地元の人の中には体育館のようだと揶揄する向きもあるようだ。
ヨーロッパ各地の有名なオペラハウスは、ヴィーンの国立歌劇場でも、パリのオペラ座でも、19世紀の後半の建築が多く、また18世紀のものでもその後頻繁に使われて来たところでは、細部に近代化が施されているものだ。
ところがこのバイロイトの歌劇場は、当時の建物が原形のまま残っている、ヨーロッパでも数少ない例なのである。
これにはバイロイトの歴史的な経緯が影響している。18世紀末にバイロイト辺境伯家直系が断絶し、その後のヴィーン会議でも復活せずに、バイエルン王国に併合されてしまったため、19世紀以後はバイロイトには宮廷が存在しなくなった。そのため本格的に使われることがなかったという事情が幸いして、オリジナルのまま残ったわけだ。
18世紀のオペラで活躍した、去勢された男性ソプラノ歌手の代表者ファルネッリの生涯を描いた映画『カストラート』で、ロケに使われたのは他ならぬこの劇場である。
辺境伯妃ヴィルヘルミーネとベルリンのフリードリヒ大王
この歌劇場を建てさせたのは辺境伯妃ヴィルヘルミーネで、すでに前回書いたように、彼女はベルリンのホーエンツォレルン家、つまりプロイセン王家の出身で、大王と呼ばれるフリードリヒ二世の姉だった人である。本来なら大国に嫁いでもよかったのに、バイロイト辺境伯という田舎の小さい君主国の、弟と同じ名前のフリードリヒと結婚した。実際彼女には、後にイギリス王になるハノーファー選帝侯家や、ポーランド王も兼ねていた強国ザクセン選帝侯家との縁談もあったが、これらはいろいろな事情でうまく行かなかった。
彼女は自身優れた作曲家であり、数々の合奏曲やオペラを作っている。中でもチェンバロ協奏曲は高いレベルの作品として評価されている。音楽の才能に恵まれているという点では、弟のフリードリヒ大王もよく知られている。
ちなみに、ちょうど同じ頃、チューリンゲンの森を挟んでバイロイトと南北対象の位置にあり、規模もほぼ同じ君主国だったヴァイマルでも、アンナ・アマーリアという公妃がいて、彼女も高い音楽の才能を持っていたので有名である。彼女はまた、息子のカール・アウグストの家庭教師に、ドイツロココ文学の代表者とされるヴィーラントを招聘したのを初め、ゲーテに至る当時最高レベルの文化人を何人もヴァイマルに住まわせ、この田舎の城下町をドイツ文化の中心地に仕立て上げた功労者である。
同じ頃、ヴィーンにはマリア・テレージア、パリにはポンパドール夫人、ペテルブルクにはエカテリーナ女帝と、優れた女性が政治、文化をリードしていて、18世紀は(少なくとも王侯貴族の間では)女性の時代だったといえるかも知れない。
さて、ヴィルヘルミーネがバイロイトに嫁いで来たころは、バイロイト宮廷は緊縮財政をとっており、宮殿の修理もままならない状態で、彼女を大いに落胆させた。しかし彼女の配偶者であるフリードリヒ三世が即位すると、さっそく劇場や離宮の整備に取りかかることになる。
すでに旧宮殿には付属劇場があり、またこのころ新造営された離宮にはそれぞれ劇場や野外劇場が建てられたが、ヴィルヘルミーネはそれらには満足せず、本格的なオペラハウスを望んでいた。
丁度そのころ、ベルリンではフリードリヒ大王の肝煎りで、大きなオペラハウスの建造が始まっていた。これが現在のベルリン国立歌劇場の前身、王立歌劇場である。ヴィルヘルミーネはこれに多いに刺激され、弟に建設の詳細を問い合わせる手紙を何度も送っている。「あなたのオペラハウスの設計図を私にも見せてくださいな。これは完璧な歌劇場になるんですよね。」とか「設計図を見るのが待ちきれないの。これはすばらしい建物で、ヨーロッパ随一の大きさになることでしょう。」などの文面からは、弟の建てるオペラハウスへの抑えきれない興味が伺える。
建築の進展と完成
ヴィルヘルミーネは、バイロイトの歌劇場の建築責任者として、最初はベルリンの歌劇場を建てたコーベルスドルフという建築家を、弟のフリードリヒ大王に依頼して契約しようとしたがこれは頓挫した。折からいわゆるオーストリア継承戦争が勃発し、オーストリア側からの圧迫を受けたバイロイトはプロイセンに与することができず、政治的にプロイセンと対立する形になってしまったのが原因である。
そこでヴィルヘルミーネは、以前からバイロイト宮廷に仕えていたフランス人建築家のサン=ピエールという人に工事の開始を命じることになる。
また内装と舞台装置はイタリア人建築家のカルロ・ガリ=ビビエナに委託するのだが、この人は息子のジュゼッペとともにバイロイトの他の宮廷建築にも関わり、「バイロイトロココ」といわれる繊細で簡素なバイロイト独特の美意識の、室内装飾の分野での推進者となっている。
このようにして辺境伯歌劇場は、1748年9月27日、ヴィルヘルミーネ夫妻の娘、エリーザベト=フリーデリケ=ゾフィーと、ヴュルテンベルク公カール・オイゲンとの結婚式の祝典をもってこけら落としとなった。
このカール・オイゲンは、シラーの伝記には必ず登場する有名な殿様だが、詳しい話は別の機会に譲ろう。一方エリーザベトは、当時のヨーロッパの諸君主家の女性の中で、一番の美人として有名だった。
この新築の歌劇場を主な会場とした二人の結婚式の祝宴は、3日間続く盛大なものだったのだが、しかしこの二人の夫婦関係は10年も経たないうちに破綻し、エリーザベトはヴュルテンベルクの首都シュトゥットガルトを去り、故郷バイロイトで余生を送ることとなる。20代半ばから寡婦となったエリーザベトが生涯住んだ離宮は、フォンテジー宮殿(Schloss Fantaisie)で、「幻想宮」とでも訳しておく。

18世紀の音
辺境伯歌劇場では、今ではさすがに大がかりなオペラの上演は行われていないが、器楽や声楽のリサイタルは年に数回ほど催される。私は10年ほど前に、シューベルトの『美しき水車小屋の娘』(歌ったのはヨナス・カウフマンだったかと思うのだが、記憶があいまい)を聞いたことがある。
残響が少なく、くぐもったような柔らかい音の響きで、現代のクリアーカットのCDの音に馴れていると、少々迫力に欠けるようにも思えたが、これが18世紀の貴族が聞いていた音と、今日の工業社会の私のような一般市民が聞いている音の差なのだろう。18世紀の音は、言ってみれば生身の人間が求める音、現代の音は、メカニズムになれすぎてサイボーグ化したわれわれの身体が求める音なのかもしれない。
同じようなことは、建物の内装にも言えよう。最初に観客席に入ったときには、絢爛豪華な装飾に目を奪われ、これぞヨーロッパのイメージそのもの、遠路見に来た甲斐があった、などと思うのだが、しばらくして眼が薄暗がりになれてくると、自分の身体の周囲がすべて木でできていることに気づいてくる。くすんだ塗料が塗ってあってところどころ落剥しているところもある。華やかであってもしっとりとして、退廃的で、同時にどこか懐かしい感覚が湧いてくる。
ヨーロッパの他の都市でも感じることだが、宮殿やオペラハウスの華やかな美しさは権力者の威厳を示すためのものである、と教科書に書いてあるが、そういうところに行ってみると、奇妙にも空間が優しさを持っているように感じる。人間中心主義を唱えたコルビジェやバウハウスの建物よりも有機的な感覚を味わえる。料理でも高級になればなるほど、家庭料理の味に近くなるのと同じことかもしれない、と私は思うのだが。
1953年5月31日 長野県生まれ。
1960年より長野県小諸市にて少年時代を過ごす。
長野県立上田高等学校卒業
東京大学文学部、同大学院でドイツ文学を学ぶ。
1987年より筑波大学でドイツ語、ドイツ文学、ヨーロッパ文化等の講義を担当。
研究領域:ゲーテを中心とする18世紀末および19世紀初頭のドイツ文化
最近の研究テーマ:バレエの歴史と宮廷人ゲーテ、18世紀の身体美意識とゲーテ、ゲーテ時代のサロンの瞬間芸(タブロー・ヴィヴァン、アチチュード)