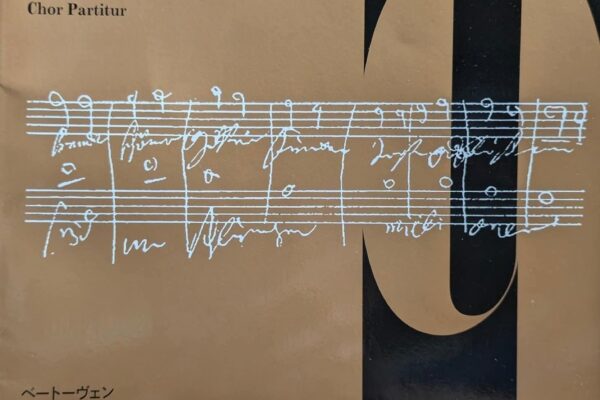ゼンパー歌劇場とドイツ人の家族
ドレスデンといえばゼンパー歌劇場Semperoperのことを書かねばなるまい。私のドレスデン・シリーズの最後に、この有名なオペラハウスの訪問記を残しておこうと思う。
クラシック音楽ファンは、ドレスデンといえばこの歌劇場のこと、そしてここの専属オーケストラであるドレスデン・シュターツカペレ(Sächsische Staatskapelle Dresden)を真っ先に思い浮かべることだろう。
私もスイトナー指揮のモーツァルト交響曲(特に第29番K.201が好きだ)やオイゲン・ヨーフム指揮のブルックナー交響曲(特に第8番第3楽章の宇宙的な響き!)で以前からこのオーケストラのすばらしさは知っていた。それに前回の1990年のドレスデン訪問のとき、ロッシーニの『セビリャの理髪師』で、絹のように滑らかな弦のアンサンブルと明るく調和のとれた管の響き合いを心ゆくまで楽しんだことは、いまだに忘れられない。
今回はヴァーグナーの『さまよえるオランダ人』の初日だったが、当初の旅行の予定に入っていなかったので、切符を持っていなかった。だが前回の訪問時に、開演前に広場にいる人から購入して難なく入れたのを思い出したので、今回もその方法を試みることにした。いわゆるダフ屋である。そこで開演の1時間ほど前に広場に行くと、案の定何人かが声を掛けてきた(しかも公式の当日券窓口の真ん前で!)。日本のこの手の商売をする人とちがって、みなごく普通の市民という印象の人たちである。結局私が券を買うことにしたのはさる中年の品のいいご婦人からであった。ベージュのオーバーコートを着て薄化粧の、典型的な中流家庭の主婦といった印象である。彼女は券を見せながら、実は今日家族みんなで来ようと思っていたのだけれど、夫が風邪を引いてこれ来れなくなってしまったの。だから、私のとなりの席よ。4階だけれど正面で、いい場所だと思うわ、と、盛んに奨める。私なら隣に座っても安心だと踏んだのかも知れない。当方もこのご婦人ならだまされることはあるまいと判断し、金額もかなり安かったので買うことに決めたのである。
ホテルに戻ってシャワーを浴び、ツィードのジャケットにネクタイを締めて再び歌劇場に行く。ゼンパー歌劇場の外観は、石材が黒ずんでいることもあって少々いかめしいのだが、内部は大理石をふんだんに使いながらも、天井や壁には至る所フレスコによる装飾が施された温かみのある空間である。これは設計者ゼンパー(Gottfried Semper)が新古典主義といわれながらも、同時代のイギリスのラスキンなどの手工芸回帰の思想から影響を受け、素材の肌感覚を重視したためであるらしい。今の建物は戦争で破壊された後ようやく1985年に復興したものだが、最初にゼンパーが建てた建物も火災に遭い、同じくゼンパーの設計によって1869年から1878年にかけて再建されたもので、完成時にはゼンパーはすでにこの世を去っていた。

ゼンパー歌劇場(外観)

ゼンパー歌劇場(内部)
さて、その席にいってみると、券を売ってくれたご婦人はすでに着席していたのだが、更にその横には、娘さんと息子さんが並んでいる。丁度私がこの家族のパパのような恰好になってしまった。
娘さんは赤い縁の眼鏡を掛けた知的な感じのお嬢さんで、20歳くらいだろうか。私が席に着くと笑顔を浮かべて挨拶し、ああ、お母さんが話していたのはこの人ね、というような表情で歓迎してくれた。
息子さんの方は15歳くらいだろうか、ブロンドで色白の整った顔立ち、真っ白なシャツを身につけ、清潔感が漂う絵に描いたようなドイツの美少年である。お母さんの話によると、彼はピアノを習っていて、今日はそんな彼に生まれて初めてオペラを見せるのだそうだ。
お母さんは、ここのオーケストラは一流なのよ、それに歌手もすばらしいの、と自慢げであった。
このご一家、私などが子どもの頃から何となく抱いてきたヨーロッパの中流家庭のイメージそのものである。
私はドイツ人とつきあい始めてからもう30年以上になるが、専ら旧西側の人たち、それも大学関係者が多かった。私と同世代の人たちの中には、1968年の学生運動の影響を受けて、服装もジーンズにTシャツ、長髪に無精髭を生やしているという風体の者も目立った。そのあまりの威勢の良さに、私などはいつも気後れしてしまっていたものだが、もっともこうした人たちも年を取るにしたがって「ふつうの」市民に落ち着いて来ているのだが、そうなると今度は今の日本の中高年とそれほど変わらない、物わかりの良さそうな年配者の顔つきになる。彼らを見ていると、どこに行っても現実の人生はこんなものなのかと、少々がっかりする。若い頃の彼らの社会批判の口吻に、さすがはドイツのインテリと感心したり、内心反発したりしていたのが、結局ドイツ人が特別賢いわけでもなく、日本が遅れているわけでもなかったと最近では思う。
そんな中でこのご一家のように一昔前の教養市民階級を彷彿とさせる、きちんとした印象の人々を見ると、どういうわけか妙な安心感が湧いてくる。これは偏見かも知れないが、旧東ドイツの地区だからこそ、まだこんな人たちが残っているのかとも思う。
さて、『さまよえるオランダ人』の演奏の方だが、この日は初日だった。このご家族とひそひそ声で話しているうちに、オーケストラの団員が一人、また一人とオーケストラボックスの席に着き、自分のパートをさらっているのが聞こえてくるようになった。フルートのぴらぴらという甲高い音や、ファゴットが低音から高音までの音の出方を確かめるように音階をならしている中に、序曲冒頭に現れる海辺の警報のようなホルンの有名な旋律も切れ切れに聞こえる。
やがて照明が落ち、観客の咳だけが響くようになると、指揮者がスポットライトに導かれて登場する。この日、マエストロは(ティーレマンではなかった)松葉杖をついての登壇である。
一瞬の静寂、そして指揮棒が振り下ろされて、序曲の冒頭、砂浜の風のうなりが弦楽器で短く奏でられると、ホルンがあの警報のような旋律を響かせる。さきほどさらっていた旋律である。これをトロンボーンが引き継ぎ、さらに弦楽器も加わって、不吉な嵐の浜辺の風景がしばらく描写されると、一転平和でどこか寂しげな牧歌が木管によって歌われる。
私なりに素人解説を書いてみたが、この曲をご存知の方には余分なおしゃべりだろう。ただ、この曲のおもしろさは、オーケストラの各パートを思う存分に響かせながら、アクセントを強調した激しいリズムを巧みに受け渡すところにある、ということを言いたいのである。
ところが、である。この日のシュターツカペレは、アインザッツが揃わない。もたもたと引き摺るようなリズムである。私の推測だが、指揮者が怪我をして、あまり練習時間がとれなかったのではあるまいか。
劇としての演出は説得力のあるものだった。この物語は従来の読み方では幽霊船の船長という男の救済がテーマとされてきたが、この演出では男に翻弄される女性の視点からのストーリーになっていた。原作にはない少女が登場し、女性の視点が二重化され、一人の女性の男性との出会いとその記憶、女性の人生における男性の存在と不在、女性の間の連帯感などが巧みに描かれていた。歌手も合唱もさすがにすばらしかった。
終演後、4階席からの階段を切符を買ったあのご一家と一緒に降りてきた。「ご感想はどう?」とご婦人から聞かれる。私は思わず「うーん」と唸った後、「歌手はすばらしかったです。でもオーケストラが…」と口走った。しまった、と思ったがもう遅かった。彼女は「あ、そう。では、さようなら」と、こちらを振り返りもせずに、先に進んでいってしまった。娘さんも息子さんも、遅れじと後を付いていった。私はまた自分の悪い癖が出た、と苦い気持ちで歌劇場の前の石畳を横切り、王宮脇のホテルへと帰った。
1953年5月31日 長野県生まれ。
1960年より長野県小諸市にて少年時代を過ごす。
長野県立上田高等学校卒業
東京大学文学部、同大学院でドイツ文学を学ぶ。
1987年より筑波大学でドイツ語、ドイツ文学、ヨーロッパ文化等の講義を担当。
研究領域:ゲーテを中心とする18世紀末および19世紀初頭のドイツ文化
最近の研究テーマ:バレエの歴史と宮廷人ゲーテ、18世紀の身体美意識とゲーテ、ゲーテ時代のサロンの瞬間芸(タブロー・ヴィヴァン、アチチュード)