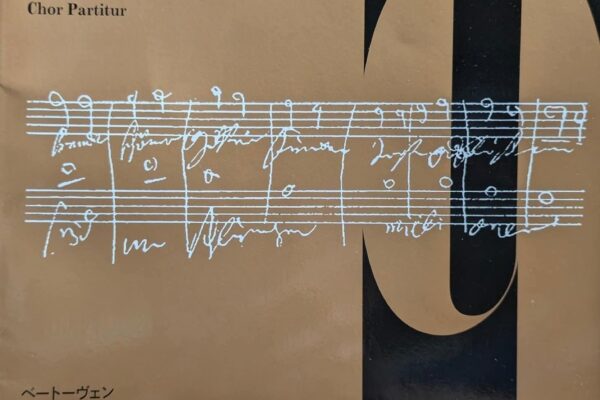太宰治と佐渡 (上)
旅が下手な旅人
旅の仕方には人となりがあからさまにあらわれるものである。太宰治もつくづくそう考えていたようで、その最晩年に書いた文章のなかで「人間の一生は、旅である」といい、さらには「旅は、徒然の姿に似て居ながら、人間の決戦場かもしれない」と怖ろしいことを語っている。(「『井伏鱒二選集』後記」)太宰は人間を旅行上手と旅行下手に分けているが、師の井伏鱒二を「旅の名人」であり人生における不敗の達人とする一方、みずからを旅行下手の見本に挙げている。

太宰治はしかし決して旅をしない人ではなく、むしろ人並以上によく旅をした。友人知己と温泉などへ頻繁に旅したほか、三島や御坂峠・天下茶屋、伊豆の湯ケ野、箱根などに単独で滞在して小説を書き、戦後は『人間失格」の大部分を熱海の旅館起雲閣、最後の部分を筑摩書房の社長である古田晃に紹介された大宮の家で書いているが、これらの滞在もまた広義の旅といえる。
転居についてはすさまじいほどの頻度で、その人生には漂白の旅という印象すらある。中学入学と同時に太宰は津軽の金木町を離れ、青森で一人暮らしを始め、以後、高校で弘前、大学で東京と早くから転々と居場所を変える生活に入る。郷里を遠く離れ、東京に暮らし始めてからの太宰には、短い人生をめまぐるしい移動のうちに生きた印象がある。上京してから十年目にそれまでの生活を顧みて書いた『東京八景』には、戸塚に始まり、神田・同朋町、神田・和泉町、淀橋・柏木、日本橋・八丁堀、白金・三光町、杉並・天沼、船橋、ふたたび杉並・天沼、甲府、三鷹とめまぐるしく転居を繰り返した経緯が書かれている。こうした転居の多くは、共産党の地下活動に関わって留置場に入れられたり、同棲していた女性と別れたりといういわば青春の疾風怒濤の産物だった。
井伏鱒二の勧めで堅実な女性と結婚した後は、終戦末期から戦後しばらく津軽に疎開した以外はほぼ三鷹に定住していた。しかし、戦後の混乱のなかで愛人が出来てからはその下宿にいることが多く、そのまま玉川上水で心中している。旅行下手と称しながら定住にも不向きだったわけで、その一生は精神的にも物理的にも安定からほど遠いものだった。
流人の島・佐渡
『佐渡』はそんなふうに旅行下手であり、とりわけ一人旅の下手な太宰の人となりがよくあらわれた紀行文ふうの小説である。昭和15年11月16日、太宰は旧制新潟高校で人生はじめての講演を行ない、その翌日、案内役の高校生ふたりに見送られ、単身、霧雨の新潟港から佐渡に向かう。もともと青森県有数の大地主の御曹司で身の回りのことは人任せで育った太宰は、万事に実際的能力を欠き、一人旅もほとんどしたことがない。その前、東京から新潟に来るときも、新潟高校のOBの東大生に案内されてやって来ていた。そんな太宰が、単身で佐渡に向かったのはきわめて異例のことで、そこにはこの島への相当な思い入れがあったようである。作者とおぼしき「私」は語る。
「佐渡は、淋しいところだと聞いている。死ぬほど淋しいところだと聞いている。前から、気がかりになっていたのである。私には天国よりも、地獄のほうが気にかかる。関西の豊麗、瀬戸内海の明媚は、人から聞いて一応はあこがれてもみるのだが、なぜだか直ぐに行く気はしない。相模、駿河までは行ったが、それから先は、私は未だ一度も行って見たことが無い。ゆっくり関西を回ってみたいと思っている。いまはまだ、地獄の方角ばかりが気にかかる。新潟まで行くのならば、佐渡へも立ち寄ろう。立ち寄らなければならぬ。言わばば死に神の手招きに吸い寄せられるように、私は何の理由もなく、佐渡にひかれた。私はたいへんおセンチなのかも知れない。死ぬほど淋しいところ。それがよかった。」
破滅型といわれる太宰の面目躍如な文である。北海道に行ったこともある太宰だが、西日本についてはこのあと10年近く生きたにもかかわらず、静岡県より先に行くことはなかった。

さて、ツーリズムがさかんな現代と、太宰が生きていた時代では佐渡の印象はだいぶ違うかもしれない。佐渡は、現代ではゆたかな金を産出した相川の金山の坑道の遺跡が観光客向けの一大名所となり、意外に高く、雄大な印象すらある山脈(最高峰は金北山で1172メートル)、風光明媚な海、復活したトキ、豊かな海産物、温泉が待っていて、最速の船で行けば1時間で着いてしまう楽しい観光の島である。しかし、太宰のころの佐渡といえば、すでに就航していたおけさ丸のおかげで3時間弱という当時としては画期的な速さで行けるようにはなっていたものの、いまだ日本海の荒海に囲まれた絶海の孤島というイメージも生きていて、今日のように観光化された場所ではなかっただろう。
江戸時代にはもっぱら無宿者が送りこまれ、いったんそこで働けば数年を経ずに死亡する、文字どおり地獄のような労働環境で知られていた。また、何よりも佐渡といえば流人の島だった。順徳天皇や、文覚上人、日野資朝、日蓮、冷泉為兼、世阿弥などが佐渡に流されたことはよく知られているが、その他、名の知れないおびただしい流人が無念の思いを抱いて生きた島だった。太宰の時代はまだその歴史の記憶がなまなましく生きていて、そこに絶海の孤島というイメージが重なり、「死ぬほど淋しいところ」と呼ばれていたのだろう。
たぶん自明のことであるがゆえに小説には書かれていないが、太宰が惹かれたのは、親族から見捨てられ、人別帳から抹消され、人外の者となった無宿者たちが死地として送りこまれた地獄のような佐渡、そして流人たちが都への郷愁や望郷の念に苛まれて生き、絶望のうちに死んだ淋しい離島としての佐渡だった。もともと、太宰は弱者や敗者に深く共感し、同化するタチの作家である。特に順徳天皇や冷泉為兼のようなすぐれた文人、世阿弥のような芸術家が佐渡に流され、落魄の身をかこったことは太宰にとって我が身のことのように感じられたのではないだろうか。
美知子夫人は、無名時代の太宰がペンネームを決める必要に迫られたとき、友人が万葉集をパラパラとめくって見つけた太宰という言葉をそのまま筆名にしたと語った挿話を紹介し、そこに大宰府や菅原道真の配流に結びつく連想もあったのではないかと推測している。夫人によれば、実際、太宰は「配所の月」という言葉が好きで、戦時中、郷里の津軽に疎開したときも、「縁側につっ立って荒れた庭を見おろしながらあるポーズをとって、『これが「配所の月」というものだ』とせりふのように呟くのを聞いた」という。(『回想の太宰治』)文学仲間との歓談の好きな太宰が東京からいわば都落ちし、郷里とはいえ、話が通じる相手の少ない津軽に住んで自足しなかった心境がうかがえる。
しかし、東京での太宰もまた、別の意味で流謫の人だった。青森の芸者小山初代を内妻にしたことで、生家から分家除籍という義絶同然の処置を受け、さまざまな不始末によってしばらくは帰郷することもできず、望郷の念に身を焦がしていた時期の太宰にとって、東京もまた流人の心境をもって生きる場所だった。極論すれば、生涯のほとんどにわたって太宰はどこで暮らしていても、そこに安住の地を感じることができず、寄る辺ない思いに苛まれる人だった。結婚し、安定した暮らしを営むようになった太宰は許されてふたたび故郷の土を踏むようになるが、そこから生まれたふるさと探訪の紀行文的小説『津軽』は、太宰にしては珍しく和解のよろこびにあふれ、謙譲と感謝の気持をもって自身の出自である場所に向き合い、自分がまぎれもない津軽の子であることを確認するものであって、その多くが寄る辺なさと焦燥と絶望の表現である太宰の作品のなかでは、その向日性ゆえに貴重なものである。
1954年、東京に生を享ける。東京外国語大学~東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1986年より京都産業大学に勤務。トーマス・マンをはじめとするドイツ文学研究に励むかたわら、日本の作家にも関心をもっている。路地裏歩きを趣味とする。著書に『クライスト/愛の構造』(松籟社 1998年)、『三島由紀夫 異端の系譜学』(風濤社 2017年)など。