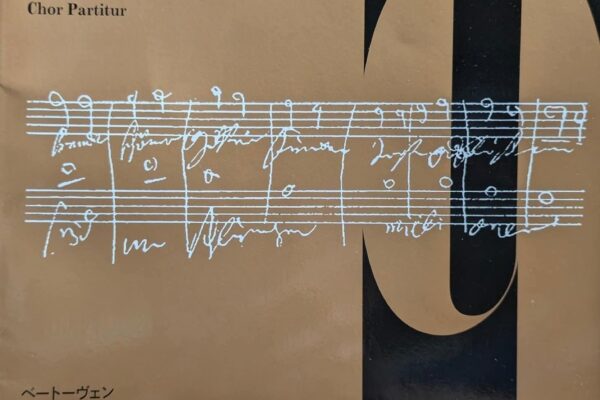「1.17」
今年も1月17日早朝に神戸市中央区の東遊園地に足を運んだ。「阪神淡路大震災1.17のつどい」に参加するためである。10数年前に報道の現場を離れて以降、ほぼ毎年この場所を訪れ、ただ合掌して家に帰っていた。だが、今年はカメラを携えて会場に向かい、感じたことをこのコラムに公表することにした。
地震発生から25年目という節目の年ということもあり今年は例年に比べ参加者が多く、会場の東遊園地は人をかき分けるようにしないと前に進めないほどであった。このつどいでは、毎年それほど広くない広場におよそ8000本の竹灯籠などを並べ「1.17」などの文字をかたどる。訪れた人々は灯籠の1本1本に火のついたろうそくを手向ける。午前5時を過ぎたころにはほぼすべての灯籠に灯が入り、少し高い位置から見下ろすと文字がくっきりと浮かび上がる。やがて場内のスピーカーから時報サービスの音声が流れ、午前5時46分が告げられる。場内は静まり鎮魂の黙祷がささげられる。

竹灯籠にはこれを用意したボランティアの人々によって墨で文字が書かれている。ほとんどは「希望」「未来」「絆」「心」など励ましや慰め、癒しの言葉である。ところが、ふと目に留まったふたつの竹灯籠に書かれてあった文字に衝撃を受けた。ひとつには「母」、そのとなりには「姉」とあった。ほかの竹灯籠に書かれている抽象的な言葉とは異質な具体名詞の「母」「姉」。これを書いた人は、さらに具体的な個人の名前を思い浮かべながら書いたのではないか。25年を経てなお深い思いを持っていることを母と姉に伝えるため、そしてそうした思いを持つものがここにいることを誰かに知ってほしいという願いも込めて竹灯籠に書き込んだのではないのか。そのメッセージはこの場を訪れた多くの人に届き、胸を打ったことだろう。6434人が犠牲になったと言われる阪神淡路大震災であるが、数ではなく、それぞれの固有名詞があり、それぞれの人生、それぞれの家族や友人があったことを改めて思う。

式典は例年どおり被災者を代表する方がその思いをつづった「追悼のことば」を読み上げる声が場内に流されるなどして短時間で終わる。その前後、一般の来訪者とほぼ同じぐらいいるのではないかと思われるほど多くの取材者が訪れた人に声をかけてそれぞれの思いを聞き出す。この場は震災に思いを持つ人とメディアとの出会いの場でもある。
一方、記帳所で受け取った1輪の菊の花を追悼施設の小さな池に浮かべるための列に並んだ時のことである。列は長く、時間にすると30分以上にもなっただろうか。低く会話を交わす声が聞こえる。私の直前に並んでいたのはともに一人で参列した中年の女性と高齢の男性だった。男性は地震の揺れの模様、直後の街の様子、その後水を求めて苦労した経験や代替バスに乗るために長時間列に並んだことなどを話す。女性は直接被災したのではない模様だが、どうやら看護師をしており震災への関心は深いようだ。男性の話に熱心に耳を傾け、丁寧に男性が心を開くように導いていた。
周囲に注意を向けるとあちこちで地震の直後やその後の暮らしなどについて近くにいる人たちの間で会話が交わされている。一期一会で終わるもの同士だからこそ話せることも多かろう。献花するまでの長い列が貴重な出会いの場になっていた。

地震があった日、私は神戸市垂水区の自宅からたまたま止まってくれたタクシーに乗って当時東遊園地の近くにあった読売テレビの神戸支局に向かった。到着したのは午前7時をすぎたころだったか。すでにストレートニュースの現場を離れ、土曜朝の報道番組のプロデューサーの職にあったが、なぜかその時は体が動いた。
支局のあったビルは倒壊こそ免れたものの、壁に無数の深い亀裂が入り、支局の内部は机や椅子、棚やロッカー、コピー機などそこにあったものがぐちゃぐちゃにかき混ぜられたような状態だった。駆けつけたカメラマンがようやく取材用のカメラを引っ張り出すのがせいぜいで、電話のありかもわからず本社にその模様を報告することもできない。後にわかったのだが、屋上に設置してあった映像伝送用のパラボラアンテナも崩壊して神戸からの映像を送るすべを失っていた。

そのとき支局に集まったのは私を含めて6人。2班のカメラ班を編成してとりあえず付近の様子を取材することとして、私は本社との連絡に当たった。支局の電話は使えない。近くにあったホテルに駆け込んだがそこも大混乱しており、電話を借りられる状況ではなかった。仕方なく記憶にあった電話ボックスに向かった。港に近くおしゃれな街並みに合わせて灯台をかたどった電話ボックスが設置されたのを記憶していたからだ。
すでに数人が列を作って家族や勤務先に状況を報告している。切迫した口調で安否を確認したり、これからどのようにするかを話し、一人一人の会話時間は長い。無言で頭を下げできるだけ早く切り上げるようにお願いする。ようやく順番が回ってきてデスクに神戸支局の状況を報告、本社からはこれまで見てきた周囲の状況を放送でリポートするよう要請される。目の前には電話を待つ列がすでに20人余りにも伸びて、それぞれ険しい目で終わるのを待っている。
リポートでは垂水区からの道中に見た長田区内の火災やビルに大きなひびが入っている様子などを話した。大げさにならないようできるだけ冷静に見たことだけを淡々と話した。しかし、私にはこれが大きな悔いとして残っている。なぜ「大変なことが起きているぞ!!!」と叫ばなかったのか。もっともっと大声で、感情をこめて伝えようとしなかったのか。たまたまではあるが、それを伝えることが出来るところにいながらそれができなかったことに、今でも痛恨の思いが消えない。
その電話ボックスは今もそこにある。写真に撮るとバックには新しく建てられた高層ビルが写り、街並みは美しい。街中で電話ボックスの姿を見ることはほとんどなくなったが、25年前と変わらない姿の電話ボックスがそこにある。まるで私に心の古傷を忘れさせないためであるかのように…。

フォト・ジャーナリスト 1952年、神戸市生まれ。1975年、関西学院大学経済学部卒、読売テレビ(大阪)入社。記者として警察・内政など記者クラブを担当。ディレクターとしてドキュメント番組(NNNドキュメント’83〜’86など)、プロデューサーとして報道番組(ウェークアップなど)を制作。報道局次長、コンプライアンス推進室長を歴任、2013年からBPO(放送倫理・番組向上機構)放送人権委員会調査役、青少年委員会統括調査役などを歴任。2018年フリーに。